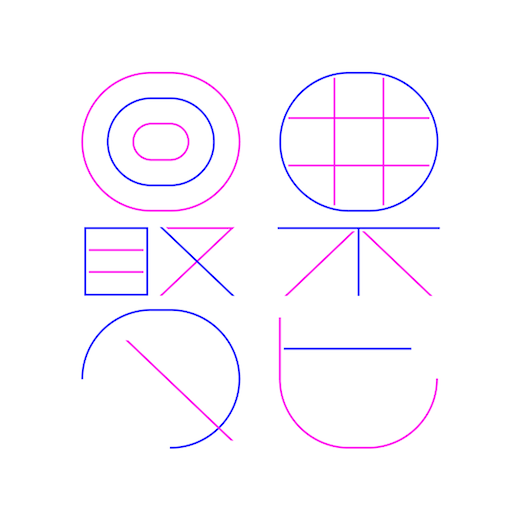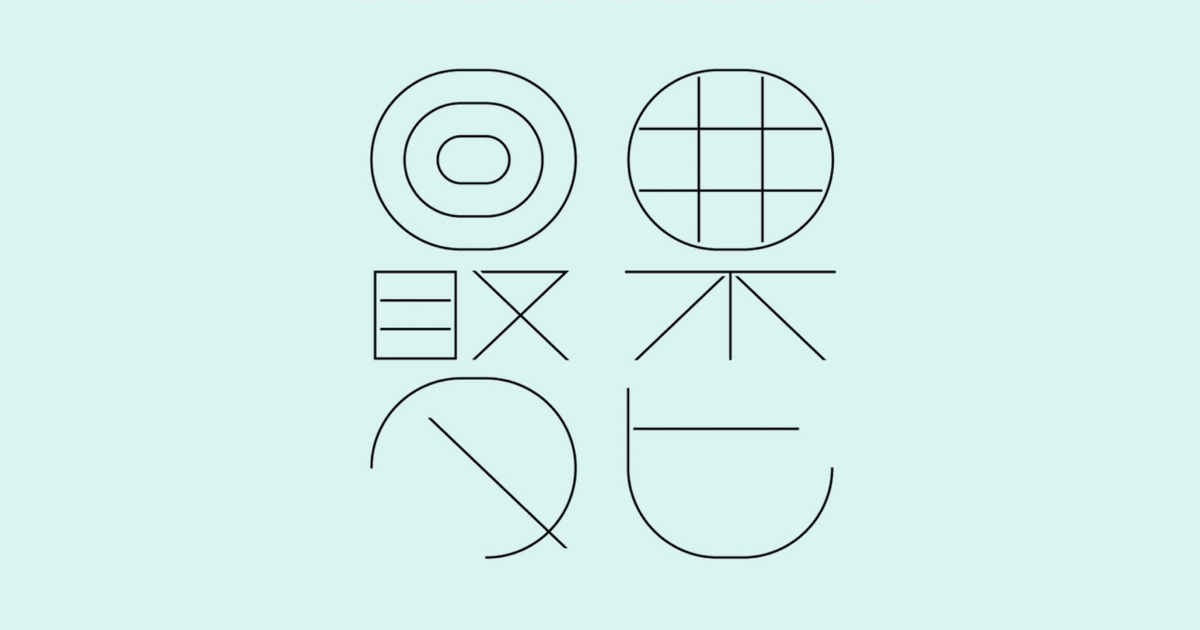100歳
としをとるということは、
ぼくが終わっていくのではなく、
世界が終わっていくということなのだけど、
きみがいつも出かける西の果てにはなにもなく、
白い海と白い空が混ざりながら光っている。
そこへ向かうきみの体と、
そこから帰ってくるきみの体が、
同じなのかはわからない。
ただ、きみはきみの家を知っていて、
鍵を持っていて、冷蔵庫の中身を覚えている、
だから、今晩もここで眠る。
ぼくが町の南を見たとき、空の左手が、
ビルの、白壁に定規をあてて、
影と光の境界線をひいた。
息を吸いながら、吐きながら、
その線がゆっくりと動くのを見まもると、
ぼくは、植物よりも動物よりもコンクリートが、
この世界にうまれるべくしてうまれた、
赤ちゃんかもしれないとおもう。
365日かけて、365回、
あの左手はひたいを撫でてくれていた、という、
そのことを知らずに、
生きてきていた。
ぼくらにはそれは、少なすぎたのか。
忘れることで、ぼくは、
ぼくの命を軽んじていたことになるのかなあ。
光がふる草原で、横たわれば、ぼくも、
光の一部として、星に降り注ぐことができた。
頬の果て、
思い出せないものが古い地層にしまいこまれ、
ぼくの体とともに、宇宙を、回転している。