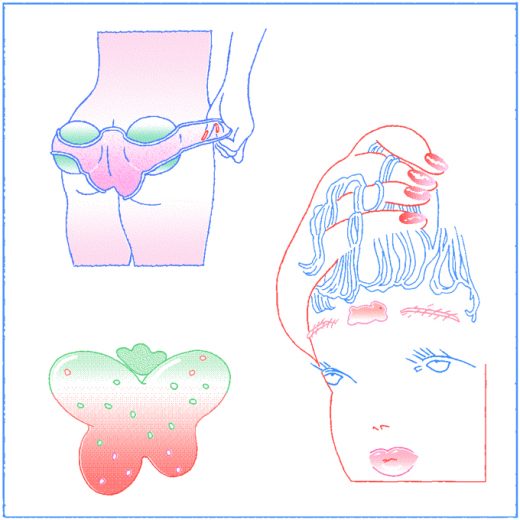高校生の頃、学校からすこし遠くの栄えた駅まで、わざと寄り道して帰った。一緒に歩いていたのは高校で一番最初に仲良くなった友達。入学して1週間のうちに、私はおすすめのBUMP OF CHICKENとthe pillowsのCDを、彼女はアジカンのCDを、それぞれ選びきれなくて10枚近くずつ一気に持ち寄っては貸し借りしていた。はちきれそうな袋をひいひい言いながら持ち帰り、歌詞カードを見ながら再生する。
きっと街中で偶然出会っても良いと感じた音だったのだろうけれど、新しい友だちのくれた音楽は、もっときらきらしていた。彼女の好きだと言ったイントロ、ライブでいつか一緒に聴きたい。覚えたら、二人で大声で歌いながら帰る。毎日寄り道を当たり前に繰り返す。私の背丈と彼女の背丈のちょうど間くらいの高さのすすきがゆれる。瞬きを繰り返し、みるみるあいだに鉄塔の先に夕日がぶすりと突き刺さる。
箸が転がってもおもしろく、マックフライポテト150円にあやかっていつまでもいつまでも端っこの席でノートを広げた。バンドを組もうよ、そうしたらこんな名前にしよう。軽音部に揃って入って、ぜんぜんうまくできないから一瞬でやめた。毎日の寄り道は続いていく。ドーナツ全品100円にあやかって暗くなっても向かい合う。私が小説を書くから、君に表紙を描いて欲しい。新しい話題に移ったっていつも実行には移されないそんな妄想の話で、前にも後ろにも進まないから楽しいままで、私たちはいつまでも笑う。
不器用で、周りにもうまく馴染めなくて、家族も先生も私たちの気持ちなんてわかってくれない。かっこいいと思う男の子もいないし、いても言ったらからかわれるだけだし、それなりに恋愛を謳歌する可愛くておしゃれなあの子の気持ちもわからないけど、私たちは私たちとしてふたりで固まっていたならそれできちんと最強だった。
ものすごく嫌なことがあった日には誘い合わせてカラオケに行く。あの子はコンビニ、私はファーストフードでせっせとバイトしてお給料をもらう。どこにだって一緒にいける。漫画を読んでも好きなキャラクターが全部同じな、私たちはほんとうに離れることはないと思っていた。
青春時代は人生の予行演習だとか、答えを見つけるための練習期間だとか、そういう一般論に素直に頷いてしまうときもある。今ではぜんぜんたいしたことない色々なことが巨大な苦悩に化けながら、耐えず私たちを苦しめていたから。家族とうまくやっていく方法も、クラスで孤立しない方法も、いわゆる普通の恋愛も、きっとそのうちわかるようになる。だけどあんなに何にもうまくいかないと思えた毎日が、どうしてずっと眩しいのだろう。くだらない嫉妬や価値観の変化で離れ離れになった友達の、あの横顔が好きだった。私たちは結局ごく普通の女友達で、無い物ねだりをしあってお互いのことを大好きではなくなってしまったのに、きれいな話なんか一切していなかったのに、どうしてずっと眩しいのだろう。
連絡先を交換してみた先輩がぜんぜん思っていた人と違ってうんざりしたとか、化学のテストが最悪な点数だったとか、お父さんに進学先のことをわかってもらえなくてムカついたとか、悪い出来事は全部私たちがしばらく愚痴ったあとに笑い飛ばすためのおやつみたいなものだった。苦悩や矛盾や苛立ちなんて、一緒にいたら最強の私たちにとっては所詮その程度のものだった。
映画『レディ・バード』の主人公クリスティンには、最高な女友達、ジュリーがいる。いつも一緒に愚痴と妄想を語り合いながら、当たり前に一緒に帰る、少しぽっちゃりしていて、口がよく回る女の子。クラスの噂も部活選びも、すけべな話も全部あけすけに話しては、転がりまわって笑い合う。

『レディ・バード』/Merie Wallace, courtesy of A24
私はそんな二人が懐かしくて、やっぱりああいう記憶を何よりも眩しく感じることが、正確なことだったのだと嬉しくなった。クラスのヒエラルキー、恋愛欲のめざめ、思春期特有の飽きっぽさともともとの破天荒な性格も、どれも過剰に意識していけば、青春時代における幸福な関係はすぐに崩れる。私たちはこうして、小さな崩壊を繰り返しながら自分という生き物を調査する。この生き物にとって、本当に大切なものとはなんなのか、失くしながら探していく。絶対に言うべきじゃないセリフを口にしてから、それが絶対に言うべきじゃなかったセリフだと解る。どうしようもない、何も生まないくだらない失敗をくりかえして、答えにたどり着いていく。

『レディ・バード』が私にとって最高な映画だったのは、辿り着くべき答えよりもそれまでの悩ましい日々自体を物語の本質として誇らしく飾ってくれていたからだ。自分で自分に“レディ・バード”と名をつけて、自由になりたいと羽ばたき喚いたあの日々を、そっと振り返るエンディングにたどり着いてもなお、ああ、あの騒いでいたこと自体が答えだった、たどり着こうとじたばたしていたこと自体が人生というものの本質的なきらめきだったのだと、鮮やかに感じさせてくれる映画だった。


女友達と過ごす時間って、場合にもよるのだろうけれど、いつもどこかへ向かう途中の時間のような気がしている。いつまでもいつまでも二人きりで日常をやり過ごしていけたなら、それもまた素敵なことなのかもしれないけれど、ほとんどの場合いつか離れ離れになることになんて気づいている。卒業したり、引越しをしたり、就職をしたり、結婚をしたり。私たちは自分の道をつねに選び取りながら、選び切るまでのほんの隙間に、永遠みたいに心を交わす。人生をやり過ごす。私たちは離れ離れになるシナリオの上を歩いていたのかもしれない。ずっと一緒なんて無理だもんね。そんなふうに思いながらも、涙が出ないのは、あなたが幸せでいるのならそこが私のいない場所でも構わない、って言い切れるような種類の愛を、友情と呼ぶからなのだと思う。

左からシアーシャ・ローナン、ルーカス・ヘッジズ、ビーニー・フェルドスタイン、監督のグレタ・ガーウィグ
映画を観た帰り、あの頃の親友とよくたむろしていたチェーン店のハンバーガー屋で夕飯を食べた。私たちは不器用で、自分たち以外の世の中の様々な要素のことを漠然と「世界」と呼び、文句と希望を交互に話し、いつまでも帰れない二人だった。きっと、あの頃探していた答えみたいなものに、いつからか何度もたどり着いてしまっているけれど、君といたあの角の席がまぶしい。射し込んでいた夕日がそのまま君の色になった、君のいた記憶のその先を今も歩いている。
君に私の知らない彼氏ができていたとして、その人に可愛い自分を見せようと努力しているとしたって、私、大人気なくひっそり思う。
私が見ていた君が一番可愛かった。
大声でパンクロックを歌い、長い手足を振り乱し、たくさん食べて、自分は可愛くないと拗ねる、君の一番かわいいところを全部知っていた。そういう一秒一秒が、人生を美しさという観点で見たときの答えに他ならなかった。絶え間ない答えの連続の中を生きていた。一秒ごとに私たちは、答えを踏んづけて歩いていた。放課後の道を、きらめきを引きずりながら歩いていた。映画の中の青春と、私の青春の共通点を星座のように結びながら、あの日の放課後を思い出すように、なるべく長く歩いて帰った。瞬きを繰り返しながら。