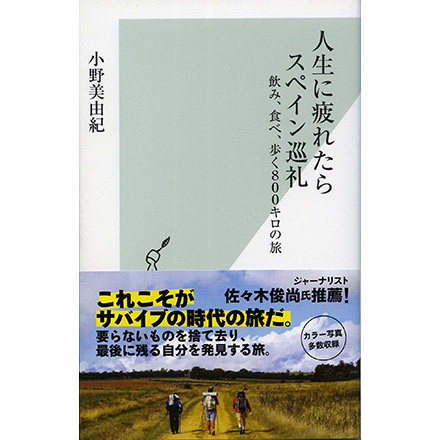こうして、私には“親友”ができた。
エージェントによれば私たちの相性は78%だったらしいが、私たちはそれよりずっと大きなものを手に入れた気がした。
私たちはしょっちゅういろんな場所に出かけた。映画、カフェ、買い物、全ての好みが一致していた。
私は韓国のバイオレンスアクション映画とB級ホラーを見るのが好きなのだが、彼女も密かにそれを愛していた。「これまで誰にも言ったことがなかったの、友達と本当に見たい映画を一緒に見に行けるなんて初めて」と彼女は嬉しそうに言った。
同じくらいの中流家庭、同じような偏差値の女子校、同じような中堅私立女子大を出て、同じような良くも悪くもない企業に勤める。
これまでの友達とは得られなかった安心感を、彼女といると感じられた。
メッセージの頻度、遊ぶ頻度、相槌のタイミング。全てがぴったりだった。
どうして私たちがこれまで出会わずにいたのか、不思議なくらいだった。
なあんだ。友達を作るのなんて、簡単だったんだ。
教室に押し込められ、同じ制服を着させられていた頃は、友達を作るのは簡単だった。“なんとなく、おんなじ”相手とひとかたまりになっていればよかったのだ。
けど、社会に出たらそうじゃない。“ちがう”ところから、始めないといけない。私にはそれが怖かった。
マッチングサービスによって同じ制服を着せられ、78%という数字によって同じ教室の隣同士の席に座らされた私たちは、これ以上にないってぐらいに安心して打ち解け合え、互いを「親友」と認められるのだった。
ある休日の午後、映画を観た帰り、私たちは渋谷の街を歩いていた。
映画は概ね面白く、私たちの感想は概ね一致していた。私は映画それ自体に対してよりも、彼女と感想がかぶっていたことへの興奮で胸を弾ませながら、次は何を観に行こう、と考えつつ坂道を下っていた。
その時だった。
あ、と彼女が一軒の店を指差した。
「ここね、別の親友の子が美味しいって言ってたよ」
一瞬、何を言われたのかわからなかった。
「今度、○○ちゃんも一緒に行こうよ」
「親友って?」
思わず真顔で聞いた私に、彼女は少し不思議そうな顔をした。
「ああ、他の“親友”の子。○○ちゃんと、同じサービスで出会ったんだ」
さっと血の気が引いた。私は彼女と出会って以来、律儀にあのサービスの利用を停止していた。
その子はね、フィギュアスケート鑑賞が好きで、と、彼女はこともなげに聞いてもいないプロフィールを話し出す。
私はポケットの中でスマホを握りしめた。
「やっぱりさ、出会いって大事だよね」と彼女は嬉しそうに言った。
「あのサービスでいろんな人に出会ってから、私、人生変わったもん。やっぱり友達って、多いほうがいいんだね」
来週は別の約束があるから、再来週、また会おうね。……そう言いながら、彼女は駅の人混みの中に消えて行った。
その背中が見えなくなった途端、私は慌てて近くのカフェに駆け込み、スマホを取り出しエージェントのサービス画面を開いた。
もっとたくさん、“親友”を作らなければ。
それから私は何人もの相手とエージェントを介して出会った。
DNAを調べる追加のオプションにも課金した。
会う相手、会う相手、みんな私ともっと仲良くなりたいって言ってくれた。
どんな言葉を投げかけたら、みんな私を好きになってくれるのか、次も会いたいと言ってもらえるのか、だんだん分かり始めていた。
友達って、多いほうがいいんだねーー。
「たくさん出会えば出会うほど、ぴったりの相手に巡りあう確率も高まりますよ」
エージェントは最初と変わらない笑顔で言った。
「こんなに多くの人が登録しているのですから、会わなければ勿体無いでしょう」
きっともっと、良い相手が私にはいるはずだ。
一生、ずっと一緒に居られるような、何があっても裏切らない、100%の女友達が。
シャワーを浴び、寝る前にスマホを見る。LINE通知が3件。きっとあの子とあの子とあの子から、週末遊びに行く予定についてのメッセージだ。
それとは別に、着信が5件。
途端に鉛のような重たい気分が胸の内側に広がる。それを振り切り、私は着信は開かずに彼女たちのメッセージに返信をする。
大丈夫。私はもう、あの人を相手にしている時間なんて無いんだから。
最初に「親友」になった彼女とは、次第にLINEのやり取りも、遊ぶ回数も減って行った。
- NEXT PAGE彼女の訃報が届いたのは、数か月後のことだった。