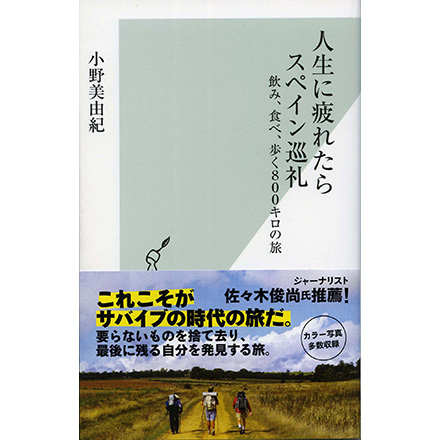彼女から突然呼び出されたのは、会社から家に帰ってきてすぐ、木曜の夜11時だった。
「今すぐうちに来て」という彼女のLINEに、私は脱いだばかりのコートを羽織り直すと家を飛び出した。
初めて踏み込む彼女の家は、彼女から受ける印象そのものだった。平凡なのに、どこかしらずれている。玄関マットと調度品のちぐはぐな色使い。靴箱の上にはチラシと空き瓶の山玄関から続く廊下には使い古された掃除用具が放り出されている。
リビングのドアを開け、その光景を見た時にも、不思議と私は驚かなかった。
「ああ」と私は言った。
「やっちゃったの?」
鼓動は疾っていたが、不思議と脳の一部はきんと冴えていた。
「うん」
彼女は青白い顔をしてリビングに突っ立っていた。
足元には、彼女と背格好のよく似た老婆がーー彼女の母親だったものが転がっている。
「いつもと一緒で、口論になって……あなたにはもう会うなって言われて、それで」
「どうするの」
彼女は俯いたまま何も言わない。ごわごわとした髪が汗で頰に張り付き、彼女の表情を隠している。
ふぅーーー。
私は大きくため息をついた。
次に言うべき言葉はもう、わかっていた。
「埋めよう」
彼女が顔を上げる。前髪の隙間から、不思議に光る大きな黒い目がのぞく。
「車で来たんだ。なんか、必要になりそうな気がして……うちの実家さあ、埼玉の山奥なんだよね」淡々と、私は彼女に説明した。「裏手に誰も入んない薮があって、そこに埋めれば」
「だめだよ」
彼女は目を細めて首を振った。奇妙に口元が歪んで、笑っているみたいに見えた。
「この人ね、外面だけはいい女だったの。近所への挨拶も欠かさなかったし、しょっちゅう家にも人を呼んでた。その度に私の悪口を振りまいてた……『いい歳して独り立ちもできない役立たずの娘』だとか『「冴えないし取り柄もないから結婚もできない』」だの、勝手な言い分を」
彼女は拳を握りしめた。
「だから、いなくなったらすぐにバレる」
「だったら、どうすんのよ」
私は苛立ちながら彼女に尋ねた。
「だったら、どうしたらいいのよ」
ーー助けが欲しいわけじゃないなら。
どうして、あなたは私を呼んだの。
彼女はじぃっと私の目を見た。視線がかち合う。あ、この目、どこかで見たことある、と私は頭の片隅で思う。
不意に、彼女は振り返るとキッチンに向かった。カウンターの向こうで何かを手に取り、こちらに戻って来る。
彼女が持っていたものを見て私は目を見張った。
それは掃除用のゴム手袋と、銀色の大きなフライパンだった。
「正当防衛ってことにしたいの」と彼女は言った。
「自首は、する。でもその前にあなたに手伝ってほしいの」
正当防衛、と私は思わず繰り返した。
「介助者による殺人はね、叙情酌量で減刑される可能性が高いの。特に、日頃から暴行を加えられてたって証言さえできればね。あなたは、日頃から私がこの人から暴力を受けていたって証言してくれたらいい。それから」
これで私を殴って、と言いながら、彼女はぐい、とフライパンを突き出す。
「この人が私をこれで殴った。私は命の危険を感じて思わずやり返した。この人ね、この一週間比較的落ち着いてて、あざも消えてるしさ、物的証拠が欲しいのよ。……自分でやろうとしたけど、うまくできなくてさぁ」
「無理だよ、そんなの」
私は言った。声が震えていた。
「当たりどころが悪かったらあなたが死んじゃうよ。もしそうなったら、私」
ーーどっちみち、あなたは私の前からいなくなってしまうのに。
「あなたの細腕で殴られたくらいじゃ、死なないよ」
彼女は馬鹿にするような目でこちらを見た。
「もっとひどいこと、されたことあるもん。……頭がおかしい人ってね、本気で殺そうとしてくんのよ。どっからこんな力出んのってくらいにね」そう言いながら、視線を下ろして足元の死体を睨みつける。まるで邪魔な粗大ゴミか何かみたいに。
「ねぇ、お願い」
彼女はそう言いながら、さらに私に近づいた。
「さっきね、ちゃんと指紋もつけといたの。あなたとこの人は背格好も近いし、きっとバレないと思う」
ぬるり、とした彼女の手が腕に触れる。
水っぽくて、熱くって、どこまでも、深く、食い込んで来そうな。
「こんなこと、あなたにしか頼めない」
すぅ、と空気が薄くなる。心臓が跳ねる。頭より先に喜びを予期して、身体じゅうが総毛立つ。
次に彼女が言う台詞を、私はもう、知っている。
「……親友の、あなたにしか」
「……どうやったらいいの」私は聞いた。
ここに立ってやって、と言いながら、彼女はキッチンに回り込んだ。
「ここに倒れこむから。こう、ガシャーンって」彼女の後ろには、埃を被った調味料の棚と、洗っていない食器が山盛りになっている。
その前に、と言いながら、彼女はポケットから煙草を取り出し火をつけた。
「タバコ、吸うんだね」
「うん、一人の時だけね」
「プロフィールには、書いてなかった」
ごめんね、と彼女は小さく言った。
「……喫煙者じゃない方が、友達、作りやすいかと思って」
私はゴム手袋をはめた。触角の鈍くなった手のひらでフライパンの柄を握りしめ、手をぶらぶらさせ、スイングの加減を確かめる。
「どこ?」
「ここ」
彼女は指先でこめかみをさす。
ボサボサの髪。うつむきがちの顔、たるんだ体。皺だらけのTシャツ。
最初の頃、私は彼女を私みたいだと思った。
でも違った。
彼女は、まるでーーー
「手加減しないでね」
「わかった」
タバコを吸い終わり、三角コーナーに放り込んだのを見届けてから、
私は目の前の女の頭に向かって、
「行くよ」
全身全霊の力を込め、テフロン加工のフライパンをフルスイングで振り下ろした。
- NEXT PAGEねっとりと、指と指の隙間を鮮やかなピンクと白の混合物が埋め尽くす。