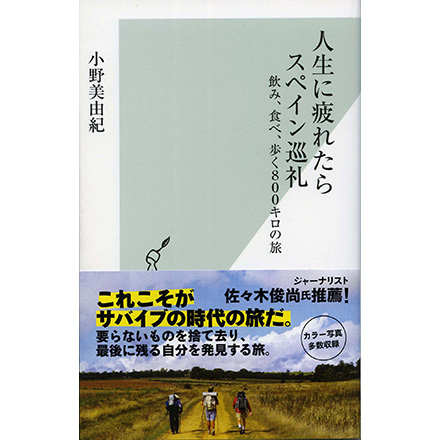ねっとりと、指と指の隙間を鮮やかなピンクと白の混合物が埋め尽くす。
ボウルの中のそれは皮膚を心地よく包み込み、絡みついて離さない。
私はその甘美な感触に、思わずうめき声をあげる。
みち、みち、みち。
ずっとこねていたいくらいだ。
まるで私のかたちを百も承知しているみたいに、ぴったりと吸い付き服従する、柔らかな奴隷。
そのうち、私の手なのかそれなのか、わからなくなる。
コンロのグリルからは鮭の香ばしい匂いが漂ってくる。かけっぱなしの鍋の中では里芋の煮っころがしがじゅうじゅうと小ぎみ良い音を立てている。
今日のお弁当のメインはハンバーグだ。
ああ、彼女にも食べさせてあげられたら、どんなにいいだろう。
彼女は自首し、異例とも言える短さの実刑判決を受けた。
私の証言によって、日常的に暴力を受けていたことが立証され、また正当防衛であることが認められたらしい。
週に一度、塀の向こうにいる親友に会いに行くのが私のルーティンだ。
刑務所の前には広い公園があって、私は面会を終えた後、いつもそこのベンチに座ってお弁当を食べる。
面会は基本的に平日の昼しか許されていないから、私はそのために仕事も変えた。お金はないけれど、週に一度必ず用事のある生活というのはなかなかにハリがあっていい。何より、私以外にそれをやる人がいないことがわかっているタスクを行うことが、どれだけ気分のいいことか。
30分の間、私たちはこれまでと同じように、たわいもない話をし、ドラマの話をし、行きたい旅行先について想いを馳せる。2人の共通の話題なら、どれだけ探しても尽きることはない。
カフェからガラスの壁越しに、場所が移っただけだ。
看守からは「まるで恋人みたい」って言われてるらしいけど、冗談じゃない。そんなヤワなものと一緒にしないでほしい。私たちはもっともっと、強い絆で結ばれている。なんてったって、98%の“親友”だもの。
一方で、私は彼女が入所してからすぐにまたエージェントサービスに登録した。彼女のことは好きだけど、彼女はああなる前に、もっとたくさん、友達を作っておくべきだったと思う。友達の数は、多ければ多いほどいいのだ。
私は新しくできた“親友”たちの願いをなんでも聞いてやる。夫の浮気の証拠を作って離婚したいから、って頼まれれば、相手の配偶者とも寝るし、お金を貸してと言われたら無理をしてでも貸してやる。
みんな「あなたがいて良かった」って言ってくれるけど、そんなの当たり前だ。だって、友達ってそういうものでしょう。
あの時、彼女に向かってフライパンを振り下ろした瞬間私が考えていたのは私自身についてのことだったーーつまるところ、私は「こういう」女なのだ。
自分よりも弱くて、惨めで、すがりつく相手の面倒を見ることでしか、自分に価値を見出せない、そういう人間とじゃなきゃ安心して一緒にいられない、そういう女。
彼女はとっくにそのことに気づいてた。
その上で、彼女はぴったりの役割を私に与えた。
私が彼女を理解するずっとずっと前から、彼女は私のことを、私以上によくわかっていたのだ。
あの時——向かい合った時の彼女の目はこう言っていた。
「あなただって、私みたいな人間を必要としてるんでしょう」
ともだちってなんだろう。
子供の頃は、お揃いのリボン。シロツメグサの花かんむり。チョコレートの宝箱。モンシロチョウの二枚の羽。ピンク色の小指の爪。二人だけの秘密の恋。先生への嘘。嫌いな女の子の悪口。
子供の頃に知っていた形とは遠く離れてしまったけれど、私には今でもそれが必要だ、だってだって私はこんなにもいびつでちっぽけで、一人じゃ生きていけなくて、ともすれば罰ゲームかってぐらいに不公平な不幸が降りかかるこの世界でそれでも生き残ってかなきゃいけなくて、だからだからだから私たちは互いに手を握り合い、褒め合い、助け合い、慰め合い、互いのダメなところには目をつむり、なにそれ最悪、とかそれちょーいいね、とか褒め合って、都合の悪いことは全部無視して、ま、しょうがないかあ、なんて言いながら、子供の頃に夢見たあの原っぱを、手と手をとって目指す相手を欲するのだ、相手ごと私の傷も弱さも丸ごと抱きしめて、間違ってないよって囁いて、世間の声は聞こえないふりをして、この、ヘヴィで、醜くて、うんざりするほど不公平な世界に、「ばぁか」って二人で舌を出すために、互いが互いを必要としてるって証明を、私たち親友だよねって目配せを、抱擁を、承認を、互いに「いいね!」をし合う相手が必要なのだ、だってだってだってそうじゃなきゃ、私は“あの人”みたいになってしまう、あの人と二人、暗い世界に取り残されてしまう。
ほつれたセーター。ボロボロのエプロン。酒臭い匂い。狭いキッチンで一人、包丁を見つめていた“あの女”ーー世の中への恨みつらみを、父が出て言った後には彼への呪詛を、両親への怒りを、幼い私に吐き出す以外に生きる支えのなかった、暗い目をした“あいつ”。
キッチンシンクの横で、またスマホが震えている。今日これで10回目、人生では何千、何万回目の、よく見慣れた番号。
番号の下に表示された×ボタンを、私は軽快にタップする。
ごめんね、お母さん。今の私には、あなた以外に私を必要としてくれる人が、たぁっくさん、いるんだ。
次の着信が来る前に、素早く“通話”の設定画面を出す。さっきの番号を“着信拒否”設定に切り替えると、私はかつてないほど軽やかな足取りで、アパートのドアを押し開け春の日差しの溢れる外へと踏み出した。
- 3
- 3