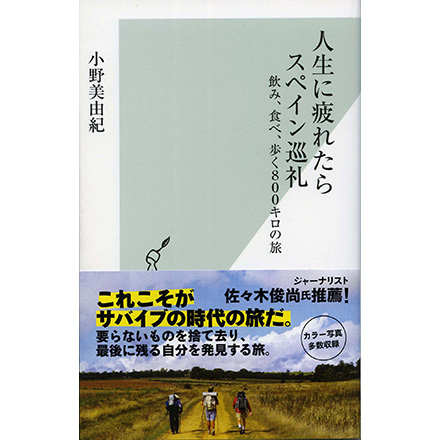マッチングアプリで「本当の親友」を見つけたいと願う「私」は、「78%の友達」との別れを経て、さらに高相性の相手を探し求める。その末に出会った究極の「親友」、ぐつぐつと煮詰められた二人の間柄で起きたひとつの事件。作家・小野美由紀さんが「友達」を書く短編小説の後編です。
前編はこちら
私はまた、サービスを通じてさらに多くの人と出会うようになった。1年でマッチした人数は100人を超えた。
とにかく、親友が欲しかった。100%の友達が。
柔らかな毛布のように、過不足なく私の隙間をぎっちりと埋めてくれる親友が。
その人と出会ったのは、10月の終わりのある雨の日のことだった。
マッチング率98%。それが、私と彼女が叩き出した数字だった。
会うのが怖いぐらいだった。
そんな完璧な親友が、この世に存在するなんて。
彼女は人気のないカフェの片隅の、トイレの横の席にポツンと座っていた。
あまりに存在感が薄くて、最初私は見逃しそうになった。いかにも安物の、すそのほつれた灰色のフリース。子供が履くようなぼろぼろのスニーカー。贅肉のたっぷりついた体を丸めて紅茶をすすっている。これまで会った子たちの中でもとびきり冴えなかった。
よほど理由をつけて帰ろうかと思ったけど、私は、そうすることができなかった。
「98%の親友」を斬り捨てるのは勿体無いような気もしたしーー何より顔を上げた彼女があまりにも恍惚とした表情で私を見たからだ。
彼女は目が合うと、上目遣いでゆっくりと顎を引いた。化粧を施さない荒れた肌に落ち窪んだ目。微笑みのつもりなのか、片頬をわずかに引きつらせ、小さな声で言った。
「すぐに、わかった」
鳥肌が立った。
粘り気があり、一度鼓膜に絡みついたら離れないような声だった。
彼女は小さな声でぼそぼそと、けど一心不乱に身の上話をした。彼女が動くたび、油っぽい長い髪が両ほほの横でごわごわと揺れた。彼女の話はつまらなかったが、それでも私はウンウンと熱心にその話を聞いてやった。彼女と一緒にいることに、これまで感じたことのないほどの安堵を不思議と覚えはじめていた。
磁石のように、私は彼女に吸い寄せられた。
私たちは、それから多くの時間を共有するようになった。
彼女は年老いた母親と2人暮らしで、恋人もおらず、結婚歴もなく、もちろん、子供もいなかった。パート以外の仕事を経験したことがないのは、母親が精神疾患を抱えていて、彼女が面倒を見ないと一人では生きていけないからだと言った。彼女自身に自由な時間はほとんど無かった。私たちが会うのはいつも、彼女の暮らす街の駅のチェーンの喫茶店で、他の子たちのように、映画も、買い物も、表参道や青山の素敵なカフェも彼女には無縁だった。
でも、そんなの大したことじゃなかった。私たちは会って会って会いまくった。夜、彼女の母親が寝てからのわずかな時間に私たちはLINEをしまくったし、少しの時間があれば私は彼女の元に駆けつけた。いつのまにか、他の「親友」たちとは連絡を取らなくなっていた。
マッチング率98%の意味を、私は彼女と親しくなってすぐに理解した。
彼女と私はよく似ていた。
表面じゃない。
どこに住んでいるとか、見た目とか、趣味とか、そういうことじゃない。
言葉を発したあと、相手の反応を確かめるようにこわごわと下から見上げるくせとか、
ふとした拍子に、世の中への不満や恨みが愚痴となって溢れ出すこととか、
几帳面で、1円単位で割り勘にして、相手に絶対に奢らせないようにするところとか。
同じ地下の水脈を分け合った2本の川のように、私と彼女は本質的にそっくりだった。
「私たちってそっくりね」と彼女はよく言った。5つ年上だったけど、いつもどことなくぼんやりしていて、私よりずっと幼く見えた。その発言に多少プライドを傷つけられながらも、一方で私はひどく納得もしていた。
なあんだ。
やっぱり、私の「親友」になるのは、こういう人間なんだ、って。
こんなに完璧なマッチングは珍しいですね。とエージェントは言った。
「おめでとうございます。親友は一生ものの財産です、どうぞ、大事になさってください」
ある日、彼女は右ほほを腫らして待ち合わせに現れた。
どうしたの、と聞くと、少しのためらいののちに「母がやるの」と彼女は言った。
「最近、特に情緒が不安定で」
母はね、私があなたと会うのが嫌みたいなの、と彼女は続けた。
「私のこと、話したの?」
「うん」彼女は私の顔色を伺うようにおずおずと見上げた。
「そんなお里の知れない相手と会うなんてやめなさいって」
「……誰か、相談できる相手はいないの?」
私は苛立ちを感じながら言った。彼女の母親に対しても、言いなりの彼女に対しても。
「ソーシャルワーカーとか、市役所とか、そういうところに」
「ないよ」彼女はその時だけ、やけにはっきりとした口調で言った。
「そういうところって、本当に重症な人しか相手にしてくれないの。それに、私が行ったところで、お母さん思いのいい娘さんだね、で済まされちゃう」
「入院は?」「……母が嫌がる」
彼女は急に身を乗り出し、私の手首を掴んだ。
「でも、私はあなたと会うのをやめたくないの」
ヌメッとした、脂肪に包まれた手が吸い付く。そのまま一生、離れないんじゃないかと思うぐらいに、強く。
「こうしてあなたが話を聞いてくれるだけで、すごく助かってる。……本当に、あなたと知り合えてよかった」
当たり前だよ、と私は言った。みぞおちのあたりから、えも言われぬ恍惚が湧き上がるのを感じながら。
「私たち、友達だもん。なんでも話して……お母さん、早く良くなるといいね」
彼女と会う頻度はますます増えた。何かを振り切るように、私たちは会った。彼女の母親の病状はますますひどくなり、時々会う直前にキャンセルされることもあった。
「ごめんね。母の病気さえなかったら、もっと会えるのに」
彼女はしょっちゅう、あざを作って来るようになった。手首や、首、目の上。暴れる母親を止めようとして、こうなるのだとよく言っていた。私は心配し、いろいろな手立てを講じたが、その度に彼女は決まって、その話題を打ち消すように言った。
「あなたがいてくれてよかった」
それを聞いた途端、私は何かを言う気が不思議と失せていくのだった。
- 1
- 3