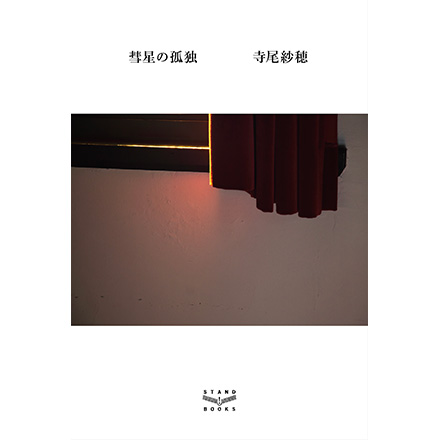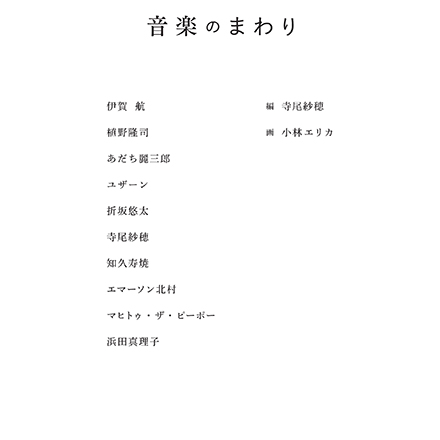これまでに2冊、南洋の本を出している。1冊はサイパン、もう1冊はパラオ。しかし、どちらも本になる予定はないまま取材を始めた。それはただ知りたかったから。急がなければ、戦前の南洋を知っていて、日本語を話せるチャモロ人やパラオ人のお年寄りたちが亡くなってしまう。サイパンについては15年以上前、学生時代から調べていた。かといって卒論や修論のテーマとは違う。いうなればそうやって気になることを調べていくのが、私の趣味であり、「好き」だった。
やがて、4年ほどたって長女を産んだ。しばらくして長編連載をやってほしいという依頼が『真夜中』という季刊誌から来た。話をくれた編集者は、私のブログや他雑誌で書いたエッセイを読んでいてくれたらしい。そのとき、私はサイパンについて前から調べていたので、そのことが書けますというと、連載の話が進んだ。現在は休刊になってしまったが、実験的なその雑誌は、修論がまぐれあたりのように新書になった1冊を除けば書き手としてたいしたキャリアのない私に、驚くほど長い枠を確保してくれた。3か月に一度振り込まれる原稿料は、当時暮らしていた2LDKのマンションの家賃代くらいにはなったので、家計がだいぶ助かった。
子育ての峠を越えてようやく行きたかったパラオ取材に向かったときは、最後にサイパンに行ってから10年以上の月日が経っていた。パラオ行きも安くはなかったが自腹で行った。すると帰国後、短いエッセイの依頼をくれた集英社の編集者と打ち合わせで会うことになり、パラオの話をすると、連載を是非ということになった。パラオ取材はその後もう一度行って、最終的に最初の渡航費用は連載の経費から出してもらうことができた。
人は、すでに動いている人間に興味を持つ。これが「取材に行って文章書いても、誰も注目してくれなかったら、そこにかけた費用はこれだけの損になるなあ」などマイナス思考で考え込んでいたら、運は開けないかもしれない。自分が気になること、やっておきたいこと、会っておきたい人、見ておきたい風景があるのであれば、即実行でよいのだと思う。それは損得の話を超えて、自分自身の知識や興味の幅を広げ、結果的に人の注目を引き、その熱や思いが伝われば、仕事の幅をも広げるかもしれないのだ。
友人に、新宿で野宿をしているKさんというおじいさんがいる。Kさんは『ビッグイシュー』という路上販売の雑誌を売ったり清掃の仕事をしたりして暮らしながら、ソケリッサという路上生活経験者による踊りのグループにも参加している。『ビッグイシュー』の販売というのは、一日駅前の道に立ち尽くして買ってくれるお客さんを待つ仕事だ。しゃがみこんでは売れるものも売れない。暑い日も寒い日も販売員さんたちは道に立つ。当然年齢を重ねればきつい仕事だ。
それでも、Kさんは販売後の踊りの練習について、練習始まる前はしんどいなと思うんですが、始まってしまうとそんなこと忘れてしまうと語ってくれたことがある。私はこの話を聞いたとき、好きなことをするとき、人の力は100のうち50しかエネルギーが残ってないと思っていても、一瞬で100や150になり得るんだと思った。これもまた、Kさんが連日の立ち仕事のために、少しでも休む時間を増やそうとか、立ち仕事だけでも大変なのに、踊りの稽古なんて無理だろう、踊ったところで金がもらえるわけでもない、など損得や苦楽だけで物事を判断していたら、できないことだ。結果的にソケリッサの活動は近年じょじょに注目と共感を集め、おじさんダンサーたちはブラジルまで公演に行ったり、公演売り上げをギャラとして分配してもらえるまでになっている。
50しかないと思われたエネルギーが実は100や150にもなるという話は、私が音楽と執筆と子育てを並行してやってこれたことにも関わるだろう。一人ぼっちのときも、人生を投げ出そうとしたときも、子どもたちが生まれてろくにライブの練習ができなくなったときも、歌うことと書くことはやめなかった。一日が本当に24時間ですか、と聞かれることもあるが、別段、時間管理がうまいわけでもない。自分のエネルギーの限界値を勝手に見積もらなかったというだけだ。やりたいことは、やめない。けれど、自分が曲がりなりにも表現や子育てを続けられている本当の要因は、そういう自分の意志や能力以外のところにある。
健康体に生んでもらい、親は大きな借金も病気もない。近所に母がいて、ライブや取材が入れば3人の子どもたちの子守をしてもらえる状況。いくつもの幸運が重なって残せたキャリア。状況は一人ひとり違う。今平穏な人も、状況が整わず波風の中にいる人もいると思う。ただ、なしえたことの幸運、なしえない状況にあることの限界を把握し、身体を通り過ぎていく経験を受け止め、表現していくことで、得られるものや生まれていく関係があるはずだと思う。
いかなる状況でも「好き」を手放さず、そのときできる形で続けたり、あたためておくこと。その「好き」が色あせぬ本物であれば、いつ晴れるともしれない霧のような時期を抜けて、いつかきちんとその人の人生を彩るものになっていくような気がする。