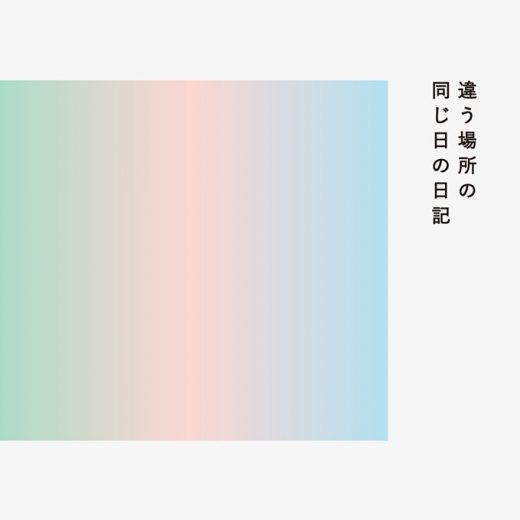4月5日(日) 豆を煮る詩人たち

詩人の新川和江さんのエッセイ集『朝ごとに生まれよ、私』(海竜社)を手に取る。数日前、荻窪の古書店・ささま書店の閉店セールで見つけた一冊。1986年刊行なので、私より5歳年上だ。
第2章、「女のつぶやき」と題された中の「豆を煮る」という文章が面白い。女友達との電話口で「豆を煮ているの」と話した著者は、「あら、いやだ。あなた、そんなことほかの人に言うのおよしなさい。あなたのイメージ・ダウンになってよ」と丁寧に忠告されてしまう。
余計なお世話、と言い返したくなるところを、著者は素朴に首をかしげる。<午前中から机に向かい、羽根ペン持って詩を書いていますと言えば、私のイメージは維持されるのだろうか。それとも、ユリの根を煮ています、と言ったりしたほうが、豆より数段、高尚なにおいが漂うのだろう>と、どこか不服そうな記述が愛らしくて、吹き出してしまう。
私にとって、新川和江さんは中学一年の春、教科書の詩で出会った詩人だった。私も詩を書きはじめて以来、「詩人のくせに普通」「作品とイメージが違う」「もっと詩人らしい格好をしよう」など散々なことを言われてきた。でも、教科書に載った新川さんもこんな<つぶやき>を持っていたなんて。くすりと笑う。勇気づけられる。
もう一人、豆を煮る詩人を私は思い起こした。三角みづ紀さんは、著書『とりとめなく庭が』にて、正に「豆を煮る」というエッセイを綴っている。
<わたしはこれからも折りに触れて豆を煮るだろう。ふっくらと皺のないつややかな時間をもとめて>。明日を見通すような、まっすぐな記述がまぶしい。
実は、新川さんの「豆を煮る」も、豆と時間を重ね合わせる描写が魅力的だ。
<固く豆を締めつけていた「時間」を、コトコトととろ火で煮ながら、ゆっくりほどいてやる楽しみは、こちらの気持によほどゆとりのある日でなければ、味わえない。私という人間をコチコチに締めつけていた「時間」も、豆を煮ることで、ゆっくりと一緒にほどけてゆくのである>
ものぐさな私は、豆を煮たことが無いし、これからも煮ることは無いだろう。何かを煮込む時間はもったいないと感じてしまう類の人間だ。それでも両著の記述は、一人の女性が抱え込む思いや、時間の厚みを想像させ、興味を掻き立てる。
精肉加工された肉とは異なり、豆は一粒一粒が個の完全体で、命の源だ。炊いた豆は、決して芽吹くことはないが、鍋のなかでふっくらとつやめき、春を待つだろう。
ここ数日、嗅覚や味覚がにわかに人々の関心を帯びた。生活には香り立つものが欠かせない。たとえば、朝は淹れたての珈琲(安いインスタントでも、コンビニの100円コーヒーでもいい)と決まっているように。
古い本は、匂いとともに、その本が経てきた時間をまとっている。古書特有のあの匂いで、嗅覚のすこやかさを確かめてみよう。開いたページに頬をすり寄せる。古びたインクと、湿った土のような、昔住んだ家の押し入れの中みたいな、どことなく甘い紙の匂いに安堵する。私の体温と本が溶けあう。「まだ大丈夫」とちいさく頷いて。
ちなみにネットで本を購入した場合に多いのだが、古書の匂いが強烈で、一人で部屋にいても他人といるような、落ち着かなさを覚えることがある。どうしても気になる場合、こんな方法がお勧めだ。
本を新聞紙(無料配布されるものを取っておくと良い)に包んで数日も置いておくと、匂いが新聞紙の方に移って気にならなくなる。幽体離脱みたいで、なかなか不思議な方法である。厚着させた新聞紙を剥きながら、要らない記憶もこんな風に、紙に染み込ませて捨てられたら楽だろうなと思う。
迷いながらも、閉店セールに駆け込んでよかった。図書館は当面閉館だしね。スマホ画面のつやめきや軽さよりも、紙のざらつきを今は求めている。日に焼けたページの感触を、指で探り当てる。
でも不安になる。こうして本のなかに、ノートのなかに、うつむいているだけでいいのだろうかと。みんなが果敢に闘っているなか、私は自分を守るための檻を言葉で編み上げているだけなのではないか。そう迷いを覚えてしまうのも確かだ。
鍋のなかを覗き込むように、私は本を開いて確かめる。炊き立ての豆の香りに、言葉の煮え立つ音に、心をほどかせながら。
「違う場所の同じ日の日記」
この日々においてひとりひとりが何を感じ、どんな行動を起こしたのかという個人史の記録。それはきっと、未来の誰かを助けることになります。
ほかの方の「違う場所の同じ日の日記」へ