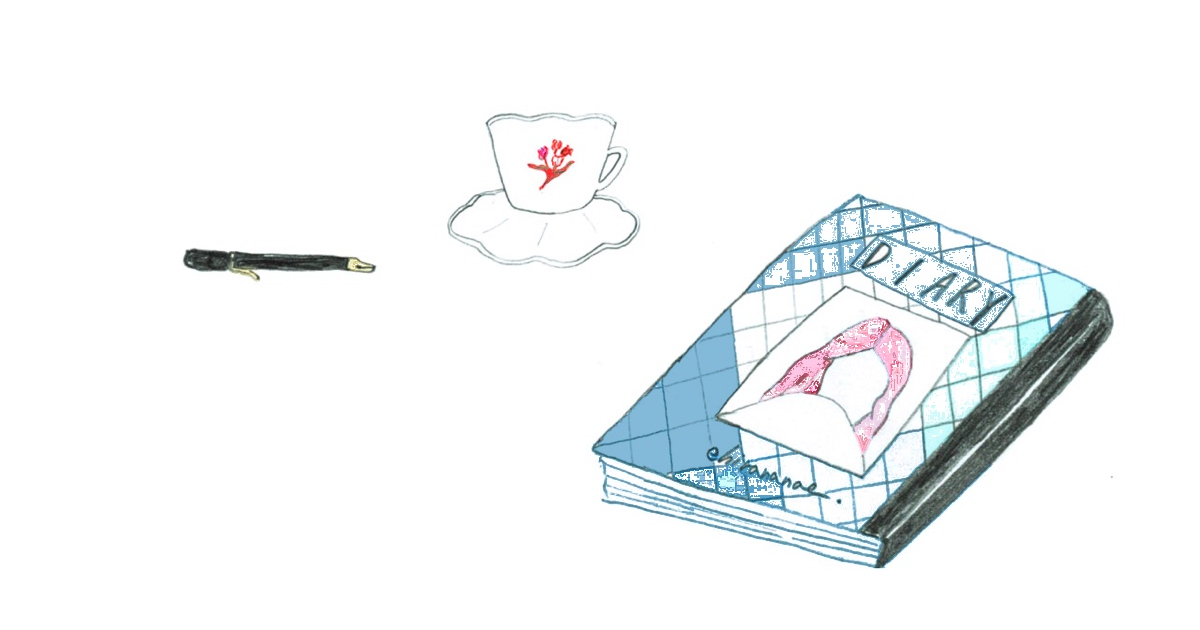まぶしかった。
駅前のツリーに灯った電球。
いつも12月が始まると、駅前のロータリーの大きな木には電球と大きな星が光る。
秋まではただそこに佇む大きな木を、みんながクリスマスツリーと呼ぶ。
もうすっかりと冬だった。
私の髪の毛からは染めたばかりの、ツンとする、背筋が伸びるような匂いがして、ずいぶん暗くなった毛先がたまに顔を覆って。こんなに暗くなった髪の毛を見るのはとても久しぶりな気がするなと思いながら。
あたらしく染まった髪の毛は、黒くて、少し赤くて、光にあたるとパープルにも見えた。
金曜日の夜、急に何か変化を求めたい気持ちになって真夜中に美容院を予約した。
土曜日は久しぶりに私たちのバンド活動とも呼べないけれど一応バンド練習の約束があったから、予約は日曜日の午後に。
土曜日はよく晴れていて、それぞれにギターを担いで集まって、スタジオの予約時間まで30分くらいしかない中でしっかりした定食を食べた。友達はアジフライ定食、私はさば味噌煮定食を。
スタジオの中で練習ともよべないくらいの練習をしながら、バンド活動の進歩のなさを反省した。
人生は楽しくありたいよねと、バンド宣言をしてからしばらくバンドは宙吊りだった。
しんとした小さなスタジオの一角で2人でギター抱えて音を鳴らして、ホワイトボードに歌詞を書いて、なぞる。
帰りがけのスターバックス。バンド活動の進歩を話すつもりがそれより近況を語って、やはりすぐに女子に戻ってしまう。それはそれでありのままに私たちであって。
バンドの話もそうだけど、ループする私の近況も、私も、はやく変わらないといけないと思った。
同じことを繰り返しては嘆く私に友達は「もう27歳になるんだからさ、はっきりさせなきゃいけないよ」と言う。
深く頷いて土曜日は過ぎた。
そして髪の毛は黒くて赤くて少しだけパープルになった。
デパートのエスカレーターの鏡に映る、髪の黒い自分が急に年相応に見えた。老けたなぁって。
手にしている、17歳の時におばちゃんから貰ったキツネのファーバッグもすっかり違和感なく収まっていて。
このバッグを貰った時はどんな格好をしても似合わなかったのに。
それが今は、しっくりと私のものみたいになっている。それもそうだ、もう26歳なんだから。
歳を重ねるって不思議だ。
冬になってこのファーバッグを持ち歩く時は少し、大人になったことを嬉しく思えたりもする。小さなことだけれど。
「私たちにはもうそんな時間なんてないんだよ?」
みんなが口を揃えて言うなかで私は、どう生きていこうか考える。
迫りくる時間があるとしたなら、なにをどうしたらいいのだろう。
分からずにまた時間は過ぎてしまって。
電車を降りて、駅を出て、見上げて。
大きな星が木の上に光っていて、私は毎年の光景を、また毎年のように、まぶしいなあと思った。
毎年のことなのに、去年はどんな気持ちでこの光を見ていたのか、覚えていない。
今よりも希望に見えていたのだろうか。今より暖かい光に見えていたのだろうか。
駅を離れてアーケードの電飾の明かりも遠くなって、もっと明るい光を見た。
今年最後の、満月だった。
アパートの階段からそれがよく見えて、しばらくそこで眺めて。丸くて街灯よりずっと明るかった。
髪の毛が暗くなったからってなにかが急に変わるはずもないのに。
無難におさまる容姿すらも、年齢を認めてしまったみたいで怖かった。
認めることも、受け入れることも、少しでも前を向いていけたならいいのに。もっと明るいほうへ。
毎日のことを「退屈」と呼んでしまいたくはない。
せめて、退屈になったら日曜くらい。
変化する予感をみつけられたなら、なにかは、変わるだろうか?
誰かに会わなくても、どこかへ行かなくても、変われる予感はきっとあるはずで。
次の土曜日あたりに私はまた、過ぎた日をまとめてそれを退屈と呼んでしまうかもしれないけれど、それでもやって来る日曜日には何かを探してみようと思った。
満月があまりにも綺麗だったから、私は寝る前に吉本ばななの『キッチン』のことを思い出して、ベッドサイドのからそれを取り出して読んだ。キッチンにでてくる月は見たことがないけれど、きっとこんな風に明るいのだろうと思った。
今年最後の満月の明かりが大きかったことを、来年の私は覚えているだろうか。
翌朝のアラームは7:40。
『キッチン』を一通りなぞり終えたあとに、部屋の明かりを消した。カーテンの向こうが少しだけ光って見えた。