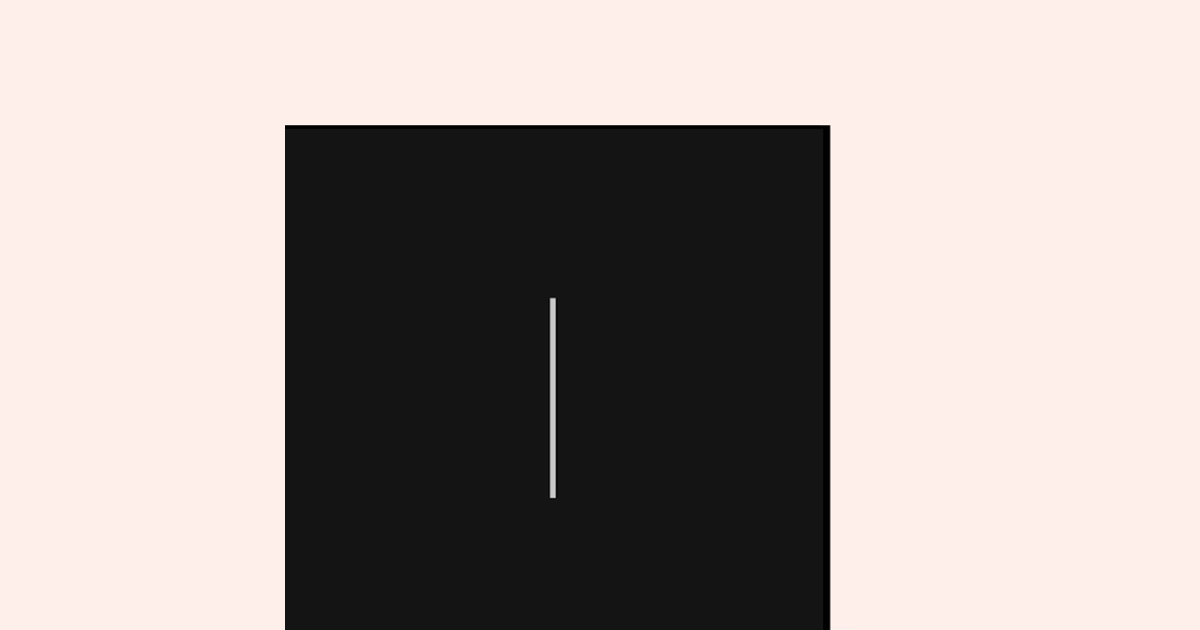11月も10日を過ぎた頃、私はいつものように母の運転する車へ乗り込んだ。
目的地は山奥に建つ私立高等学校。私の通う学校だ。
自宅から車で約30分ほど、その道すがら母と私は言葉を交わすのだ。
それはちょっとした近況報告だったり、たわいもない家庭の話だったりする。
その日の母は気が立っていたのか、普段よりやや荒々しくハンドルを切った。
変わらぬいつもの会話。
けれど空気だけはピリピリと張り詰めていて私は少しばかり怯えと怒りを覚えた。
思い返すと私に不登校の兆候が見え始めたのは小学生の頃からで、中学生にもなると母の運転する車で半強制的に学校へ送迎されることは、私にとって「日常」と言えるまでにごく当たり前のものとなっていた。
私がこんな風だからお母さんは苛ついているのか
なにを今更。でも私が悪い
どうしてこんなことになった
なにも考えたくない
無意味な言葉ばかりが頭の中を占め、脳を内側から圧迫する。
いつの間にか母との会話は止まっていた。
そうしているうちに車は目的地へとたどり着く。
校門の前の駐車スペースに車体がゆっくりと滑り込み、そして止まった。
静寂が五秒ほど。
思わず私がうつむくと母が隣で身じろいだように思えた。
不思議に思い、恐る恐る様子をうかがうと母は静かに速度計の方向を見つめていた。
「私の」
母の唇が不意に動き、音を立てる。
「私の育て方が悪かったのかな」
あ。
速度計を見つめていた母の目がゆっくりと動き出す。
目が合ってしまう。
私はとっさに膝の上で握られた自分の両手に視線を向けた。
「……あんたがどう思ってるか知らないけど親だからって子供のことを四六時中好きなわけじゃない。嫌いになるときもある」
沈黙が車内に蔓延していた。
母にこんなことを言わせてしまった。母にこんなことを言われてしまった。
なにか言わなければ、そう思うのに言葉が出てこない。
自分の奥の方から湧き上がるありとあらゆる感情が混ざり合ったような、それでいてなにも無いがらんとした気持ちを持て余すことしかできなかった。
なんの努力もせず自分の嫌なことから目をそらし続けているような私が母に対してなにか言えるはずもない。
私は車のドアを開け、黒いタイツとローファーに包まれた両足を地面の上にそっと置いた。
学校へ行こうという意欲からではない。
ただここから逃げ出したいという逃避からくる行動だった。
足先からはひんやりとした空気がのぼってきて身体中の熱を奪ってゆく。
「いってきます……」
返事はなかった。
ドアを閉めて二歩下がる。
それを合図に車はゆっくりと動き出し私へ背を向ける。
私は白いナンバープレートに書かれた文字と数字を頭の中で繰り返した。
母が乗った車がどんどん遠ざかり、やがて文字も数字も見えなくなった。
お母さん
お母さんは、私の
お母さんは、私のこと
お母さんは、お母さんは、お母さんは
どうして私を産んだの
生まれてこなければよかった。生まれたくなんかなかった。
なにもかもがわけが分からなくなって、目から涙が次々こぼれた。
お母さんは悪くない悪いのは全部私、それは間違いなくて。
間違いではないのに、お母さんはなにも悪くないのに、
それでも私は母を憎しむ心を捨てられずにいる。
お母さん大好き
何度か言おうとしたその言葉は音になる前に口の中で溶けて消えた。