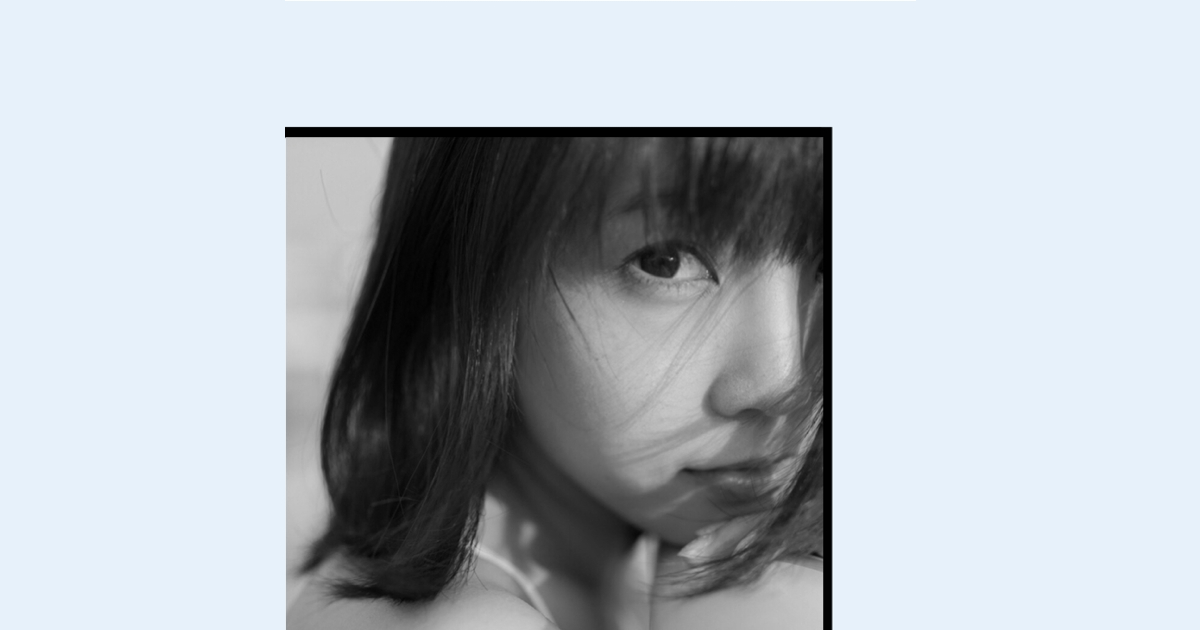自分を構成している要素を分解してみると、社会のちいさな縮図のように見えてくる。
わずかでも誇れる部分はあって、それらは周りにも重宝され自分自身にも愛されているため、満ち足りたピカピカとした光を放っているけれど、誰にも愛されてこなかった部分たちは、居場所をなくし息を潜めている。ピカピカする暇もなく、なるべく目立たないように、と努める。
毎朝、鏡の前で神妙な顔をしてメイクブラシを持っては、縦幅の小さい目をなるべく上下に大きく、丸い頰や低い鼻には影を塗り足して目立たなくしていく。これは欲望なのだと思う。誰にも「ここがへんだね。」とあえて言われたくないという欲望。そう気付きかけながら、無心を掘り返し、尚も丁寧に描き変えていく。

もっと根深いコンプレックスは生き方のほうにあった。AV女優としてデビューする前、わたしにはセックスの経験がなかった。結果として珍しがられて役には立ったのだけれど、デビューを志願してプロダクションを訪ねたときは平然を装って、未経験という事実を頑なに隠そうとしていた。
自らの意志で守っていたものだったけれど、いつからかそれが普通じゃないと教えてくれる無邪気な声たちに向き合ううちに、ただの、恥ずかしくてたまらない、隠したい部分へと変わってしまっていたのだった。
それでも、誰がなんと言ってからかってもわたしの歪みはわたしのもので、わたしにはコンプレックスを背負って生きていくという責任があるように感じていた。人から見ればいびつに見える凹凸も、もしかしたらぴったり嵌まるときがくるかもしれない。パズルのピースには、ひとつとして同じ形はない。あってはいけないのだ。生きるのに邪魔なでこぼこも、本当に耐えられなくなるときまでは、削り取らないで頑張ってみよう。そう決めていた。負けず嫌いだった。

よいこが真似するといけないから、という理由であまり公の場で卑屈なことを言わないようにしているわたしだけれど、ごくたまに、つい「自分のここが嫌い。」と口にしてしまうときがある。そういうとき、やさしい人らは「そんなことないよ。」辛辣な人らは「じゃあ直せば?」とそれぞれ無邪気に伝えてくれる。やさしさは気休めにはなるけれど、自分の痛みを知らない人のやさしさよりも、痛みを知っている自分の不満の肉声の方が大きな音で反響する。そして厄介なのが、「直せば。」と言われた場合でも、そんな簡単に言わないでほしい、と思ってしまうところなのだった。
嫌いは、好きの裏返し。とはよく言うけれど、その言葉の持つもっとマイナーな真実は、「嫌い=好き」ということだ。わたし、生まれてから何度も何度もこの「自分の持つ恥ずかしい部分」について考えた。丸いほっぺたを困った顔で眺めていた。どうしてみんなと同じようにできないのだろう、と口にはしながら、それでも変えてしまうことを踏み切れない自分を、どこか親のような目線で、見守っていたのだと思う。わたし、わたしの凹凸が好きだった。
全てをあっけらかんと変えたのは、応援してくれている人からの、うつくしい手紙だった。
ずっとわたしの活動を追いかけてくれていたらしいその人は、デビューする前のわたしと同じく性交渉経験がなく、その理由は「本当に愛する人と結ばれるときにそうなるべきだ」という、ごくシンプルなものだった。それは、かつてのわたしと同じだった。
なにも、こんな理想論を、それだけを正しいことだなんて到底思わない。なにも正しくなく、なにも、別に間違いじゃない。顔だって、身体だって、生き方だって、本当に何一つこれが正しいなんてものはない。平均値を測るのは、それによって糾弾されることのない誰かが、単に安心したいからに過ぎない。
だけれど、わたしはそのとき確かに光を見たような気がした。自分の過ごしてきた、後ろめたさと居心地の悪さに塗り固められた日々が、いま火を灯した線香花火のように、ぱちぱちと輝いて見えた。この手紙の差出人の、孤独を、知ってしまえるためにあったのだとしてもいいような気がした。幾つものさみしい夜が。
完璧な人間はいないけれど、完璧な幸福というものはある。持ち得たこと、起こることの全てに意味があるとは思わないけれど、気まぐれなご褒美のように全てが星のように光りだし、星座のように結んでいける瞬く神様の時間がある。
それらは、自分の顔や身体や生き方が、平均値と近いかどうか、いびつなところがないのかどうか、ということとは、本当にまったく関係がない。誰が、どんな形をして生きていても、降り注いでくるかもしれない幸福なのだ。

あたらしい定義がわたしの内部の縮小された社会を、そのあり方を変えていく。
コンプレックスというのは、それそのもの、見つめるあなた自身の眼差しそのもので、「愛されることを待っている」場所。其処こそを愛してくれたらいいんだよ。と、ピカピカと点滅して教えてくれているような、いとしい目印なのだと思う。
あなたが嫌いなあなたの部分を、誰かが親しく思うとき、誰かが愛してくれるとき、Dear,コンプレックス。きみが居てよかった。きみが纏わりついて歩きにくかった道の途中で、途方にくれるわたしでよかったね。と、思う。
そうしてきみは、消えていく。誰かに愛してもらったくらいで、消えてしまう程度のしつこさだった。なんだかちょっと寂しいんだ。
とはいえ他の部分にだって無限に「ここが嫌い。」は湧き続ける。わたしだって気にしているのに誰かにつつかれたりなんかして、うんざりとまた項垂れながら。
それでもこんなのも全部、いつか消えちゃうようなものなのか。そう思うと、おかしいことに儚いなにかを観測しているような気になって、笑ってしまった。
シャボン玉ぐらいのイメージで。今日も、愛される日を待っている。