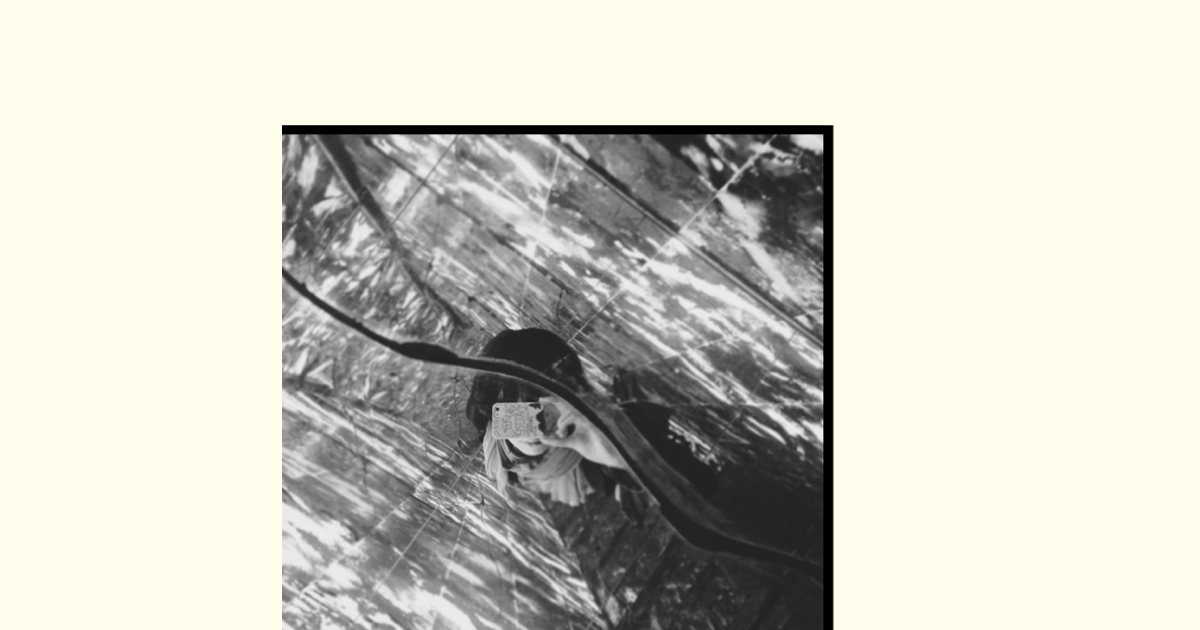自分にとってのスウェーデン語を思うとき、最初に浮かぶ風景がある。
大学生活最後の、スウェーデン語の試験の帰り道。ロンドンは夕暮れだった。ピーター・パンが飛んでいきそうなかたちの煙突の上を、色づいた雲がゆっくりと流れていく。寮へとつづく坂道はきのうまでとは違う表情に見えて、きゅうに一人になったような心ぼそさだった。これで、本当に、大学で学ぶスウェーデン語は終わりなのか。自分のスウェーデン語を信じることができなかったわたしがそのとき感じていたのは、達成感ではなくて、絶望に近い不安だった。
わたしは、ロンドンの大学で、スウェーデン語の勉強をはじめた。Scandinavian Studiesというコースで、学生は北欧地域にまつわる諸々とともに、言語を学ぶ。憧れつづけた北の国々へ初めて出かけていって、書店に並んでいる本をまったく読めないという当たり前の事実に打ちのめされ、“北ヨーロッパの言語を全部読めるようになる!”と無謀な目標を掲げてから4年。わたしにとってロンドンのその大学は、忙しい日々に埋もれてしまっていた目標へと続く早道で、“海外のよい大学で現地の学生と対等に学ぶ”という漠然とした夢も叶えられる、理想的な場所だった。
けれど、実際に入学してみるとまわりの学生はみなイギリス人かヨーロッパからの留学生で、スウェーデン語の飲み込みがおそろしく早く、わたしはあっという間に追いつけなくなってしまった。英語すら覚束ない者にとって、ロンドンの大学で他の授業を受けながら第二外国語をまっさらな状態から学ぶというのは、着の身着のまま登山にでかけるようなものだ。入学前きっと楽しめると思っていたスウェーデン語は、わたしの前にそびえ立って、永遠に攻略することができない要塞のようだった。
須賀敦子がフランスに居た頃のエッセイで、行き詰まっていた日々を「岩に爪を立てて登ろうとするのだが、爪が傷つくだけで、私はいつもおなじところにいた」と表現しているけれど、まさにそういう感覚で、どれだけあせって勉強しても、登れている気も進んでいる気もしなかった。英語がある程度ストレスなく使えるようになり、スウェーデン語がすこしずつ上達してきても、フィンランド語の授業も受けるようになっても、そんな感覚はずっと続いた。大学を卒業するまで、ずっと。
そんなわたしを変えてくれた一冊の本がある。ジュンパ・ラヒリ『べつの言葉で』。大学を卒業してスウェーデンで暮らしていた冬、友だちが、読んでいたらわたしを思い出したと言って薦めてくれた。ベンガル語と英語の話者であるラヒリが、自身で選んで勉強している新しい言語、イタリア語で書いた、言葉についてのエッセイ。
この本は、全部がわたしにとって特別だった。情けない、できれば隠したいものだと思っていた自分にも覚えのある苦しさが、そこでは美しい言葉になって光を放っていたからだ。
それでも、わたしのこのイタリア語の計画は、言語と言語の間に膨大な距離があることをはっきりとわからせてくれる。一つの外国語は完全な分離を意味することがある。いまでも、わたしたちの無知の残酷さを象徴することがある。新しい言語で書き、その核心に入り込むためには、どんなテクノロジーも助けにならない。プロセスを加速することも、省略することもできない。動きはゆっくりでぎこちなく、近道はない。隔たりはそのままだ。言語がわかればわかるほど混乱は増す。近づけば近づくほど遠ざかってしまう。いまもわたしとイタリア語の間の隔たりは乗り越えられないままだ。ほんのわずか進むために人生のほとんど半分を費やした。ここまでやってくるためだけに。
ジュンパ・ラヒリ『べつの言葉で』(新潮クレスト・ブックス:p61〜62)
この本に出会ってから、わたしは、自分の使う言葉を認められるようになったと思う。ラヒリがおそらくネイティヴのようではないであろうイタリア語で書いた文章を前に、どの言語であっても自分が発する言葉は自分のものだと目がひらく思いだった。もちろんなるべく完璧に読んで、自然な言葉を話したいけれど、たとえばすこし間違いがあってもその言語を使って読めるものの幅はそんなには狭まらないし、表現したかったことは消えてなくなったりしない。それに、不自由な言語だからこそ表現できることだって、確かにある。
そして、彼女と同じように(と、言うのはおこがましいけれど)わたしは苦しみながらも外国語が好きなのだ、とも思った。膨大な時間をかけているのは、もちろん習得した言語で読みたいものが多くあるからだけれど、それと同時に言語そのものを、言葉を、愛しているからだということ。
それぞれの言語には、それぞれの美しさがある。たとえば音ひとつとっても、スウェーデン語には歌うような、流れるような響きがあり、フィンランド語は口の端から音がぱらぱらぽろぽろとこぼれるようだ。本を読むとき、わたしはときどき文章を口にだしてみる。そうすると、その言語ならではの旋律や余韻に、全身の血液がめぐるような生き生きとした気持ちになったりする。とても単純なことだけれど、音、というのは言語を愛する理由のひとつになると思う。
それに、言い回しも、言語によってぜんぜん違う。ある言語で頻繁に使う表現がほかの言語にも存在するとは限らない。またある言語では自然なものの言いかたでも、ほかの言語に直訳すると違和感を覚えたりする。そんなときは、なんだか文化の端っこをつかまえたみたいで、嬉しくなる。言葉はどれも、人びとのあいだで育ってきたものなのだという当たり前のことに、たしかに触れられたような気がする。
言語をひとつ習得するということは、その言語に付随する世界を得るということだ。ずっと、そう思ってやってきた。どうして外国語を勉強するのかとよく訊かれるけれど、やっぱりこれ以上の答えはない。ボートをこしらえれば、無限に読むものがある世界を漕いでいける。数えきれないほどの小説はもちろん、たとえば百年前の人が書いた日記も、いまを生きる人が書いているブログも、読むことができる。つまり、国境も、時代も、がんばり次第で超えていけたりするということ。それはいまも昔も、わたしにとって言葉を学ぶ原動力で、変わることがない。
けれど、それだけだっただろうか、本当にわたしは道具を作っていただけなんだろうか、と、ラヒリはわたしを立ち止まらせ、考えさせてくれた。そうして、劣等感と歯がゆさに圧されていた日々のなかでも、自分はつよがりでなくほんとうに楽しんでいたのだな、と気がついた。言葉の手触りを、その違いを。すこしずつ言語の感覚が染みて、すこしずつ頭のなかで繋がっていく、実験のような過程そのものを。わたしはわたしが思うより、言語を、言語を学ぶことを愛しているし、愛してきたのだと、ようやく知った。
日本に帰国して一年半が経ついまも、わたしは仕事でも私生活でも、いくつもの言語を使っている。日本語、英語、スウェーデン語、フィンランド語。いまもっと勉強したいと思っているのはドイツ語だ。あいかわらず頭のなかを整頓することはできず、ひとつ段階を上がったかと思えばまた新しい問題が起きて、を繰り返しているけれど、時間とともに、それぞれの言語との心地よい距離感を見つけられるようになった。さまざまな文章を読む日常を、それなりの自由を手に謳歌している。ひとつの言語がなにかの理由でつらいとき、ほかの言語が匿ってくれるように感じることもある。攻め落とせないとあんなに嘆いていたスウェーデン語も、気心の知れた友だちのように思うようになった。
長い旅に終点はなく、わたしはこれからも言語を学びつづける。自分の足りなさといつでも向き合いながら、それでもいつかよりはずっと身軽にやっていけると思う。外国語が大好きだと、いまはやっと、まっすぐな気持ちを持って言えるのだ。

上から、スウェーデン語、ドイツ語、英語、フィンランド語。どれも自分にとって大切な本だ