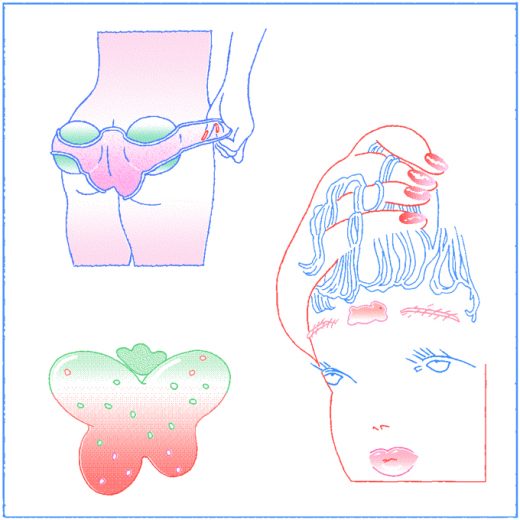男になりたいわけじゃない。
女をやめたいわけでもない。
ただ……。
ただ、なんだろう? ここを発つ。どこに行けるか、わからないまま。

「ダイエットしてるんだ」
と、その女の人は言った。
「知ってる? 男は君みたいなちょいぽちゃの女の子が好きなんだよ?」
と、その男の人は言った。
「なんでてめえのためにダイエットしてると思ってんだよ」
と、わたしは言ってしまった。男言葉だった。
女の人は笑ってくれた。
「だって男はさあ!」と、男の人はまだ言い募った。
ずるい、と思った。
ずるいよ。その「俺たち男はさあ」チームから、たったひとりにものを言うなんて。
かくなる上は、団体戦を個人戦に持ち込むしかないだろう。
「俺たち、って言ってるけど、それ、あなた個人の意見ですよね」
その声がどうしても、男ぶってしまう。
わかっている。
これは、彼女を守るための優しさじゃない。
ただ、欲しいだけなのだ。「俺たち男はさあ」チームから排除されないための、“男”のポジションが。
ドラァグキング、というものをご存知だろうか。

ドラァグキングチームAll the kings men / Dedda71, Wikimedia Commons
簡単に言えば、「男装して男のパロディをやる」パフォーマンスだ。
日本で最も心意気が近いのは、「おじさんLINE」だと思う。「おっは〜❗️ななちゃん😆✋よく眠れたカナ🛌?昨夜から返事ないよ??朝寝坊🌀だね(^◇^;)ちゃんとパンティーはいて寝るんだぞ〜😜ナンテネ😈⚠️」みたいなおじさんを女性が誇張して演じ、笑い飛ばす。
ドラァグクィーンの方が断然有名だろう。
ド派手な女装、あふれる自信。好き放題な格好で言いたい放題する姿は、痛快、自由。
女装して女のパロディを演じる「ドラァグクィーン」の方が、ドラァグキングより知られていると思う。Netflix『ル・ポールのドラァグ・レース』は10年間11シーズン続く人気番組だし、舞台では三浦春馬演じる『キンキーブーツ』ローラ役も話題になった。
ドラァグクィーンは、抵抗者であった。若い女だからとナメたLINEをよこす奴を笑い飛ばす「おじさんLINE」のように、ドラァグクィーンたちもまた、「男らしく女を愛せ」の抑圧に抗ってきたのだ。
「“女になりたさ”以下、“男らしくなりたくなさ”以上」。
(Roger Baker著『Drag: A History of Female Impersonation in the Performing Arts』1996, NYU Press/牧村朝子訳, p.237)
そのような精神から生まれたはずのドラァグクィーン文化が、しかし、なぜだろう。マスメディアの大舞台に引きずり出された途端、「女にはっきりブスと言える毒舌オネエ」演出をされてしまった例を見た。
「ブス」という言葉は、ドラァグクィーン文化を生んだゲイ・コミュニティにおいては、ある種の親密さの表現として使われることもある。だが、それをゲイクラブでやることと、外に向けることとは違う。
ゲイクラブを出て、マスメディアに登用され、男の座を脅かさない、けれど女よりはちょっと上からものを言えるくらいの安全な位置から、「ブス」で笑いを取る。笑えない、と思った。
キングになりてえ、と思った。
ドラァグクィーンをゲイクラブから引きずり出してきてカメラの前で「ブス」って言わせるようなその人と、ちゃんと、話す自信が欲しいと思った。
なのにその彼に……おそらく、マスメディアの管理職の男女比から推定すると多くは男性なんだと思うけど……「俺たち男はさあ」チームから出てきていただくにあたり、「男言葉で挑発しないと聞いてももらえない」と思ってしまう自分がいる。
女の声では弱すぎる、と。
そう思っているのは、自分自身だ。
鏡の前に座った。

「男装メイクを教えてください」と、プロのメイクさんに頼んだ。
女に銃が許されなかったころ男装で銃をとった、新島八重のように。
女にジャズが許されなかったころ男装でピアノを弾いた、ビリー・ティプトンのように。
わたしは、許されたかった。「うっせえブス」「黙れヒスBBA」で片付けられずに、話したかった。ちゃんと話したかった。人間扱いされたかった。
ただ人と人として、出会い直したかった。
「俺たち男はさあ」チームの、その人と。
男性である前に、ひとりの人間であるはずの、その人と。

「今日は今までのメイクの常識を全部ぶち壊すつもりでいてください」
と、メイクさんはおっしゃった。「乙女塾」メイク講師、NAOさん。男性として生まれた人を含め、それぞれに「今よりも女の子らしくなりたい」と願う人にメイクを教えている。
その真逆をやるのが、男装メイク、というわけだ。
・肌を粗く見せる。
・額や眉間やほうれい線にシワを描く。
・青シャドウでヒゲの剃りあとを描き、つけひげをつける。
今までの人生で隠してきたシワ、アラ、ヒゲを(そう、女にだってヒゲが生える人はいる)、どんどん濃くした。
「それが顔の“味”になるんです」
歳を重ねることは「劣化」だと思い込まされてしまった女であるわたしにとって、シワやヒゲを描くことには、それを「味」と言われることには、なんとも言えないセラピー効果があった。


YouTuberのマネをして、つけあごヒゲをあごに貼る。

メイクブラシでヒゲを整え、立派なヒゲづらになった。
ヒゲ剃りの苦労は、つけヒゲじゃわからないけど。
ヒゲづらでコンビニに寄った。ヒゲ隠し用にと用意していたマスクは使わなかった。
お次のお客様、と呼ばれてわたしは、男性(に見える)店員さんに、ピンク色のいちご大福を差し出した。
「108円です」
「Suicaでお願いします」
声を出した。女の声だった。店員さんがちょっと驚いたのがわかった。
いたずらが成功した子どもみたいな気持ちになった。
いちご大福を食べて、手の甲に誇らしく「女」と書いた。「女」という字が、剣士の太刀筋みたいに鋭く見えた。
もう、弱くない気になれた。

男になりたいわけじゃない。
女をやめたいわけでもない。
ただ……。
ただ、人間になりたいのだ。
本当は作り笑いしたくなくて、怒りたくも泣きたくもなくて、ただあの人とちゃんと話したいだけで。強さなのか、元気なのか、何か、何かが欲しくて、欲しくて、欲しくて、
ヒゲづらでたべている。
ピンクのいちご大福を。