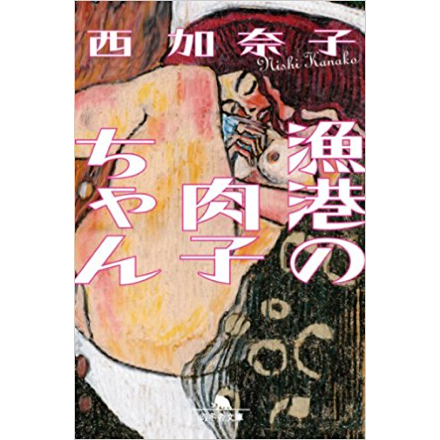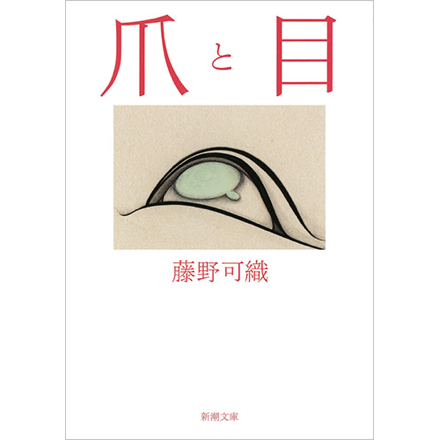母親という道を選択する覚悟を問う。ホラーに近いほど胸をえぐられる『爪と目』
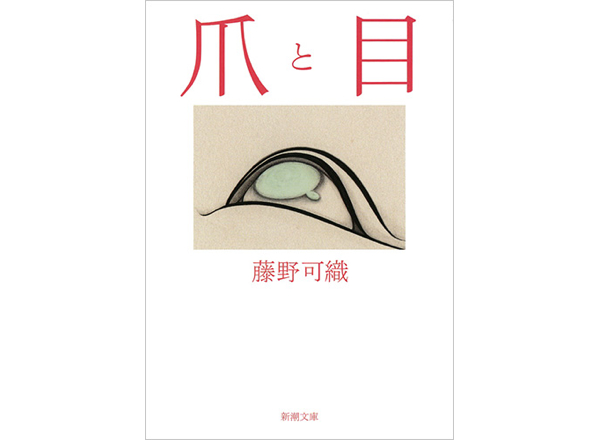
『爪と目』(藤野可織)(Amazonで見る)
紗倉さんが紹介する2冊目は藤野可織さんの『爪と目』(2015年)です。『芥川賞』を受賞している本作は、3歳児の「わたし」が、父、死んだ母、父の再婚相手をとりまく関係を語るという作品。「父のもとにやってきたのは、子どもに愛着のない冷めた感性を持った愛人。虐待的な日々に小さな子どもは精神崩壊してしまうのですが、その壊れていくさまがあまりにも怖くて……」と紗倉さんは話します。
母親になることは、自分ではないけれど他人ほど遠くない、子どもという不思議な存在を持つことです。「子どもは大切にしなきゃいけない」という社会の暗黙のルールがある中で、「そういった精神的に制約がある道を選ぶ覚悟が私にはあるのか、そんな問いを向けられる」と紗倉さん。「女性は出産なり、仕事なり、生きていくなかでさまざまな選択を迫られます。母親という道を選択する覚悟が、私にはあるのだろうか。自覚を持って、生き続けられるのだろうか。そんなことを考えさせられます」。ホラーに近いほど胸がえぐられる苦しい作品だと紗倉さんは話してくれました。
母親の支配について考えさせられる、大島智子さんがイラストを描くきっかけとなった『青鬼の褌を洗う女』
大島さんが2冊目にあげたのは坂口安吾さんの『白痴・青鬼の褌を洗う女』(1989年、Amazonで見る)です。この本に収録されている『青鬼の褌を洗う女』は、戦時中でも男に媚びながら退屈を愛す女性の寂しさや孤独が描かれています。大島さんがイラストを描くきっかけになった作品なのだそう。
母親に溺愛されている主人公は、戦中の空襲で母親が亡くなったときに溺愛からの自由を喜びますが、自分の中に拭い去れない母親という存在を感じます。「焼け野原を目の前に、主人公は『私の人生はここから始まるんだ』と感じます。でも、ふとした仕草や声が母親に似てきて、自分の中に母親が生き続けている嫌な感覚がだんだんと芽生えてくるんです」。
小さなころは気づかなかったけれど、大人になると次第に母親に似てくることもあります。「嫌なところを受け継いでいることに気づくと、母親の支配について考えさせられるんです」と大島さん。親からふと感じる窮屈さのようなものは、愛だと感じることもあれば、逃げたいと思うこともある。そんな気持ちをぶつけられる一冊です。
母親が愛してくれない、絶望と痛みの瞬間が描かれている『乳と卵』
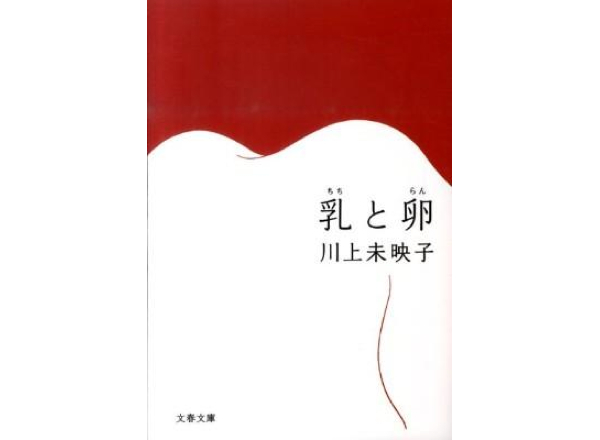
『乳と卵』(川上未映子)(Amazonで見る)
「大好きな作家さんなんです」と興奮気味に紹介くださった紗倉さんの3冊目は川上未映子さんの『乳と卵』(2010年)。She isのインタビューでも、女性たちに生きるエールを贈ってくださった川上未映子さん。紗倉さんも、そんな川上さんの勇敢さに励まされているひとりです。
「中でも『乳と卵』は特別な作品」と紗倉さんは話します。「反抗期が長くて……ずっと母親と衝突していたんですよね。とても愛情を注いでくれたのですが、溺愛されすぎて受け入れられなかったり、逆に私から離れて女性として生きようとする姿が許せなかったり。母親がなにをしても許せない、そんな頃の自分を思い出される作品です」。
「血のつながり」という特別な関係だからこそ、どうしようもなく受け入れられないこともありますが、それでも離れられない母と娘という関係。「母親が愛してくれないと、絶望を感じていたんですよね。そういう痛みの瞬間がこの本では描かれていると思います」。
母親であり、ひとりの女性である。写真家のせきららな日記『かなわない』

『かなわない』(植本一子)(Amazonで見る)
大島さんが紹介する3冊目は写真家・植本一子さんのエッセイ『かなわない』です。2011年から綴られた日記には、音楽家である旦那、ECDさんとの日々や子育て、不倫関係にある恋人とのことなど、植本さんの私生活がせきららに綴られています。
「生活全部がなんの取り繕いもなくそのまま書かれていて、人生っていい部分だけじゃないよね、と思える作品です。淡々と日々が過ぎていきながらも、私たちの手元にはなにかが増えていて、母親になるとそれが如実に増えていくのだと、この本を読んで思いました」。母になること、そして一人の女性であるということ。その間で揺れる女性の生活そのものを感じることができる作品です。
なにかを失ったとしても、なにかを得ようとする。そういう女性になりたい
最後に紗倉さんが口を開きました。「いろんな生き方があると思いますし、ひとりひとりがいろんな悩みを抱えていると思います。なにかを失ったとしても、なにかを得ようとする、そういう前向きな力を持っている女性はカッコいいと思いますし、そういう女性になりたいです。『最低。』も、そういった前向きな力を感じ取れる作品であるといいな」。

母と娘、という抗えない血のつながりを持った、特別な関係。それぞれが母に対して抱えている思いをぶつけ、自分自身の母親像を考えるきっかけをくれる6冊が贈られた、トークイベントでした。
- 2
- 2