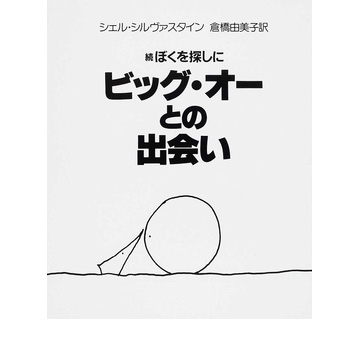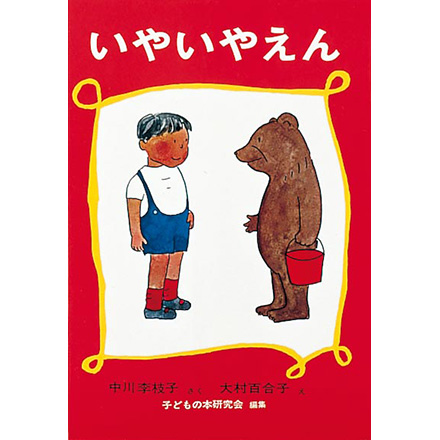コンプレックスをテーマに、少年アヤさんが児童文学を選ぶ
「コンプレックス」というのは、多くの人が口にしたことのある言葉だと思いますが、その内容も向き合い方は人それぞれ。そんなコンプレックスについて考えるべく、She isでは1月特集を「Dear コンプレックス」と銘打って、「コンプレックス」との関係についてさまざまな方にお話をうかがってきました。その連動企画として、毎月の特集テーマから連想される本をゲストに選んでいただく恒例のイベント「She is BOOK TALK」を、駒沢公園近くの本屋SNOW SHOVELINGにて開催。

SNOW SHOVELING
ゲストは、自分自身のジェンダーやコンプレックスを真摯に見つめ、世の中の「こうあるべき」に問いを投げかけてきたエッセイストの少年アヤさん。「コンプレックス」というこちらからのお題に対して、「すべて児童文学を選びました」というアヤさんの意図とは? イベントが終わった瞬間、アヤさんの言葉に拍手がおくられた、やさしい一夜をお届けします。

少年アヤさん
いびつで不器用な生き物たちが、ただ自分らしくいられる物語。『ムーミン谷の夏まつり』

『ムーミン谷の夏まつり』(著:トーベ・ヤンソン、訳:下村隆一)(Amazonで見る)
昨年から児童文学を読み返しているというアヤさんが紹介してくれた1冊目は、トーベ・ヤンソンの『ムーミン谷の夏まつり』(1954年)。
本作はムーミン谷が大洪水に襲われ、なにもかもが水没してしまうところからはじまります。もちろんムーミン屋敷も水没し、ムーミン一家やミイ、避難してきた数名のキャラクターたちは窮地に立たされます。するとそこへ、見たこともない巨大な建物(劇場)が流れてきて、渡りに船と住み着くことになるのですが……。
「ムーミンシリーズはどれも示唆に富んでいて、どういう物語かということを一言で表すことがむずかしいのですが、本作でぼくが最も惹かれたのは、ミーサという女の子をめぐるドラマです。
彼女はいつも眉間にシワをよせていて、人と関わるのが苦手。それどころか、夜になるとわけもなく泣きたくなったり、はたまた癇癪を起こしてしまったり、自分自身を持て余しているんです。
ところが物語の終盤、そんな彼女に転機が訪れます。ひょんなことからみんなで劇を作る流れになるのですが、お芝居を通してはじめて、自分のなかにあるモヤモヤを解き放つんです」

初めて舞台に立ち、恍惚とした表情を浮かべるミーサ。そのシーンの描かれたページをみんなで回し読みしながら、アヤさんは彼女に思いをめぐらせます。
「鬱屈とした感情やコンプレックスを表現に置き変えるのは、ぼくも文章を通じてずっとしてきたことなので、恍惚としている彼女がいまどういう興奮のなかにいるか、ちょっと想像がつくんです。
表現として吐き出すって、たとえば原稿用紙だったり、虚構の世界だったり、はたまた音楽だったりに、息が詰まりそうな自分を逃がしてやることでもあるんですよね。純粋にガス抜きにもなるけれど、たとえば誰かが笑ってくれたり、気に入ってもらえたりしたときには、ほんのすこし自分を愛することができる。そして前に進める。
ちなみに最後、ムーミンやミイたちは谷に戻るんですが、ミーサはお芝居を続けるために劇場に残るんです。
ムーミン谷には異形だったり、偏屈だったり、個性しか持ち物のないようなキャラクターがおおぜい暮らしています。トーベ・ヤンソンがすごいのは、そういった人物たちをいきいきと描けるということもですが、なにより彼らひとりひとりに、まんべんなく視線と尊敬を注いでいるところだと思っているんです。ストーリーから脇道にそれても、たとえばミーサみたいなサブキャラクターにも、ハッピーエンドを贈ってみせちゃう。だれひとりないがしろにされていないんです」
ちょっとしたことが、壁を乗り越える勇気になる。『真夜中のパーティー』

『真夜中のパーティー』(著:フィリパ・ピアス、訳:猪熊薫子)(Amazonで見る)
「乗り越える、ということの爽快さを、存分に味あわせてくれます」とアヤさんが紹介する2冊目は、フィリパ・ピアスの『真夜中のパーティー』(2000年)という短編集。全8編のうち、アヤさんが紹介するのは「アヒルもぐり」。
水泳の授業中、先生が池に投げ入れた箱を、水底から取ってくるというテストを与えられた子どもたち。太っていて、いつもからかわれてばかりの主人公は、びくびくしながら池に飛び込みます。
「時間にしたらたった数秒の出来事だと思うのですが、彼にとっては永遠のような時間なんです。つめたい池の底にブクブクと潜っていきながら、今日も失敗するんじゃないか、笑われるんじゃないかと不安になり、やっと箱をつかんでも、こんどは息がつづくかどうか不安になり。
だけど、その日はきちんとやり遂げることができて、クラスメイトたちから喝采を浴びるんです。
物語のラストはこんなモノローグでしめくくられています。
『ぼくは生きてるかぎり、あの箱をもってるつもりだ。
ぼくはゆうゆう百歳ぐらいまで生きるかもしれない。』
ビクビクおびえて、いつも自信のなかった少年が、もしかしたら100歳まで生きちゃうかも、なんて思えるような興奮とか、未来がきらめいて見えるような感覚って、どんなものか想像もつかないですよね。というか、簡単につくなんて言ったら、うそになっちゃうくらいのものです。
もしかすると、日々のなかでたやすく薄れてしまう感覚かもしれないけれど、でもけっして、消えてしまったりはしないだろうと思うんです。それは、物語として垣間見たぼくたち読者にとっても、おそらく同様です」
- NEXT PAGEほんとうの意味で「他者と共に生きる」ことができるようになるということ。
- 1
- 3