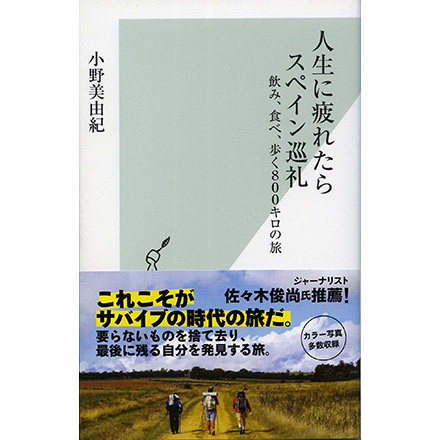初めての相手と会ったのは、それから1か月後の日曜日の午後だった。
「ごめんなさい、遅れてしまって」
優雅にシフォンスカートを翻し、春らしいラべンダー色のカーディガンを肩にかけた彼女は待ち合わせのカフェに現れた。
「このお店に入ってすぐに分かりましたあなたが○○さんだって」
細い手首をくるりと返し、洗練された仕草で椅子を引きながら彼女は言った。よく通る声は5月の日差しに温められ、蒸れた店内の空気までを清く一新するようだ。
綺麗に巻かれたツルツルの髪、品良く顔を彩るパステルカラーのメイク。まるでファッション誌から抜け出て来たように彼女は美しかった。
本当にこの人が私なんかとマッチングしたのか。何かの間違いではないか?
驚きと緊張でうんともすんとも言えないまま、私はしばらく呆然と彼女を見つめるより他になかった。
彼女が指定してきたのは、私がずっと前から行きたいと思っていたカフェで、何度かのメッセージのやり取りののちに
「初めてでどんなところか分からないのだけど、前から行ってみたいと思っていたんです。良かったら行きませんか」とURLが送られてきた時には嬉しさで思わず飛び上がりそうになった。
なんせ私には、これまで行きたいカフェに誘える友達もいなかったのだ。中高時代の友達とは、年に数回グループで会うだけ。それも、誰それが結婚した、だの職場の上司がうざい、だの、変わりのない愚痴ばかりが飛び交い全く面白くない。しかしそれも仕方がない。私はただ、キョロキョロしながら相槌をうち、皆のタイミングを図って同時に笑うだけのびびりだから、誘ってもらえるだけマシなのだ。リーダー格の子の「今度はここの店に行こうよ!」という声にただ従い、行きたいお店を言い出すことすらままならない。
そのグループですら、皆、結婚だの出産だので集まる回数は年々、減っている。
彼女はメニューを取り、さっき私が注文したのと同じきなこ豆乳ラテをウエイターに注文した。
気まずい沈黙。何か言わなければ。
先に口火を切ったのは彼女の方だった。
「あの、私、こんな素敵な方がいらっしゃると思ってなかったので、緊張しちゃって」
素敵!?
私が!?
驚きのあまり赤面しながら、私は彼女を凝視した。言われてみれば、彼女のまつげは細かく震え、口元は心なしか引きつっているように見える。チークよりも広範囲で赤らんだ頰。
「いえ、そんな、恐縮です」やっとのことでそう言い、私は顔の前で高速で手を振った。「私なんて、そんな」
……なんと続けるのが正解かわからない。2秒、3秒、無言が続く。
窓辺の日差しは強く、外の景色が膨らんで見えるほどに蒸し暑い。テーブルに落ちた樹木の影、豆乳ラテの液体と氷の境目の白っぽい部分、そういうものこそ目に飛び込んでくるものの、肝心の彼女と仲良くなるための一言を、私のうかつな脳は一向にひねり出してはくれない。
彼女は困ったように足を組み直した。
その時ふと、彼女の胸元で見覚えのあるものが揺れた。
「それ」
え、と彼女は声を上げる。
「それ、◯◯のノベルティの……」
私は彼女の胸に下げられた、猫のモチーフの陶器のネックレスを指差した。私の大好きなイラストレーターさんが、とあるコスメブランドの限定コフレBOXのノベルティのために描き下ろしたファン垂涎のアイテムだ。
「そう! そうです!私、このブランドも、××さんの猫のキャラクターも大好きで」
彼女は嬉しそうに顔を輝かせると、ネックレスを指先で持ち上げて見せた。
「まさかコラボしてくれるなんて思ってなくて。予約開始してすぐに申し込んじゃいました」
「私も◯◯、好きなんです。毎シーズンは使い切れないから買えないんだけど、いつも欲しいなって。前回もそれ目当てで予約しようかどうか迷ってるうちに、結局逃しちゃったんですけど……」
「色もデザインも可愛くて、迷っちゃいますよね。コフレのアイテム数も多くて」
「コフレも、いつも3種類あるじゃないですか。どのセットにするか迷っちゃうんですよね。全部の色味が似合うわけじゃないし」
「あ、よかったら今度のBOXは一緒にAバージョンとBバージョンを買って、お互いに欲しいアイテムを交換し合いませんか?」
「わあ、いいですね、それ!」
夢みたいだった。初対面の相手と、こんなに会話が弾むことが。私の一言一言に、こんなに嬉しそうなリアクションを返してくれる人がいることが。
一度、火がついたら止まらなかった。
私たちはそれから話して話して話しまくった。これまで堰き止めていたものを、一気に解き放つように。
話せば話すほど、私たちの中にある共通点が掘り起こされて行くようだった。こんなにも私のことをわかってくれる人間、私を肯定してくれる人間は他にいないと思った。
とっぷりと日が暮れ、ラストオーダーが終わり、最後に1組の客になるまで、私たちはずっと、2人きりの繭の中にいた。