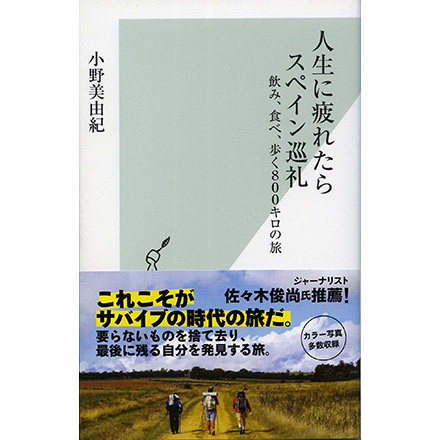彼女の訃報が届いたのは、数か月後のことだった。
交通事故だった。
肌寒い10月の終わりの夜、私は季節外れの夏物の喪服に身を包み(急だったので買う暇がなかったのだ)身を縮めながら通夜の会場に向かった。
彼女の両親は、彼女のスマホの履歴からマッチングサービスでやり取りしていた“親友”全員に訃報を送ったらしい。弔問客の中には、サービスで彼女と出会ったと思しき幾人かの女たちがいた。彼女たちは「どの程度」悲しんだらいいかわからないという顔をして、所在無げに佇んでいた。
斎場には私たち個人の客とは別に、彼女と同い年ぐらいの女の子たちの集団がいくつかあり、漏れ聞こえる会話から、中高の同級生のグループや、大学のサークルのグループ、バイト仲間のグループであることがうかがい知れた。
マッチングで出会った人たちと彼女たちの間には明確な温度差がある気がした。彼女たちはオレンジの熱気を帯び、それはもうがむしゃらって感じで泣いてた。まるで私たち、泣くことが義務です、権利です、って言わんばかりに。
私はそれを見ながら「なんだ、彼女はエージェントに頼まなくたって、友達、作れたんじゃない」って少し意地悪な気持ちで、葬儀場の隅の温まりきっていない自販機のぬるいココアを飲んでいた。
「あなた、~~さんのおともだちでしょ?」
突然、声をかけられて私は振り返った。
白髪の小柄な老婦人が立っていた。
「あなたも、あのサービスで出会われたんでしょう」
その婦人の顔は額のきわから耳の下までみっちりと白粉で塗り固められ、シワというシワに粉が落ち込んでかえって生気を失って見えた。会場の蛍光灯に照らされたその顔は、通夜の場に似合わず妙にてらてらと明るい。
光沢のある高価そうな黒のブレザーとワンピースが、かろうじて彼女の社会性を保っている。
「はあ……そうですけど」
「あなたのお話、~~さんから聞いてたのよ。78%の相性なんですってね」
私は驚いた。老婦人はアイシャドウで黒々と囲んだ小さな目を輝かせて続けた。
「~~さんを亡くしたのは惜しいわね、素敵な方だったのに。私、あのサービスで出会えてとっても嬉しかったのよ」
あのサービスでは、指定さえしなければどんな年齢の人とも出会える。私はこんなばあさんになってもまだ友達を必要とするのか、と軽く絶望的な気持ちになった。
「私はね、84%だったのよ。すごいでしょう?」ニヤニヤしながら彼女は言う。強引に描かれた左右非対称の眉毛が、奇妙な形にひしゃげる。
だからなんだ。死んだ人間との相性なんか競ったって、しょうがないじゃないか。そう口を開きかけた時、
「彼女、犬を飼っていたでしょう。シェットランドシープドッグ。うちと一緒なのよ、よくその話で盛り上がったわぁ」
え、と思わず言ってしまった。私は犬が死ぬほど嫌いで、近づいただけで鳥肌が立つ。
「彼女、オペラ鑑賞も大好きだったでしょ。私もね、月に1度はご一緒していたのよ。あなた、オペラは?」
そんな話、あの子の口からは一度も聞いたことがない。
「……観ません、犬も飼っていません」
そう小さな声で言う私を、老婆は眉毛をちょっと持ち上げて見た。
「彼女はご家庭が複雑でね、育てのご両親はなんというか、平凡なご職業でしたけど、本当はね、いい家のーーかなりね、田園調布のあのあたりのーーご出身でね。あ、私もそこの出ですけれどもね。本当のお父様は音楽関係の有名な方だったそうで」
黙る私をよそに、ばあさんは唾を飛ばしながら喋り続ける。芋虫みたいに不気味にうごめく口元から、知らない彼女の情報がこぼれ落ちてくる。
「音楽教育だけは実のお父上がされたそうでね、オペラにとっても精通していらっしゃって。あそこまでお話のできる方なんて、年寄りでもなかなかいないのよね。やっぱり、教養がないと」
マッチングサービスでは、本人の望まない情報は開示されない。相手がどんな人生を送って来たのかは、本人の口から語られるよりない。相手と自分の、どの部分がマッチしていないか、についても。
私と彼女は多くの部分が共通していたはずだった。
両親が厳しくて大変で、友達と遊ぶこともままならなかったこと、漫画を読むのと映画を見るのが好きなこと、「ひみつ堂」のかき氷が大好きなこと、清澄白河と門前仲町と谷中の雰囲気が好きなこと。渋谷と港区が苦手なこと。
好きなインディーズのミュージシャンが同じで、今度、ライブに一緒に行こうよ、って盛り上がっていたこと。
「あなたは」
濡れたモップみたいにじっとりと湿った目で、彼女は私を見た。
「彼女と78%もマッチしてるお友達なら、きっと楽しくお話しできるんじゃないかと思ってたのだけど、」
べちゃりとした視線が心に触れる。薄い喪服の内側を、冷たい風が駆け抜けてゆく。
「音楽にご関心がないのじゃね……私、オペラを一緒に観に行けるお友達が必要なの」
そう言い残すと、彼女はさっと踵を返して去って行った。まるで、この場に留まる理由などは何もない、と言うかの如く。
全身を汚水に浸されたような気分で、私は一人そこに残され、しばらくの間佇んでいた。
(後編に続く)
- 4
- 4