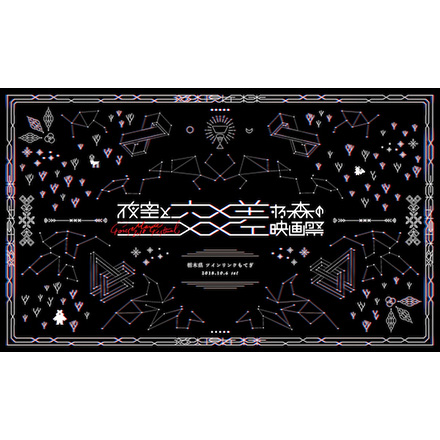今年の5月、是枝裕和監督の『万引き家族』が『カンヌ国際映画祭』の最高賞、パルム・ドールを受賞した。そんな時、私は深夜の喫茶店でドラマの打ち合わせをしていた。もう4日寝ていない。寝たい、寝たい! 寝たい!! 朝日を浴びながら、パルム・ドールの一報をスマホで知り、限界の中こうつぶやいた。「これで日本映画、何か変わったらいいな」と。
5年前、是枝監督の会社の採用試験を受けた。20歳。募集年齢は22歳からだったが、どうしても受けたくて詐称した。思いもよらぬことに、最終まで残ってしまった。「でも、君、よく見たら20歳か。授業あるよね?」と是枝監督。ああ、落ちたなと思った(まあ、落ちたんだが)。落胆した帰り道、なんとなく渋谷のアップリンクに寄った。そこで『わたしはロランス』が目に入り、ざっくりとした予備知識の中、劇場へ入った。
映画が終わり、館内が明るくなる。すぐに立てなかった。腰を抜かしていた。よろよろと渋谷の街を歩き、苦しさに堪え兼ね水を買って一気飲みした。
言語化できない感情を抱え、海を越えてやってきた光を3時間浴び続ける幸せはこの上なかった。とてつもなく悲しみが溢れた時、部屋で1人縮こまるでもなくファミレスで泣きながら愚痴るでもなく、ただただ天井から1トン近くの水が降り落ちていた。もう二度と訪れない2人だけの幸せには、誓いのキスや指輪なんかじゃなくって、カラフルな下着が宙を舞っていた。(グザヴィエ・)ドランの映画には、規範がなく、確かな愛だけが溢れていた。

『わたしはロランス』
「私たち、こうあるべきだ」と渋谷の街で一人思った。映画にはルールがない。良いものは良いのだ。カットのつながりとか、リアルじゃないとか、イマジナリーとかもうそういうのマジでどうでもいいよ。そのルール、守ってたら君らの心は震えるのかよ? 違うでしょう。私たちは何のために映画を観にきているんだ? と。私たち、日々の中で越えられない何かをスクリーンに求めているはずだ。『わたしはロランス』のコピーはこうだ。「愛がすべてを変えてくれたらいいのに」
あの映画の日本での公開から5年。今のところ、愛はすべてを変えてくれない。でも、『わたしはロランス』を観た私たちは、何かを変えたいと思ったはずだ。ああ、何かを越えたいと、渋谷の雑踏の中で小さく噛み締めたことを5年後、再び朝日を浴びながら思ったのだった。