GirlfriendsとMembersのみなさま同士の出会いや、対話を重ねる機会をつくり、そこからともに創造し、行動していくオンライン上の場所「Girlfriends ROOM」。昨年8月17日(月)に行われた「安心できる場で、自分の言葉で、フェミニズムを語りはじめよう」の回では、Girlfriendsのエミリーさん、きくちゆみこさん、楠田ひかりさん、垂水萌さん、麦島汐美さん、めぐみあゆさんの6名が集い、自身とフェミニズムの出会いと、今気になっているテーマについて話してくれました。
友達と夜ご飯を食べながら「私はこう思っているけど、あなたはどう思う?」と話すような、気軽で安心できる場所で話せること。誰かから借りてきた言葉をつかわずとも、自分の言葉で、自分のペースで話せること。そんなことを大切にしながら行われた、私たちの日常の延長線上でフェミニズムを語る会。
今回は6名がフェミニズムに出会ったきっかけと、イベント時に考えていたフェミニズムにまつわるテーマを紹介。さらに、フェミニズムを考えるにあたり影響を受けたという本をブックリストにしました。気になったテーマがあったら、ブックリストの本もチェックしてみてくださいね。
大学時代に感じた「違和感」がきっかけでフェミニズムに興味を持った三人。「『ああ、これや!』と自分の経験に言葉が与えられた感覚」
まずはみなさんに、どうしてフェミニズムに興味を持ったのかお話ししていただきました。めぐみあゆさん、エミリーさん、麦島汐美さんは、大学時代に感じた「違和感」がきっかけになったと言います。
めぐみさんは、大学に入学してから入った音楽サークルで、ときおりミソジニー的な雰囲気を感じ、ただ「女性」であるだけで性的なまなざしで見られることに違和感を覚えたそう。
めぐみ:例えば、よくあることですけど「オンナ」ってひと括りにして呼ばれることが嫌でした。そういう自分の感情に対して「はて? これはなんだろう」と思っていたのですが、大学のゼミでフェミニズムという言葉やそれにまつわる本を知り、「ああ、これや!」と自分の経験に言葉が与えられた感覚があって。大学院でも修士論文ではミランダ・ジュライや、カルメン・マリア・マチャドなどの作家を取り上げ、女性の体がどのようにまなざされるか、また、固定的なジェンダーロールに頼らないコミュニティのありかたについて、考えつづけています。マチャドの『彼女の体とその他の断片』は、「女性」であることの喜びも、悲しみもしんどさもそのまま入っていて、おすすめです。

『彼女の体とその他の断片』(カルメン・マリア・マチャド著、小澤英実・小澤身和子・岸本佐知子・松田青子訳、エトセトラブックス)
エミリーさんは高校生の頃から、性的な対象でなく人間として見てほしいという気持ちを抱いていたと言います。その一方で、ずっとフェミニズムは怖いものだというイメージがあり、一冊の本がその印象を変えたそう。
エミリー:大学生になってからも、例えば友達が合コンに行った時に「支払いが割り勘だったんだけど、ありえなくない?」といった話をしているのを聞いて、私は「女性だからってなんで払ってもらわなきゃいけないんだろう」とずっと違和感を感じていました。フェミニズムをちゃんと考えるようになったきっかけは25歳のとき。友人とチママンダ・ンゴズィ・アディーチェさんの『男も女もみんなフェミニストでなきゃ』(チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著、くぼたのぞみ訳、河出書房新社)という作品の刊行イベントに行ったんです。それで興味が湧いて、いろんな本を読むうちに今までフェミニズムと関係ないと思っていたこともつながっていることがわかって。それから自分の感じていた違和感もだんだん言語化できるようになりました。
麦島さんは、大学に入ったときに今まで自分たちで行ってきたことも「男子の力なしではできない」とされてしまったことに戸惑いが。
麦島:大学に入ったら「あれ?」って思うことが増えて。当時は集団的自衛権や平和安全法制をめぐるデモが盛んで、私もなんとなく参加していたんですけど、そこでデモ参加者の方から60年代のウーマンリブについて聞く機会があって。全共闘運動の先頭に立つのは男の人で、裏では女の人が家事をさせられていたような抑圧があったそうなんです。その話がきっかけでフェミニズムについて考えるようになりました。最近はイ・ミンギョンさんの『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』という本を読んで、すごく救われた気持ちになって。話したいという気持ちを持ちながら、話したくない時は話さなくてもいいんですよね。

『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』(イ・ミンギョン著、すんみ・小山内園子訳、タバブックス)
他者との関係を考える中でフェミニズムと出会った三人。「言葉を知ることって本当に大事だなと痛感しました」
きくちゆみこさん、垂水萌さん、楠田ひかりさんは、男性や家族などの他者との関係を考える中で、フェミニズムに出会ったと言います。
「いまだにフェミニズムというものをどう考えていいかわからない」と正直な思いを話してくれたきくちさん。海外文学の男性作家に憧れ、今まで「23歳の男性みたいな気持ちで生きてきた」と言います。そんなきくちさんの気持ちに変化を与えたのは、2人の女性思想家でした。
きくち:私はスコット・フィッツジェラルドやレイモンド・カーヴァーのような男性作家に、同一化したいほどの憧れをずっと抱いていて。当時そういう気持ちは「髭を蓄えたい」というような、個人的な願望や興味から来ているんだと思っていたんです。でも、その後アメリカの大学院で文学理論を学んだ時に、ジュリア・クリステヴァというフランスの思想家と、ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァクというインド系の思想家の本に出会って。特にスピヴァクの『サバルタンは語ることができるか』を読んだ時に、女性で、さらにマイノリティでもあったら、そもそも書くことも話すこともできない人たちがいるということに、だんだんと気づきはじめました。
それから、子供を産んだ後にケイト・ザンブレノの『ヒロインズ』(ケイト・ザンブレノ著、西山敦子訳、C.I.P.Books)に出会いました。これは声を無化されてきた女性たちの声を集めた本なんですけれど、そこで初めて、自分が男性性に惹かれ続けてきたのは、単純に自分の興味というだけではなくて、実は男性優位の社会に強く影響されてきたからなんじゃないか、ということに気がついたんです。「ああ、遅かった!」と思いながら、今も少しずつ少しずつ学んでいる感じです。

『サバルタンは語ることができるか』(上村忠男訳、みすず書房)
垂水さんにとってフェミニズムは「気がついたら隣にいた」存在。成長していく中で、「モテ」や「女性としての振る舞い」というものが求められ続けることに窮屈さを感じてきたそう。
垂水:特に恋愛に向き合おうと思って、「モテとは」みたいなことを突き詰めて考え出すと、モテる女性像に応えようとする自分と生来持っている内面的な自分が解離してしまうような気持ちに苛まれていました。そんな中で、大学時代にヴァージニア・ウルフの『自分ひとりの部屋』を読んだんです。思えばこれがフェミニズム的なものとの出会いだったのかな。今は特に「フェミニズム」を勉強しているというわけではないんですけど、一見関係がなさそうなものの中にもフェミニズムに関係するものが見出だせるなと思っていて。フェミニズムといろんなものとの関係を考えるのが楽しいです。

『自分ひとりの部屋』(ヴァージニア・ウルフ著、片山亜紀訳、平凡社ライブラリー)
ご家族、特にお母様との関係でフェミニズムについて考えるようになったという楠田さん。大学入学後に一人暮らしをするようになって、家族が抱えていた問題は自分たちだけのものではなかったことに気がついたそうです。
楠田:最近になって母が「20年前にはDVという言葉が今ほど浸透していなくて、自分だけの問題だと思っていた」と言っていて。その時に、言葉を知ることって本当に大事だなと痛感しました。今思えば、そのことが大学院で研究を続ける一つのきっかけになったのかもしれません。大学院ではヴァージニア・ウルフやフェミニズムについて学んでいます。院に入学したのは2018年だったんですが、ちょうど『ヒロインズ』やはらだ有彩さんの『日本のヤバい女の子』(柏書房)が話題になっていた時で。自分がフェミニズムという言葉を知って、過去のいろいろな違和感を言語化できたタイミングで、運よく素晴らしい本に巡り合えたなと思います。2019年に出版された長田杏奈さんの『美容は自尊心の筋トレ』(Pヴァイン)、川上未映子さんの『夏物語』(文藝春秋)にもすごく影響を受けました。

『日本のヤバい女の子』(はらだ有彩著、柏書房)

『美容は自尊心の筋トレ』(長田杏奈著、Pヴァイン)
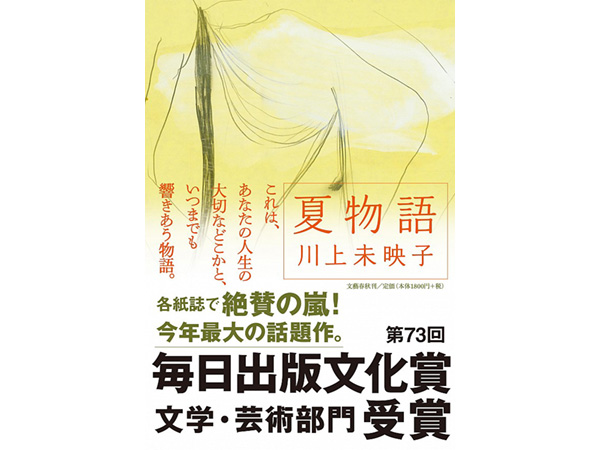
『夏物語』(川上未映子著、文藝春秋)
- 1
- 2




















