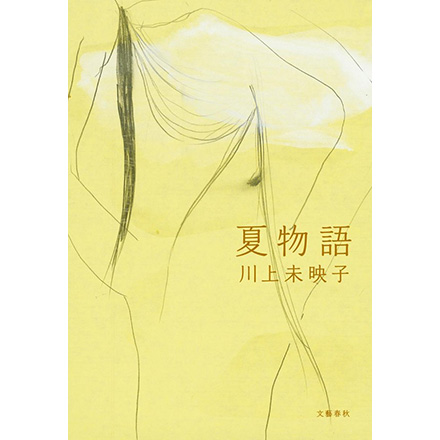人はいつのまにか生まれていて、いつか死んでしまうその日まで、時間は止まらないし、どんなに強く願っても、時間は、誰かは、かえってきてくれない。すべての呼吸、言葉、時間、ふれあい、感情、思い出は一回きりで、その「取り返しのつかなさ」にたいして、小説家の川上未映子さんは、子どもの頃から切実な興味をもって生きてきたといいます。
新作『夏物語』は、その「取り返しのつかなさ」の最たるものである、「生まれてきてしまうこと/そして死んでしまうこと」のいっさいが描かれている、これまででいちばん長い物語です。たくさんのお話をうかがったので、今回は前編・後編にわけて、川上未映子さんとの対話をお届けします。前編はおもに、「子どもを生む」ことについて。『夏物語』というタイトルからは、本作が女性やフェミニズムということに限定されない物語だということが伝わってきます。これは女性にかぎらず、すべての人間にかかわる、人生のお話です。
【後編】川上未映子が提示した、正解がない家族関係を結ぶときの大切な指針
生や死、そしてセックスを含む「性」に関するものを女性の作家が書くと、「女性の問題」としてクローズアップされるんだけど、それはすべての人間に関わっていること。
―『夏物語』には、出産と性行為の関係、精子バンク、子どもを生むか生まないかとその理由、そして人間が生まれて死ぬこと……すごくいろいろなトピックが詰まっていて、読んでいるうちに自分の人生が枝分かれしていくような感覚がありました。
こっちの人生だったらこうだったのだろう? と自分が選択していない人生を想像しては、立ち止まってまた考えるような、まさに「終わりのない話」をえんえんとしている気持ちになる物語だと思います。あらためて『夏物語』を書きはじめたきっかけを聞かせていただけますか?
川上:長編小説を書くときはいくつもの複数の動機があるんだけれども、どの小説にも大きい根本の動機のようなものがあって。それが、「どうして世界にはこんなふうにすべてが存在して、そしてなくなってしまうのか」という生死の問題なんです。それを「恋愛の関係」に見出すこともあれば、「身体」に見出すこともあって、それは小説ごとに変奏曲のように変わってきたのだけれど、根底にはそれがあるんだと思います。
生きているわたしたちにとって、もっとも取り返しのつかないものはやはり「死」だと思うのですが、それは同時に「生まれてくるということ」の取り返しのつかなさからはじまっているわけですよね。それで、「生」と「死」の両方の取り返しのつかなさについて書こうとしたら、その間の「すべて」のトピックを含めることになりました。

川上未映子さん
―たしかに、生まれることは「生まれてくる」というふうに言われて、死ぬことは「死んでしまう」と言われがちだけれど、「取り返しのつかない行為」という意味では、生まれることも「生まれてしまう」ことですよね。
川上:うん、産むほうと、生まれてくるほうには、越えられない非対称性があるよね。子どもは、ある日とつぜん親によって、いきなり存在させられてしまうわけだから。
―この『夏物語』では、『乳と卵』(2008年)の登場人物たちの約10年後が描かれていて、未映子さんの作品史上いちばん長い長編になったというのも、生から死までの「すべて」のことを物語で描こうという意思の表れのように感じました。
川上:生や死、そして生がはじまるセックスという行為を含む「性」に関するものを女性の作家が書くと、「女性の問題」としてどこか矮小化してクローズアップされるんだけど、それはすべての人間に関わっていること。そこから、子どもをつくるときに必須である男性の存在についても、しっかり書いてみたいと思ったんです。そのためには『乳と卵』の3人の登場人物である、夏子と姉の巻子、その娘の緑子を、いまもう一度語り直す必要があったという感じですね。
わたし自身は出産をしたけれども、わたしがしたことって一体なんだったのか? ということは、死ぬまで考えていたいことのひとつなんです。
―「生殖」という言葉から子どもを生むという話に移っていけたらと思うんですけど、『夏物語』では「子どもを生む」ことに関してもいくつものはてなを投げかけていますよね。まず『乳と卵』でも描かれていた、「女性の身体をもって生まれた人間は、自分のなかに子どもを生める機能が備わってしまっている」ことに、個人としてどう向き合っていくのか? という問題。
川上:『夏物語』で『乳と卵』の登場人物をもう一度書こうと思ったのは、『乳と卵』のときには12歳だった緑子の存在が大きいです。緑子は直感的に「反出生」的な考えを持っているんですよね。
生きているうえでの「嬉しい」とか「悲しい」とか「辛い」とか「苦しい」という感情も、なにもかもが生まれてこなければ存在しないのだから、生まれてこないほうがいいんじゃないかという感覚について、いつか長編で扱いたかったんです。
―「生殖して子孫を残すこと」が、ある意味であたりまえの行為だとされているけれど、なぜ子どもを生むのかという理由も、本当は人それぞれにあるはずですよね。そして生まれてきた側に関しても、生まれてきたことを心から幸せに思う人や瞬間ばかりではないはずで。
川上:「やっぱり子どもほしいよね」って、自然とすっと行動できる人もいると思います。でも、そうじゃない人もいますよね。それは考えるに値する大事な問題だと思う。
―そのことを、『夏物語』では「誰も生まれてくる人のことを考えている人なんていないんじゃないか」というような強い言葉で書かれていて。そこまで強い言葉で書いたのはどうしてなのかなって。
川上:うん、生まれてくる人のことを思って子どもを産む人は誰もいない、とわたしも思うな。みんな、結局は自分のためか、深く考える必要もないくらいに自然なこととして産むんだと思う。わたし自身は出産をしたけれども、これって本当のところはいったいどういうことだったのか? ということは、死ぬまで考えていたいことのひとつなんです。夜、寝顔を見ながら、このさき息子に起きるかもしれない色んなことを想像しながら、よく考えてる。
- 1
- 3