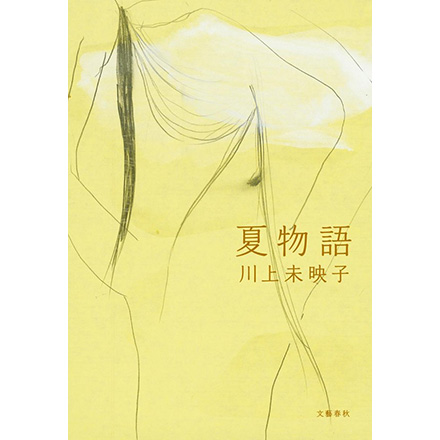子どもを生むということが、もう自然なことではなくなってきている。
―わたしはいま32歳なんですけれども、昔から子どもを生みたいと強く欲望するほうではなくて、だから『夏物語』を読んで、子どもを生む/生まないにとどまらず、誰と子をつくり、誰と育てるのか……。本当にいろいろな選択肢があると感じたし、そして読み終えたいまも、なにが自分にとっての正解なのだか、ますます全然わからないなと思ったんですよ。
川上:うんうん。
―それこそ以前、政治家による「3人以上の子どもを生み育てていただきたい」という発言がありましたけれど、それは子どもというのが、旧来的な「国家」のものだという考えがベースにあってこその言葉なのかなと。
『夏物語』では、「国家」の所有物のように捉えられてきた子どもという存在が、「家制度」のものへと変化し、そしてだんだん「個人」のものになっていく、その変化や未来のあり方を描いていると思いました。そしてその選択肢がありすぎる未来において、ひとりひとりはどんな倫理観をもったらいいのか? なにを拠り所にすればいいのか? という疑問を予感した作品のようにも感じて。
川上:そうですね。その政治家の言葉は「子どもを生むかどうか」をひとりひとりが考えることさえ思考停止させるような発言だし、それに「生んでいただきたい」と言われたからといって、実際問題として育てられないという現実があるわけじゃない。
経済的にも、労働的にも、本当に難しいですよね。そう考えると、子どもを生んで育てるということが、当然なことではなくなってきていますよね。結婚して、結婚式を挙げて、車を買って、家を買って、大学にも行かせるなんて、そんな特権階級みたいなこと、ほとんど不可能じゃないですか。そして、そんな昭和モデルがすべての人にとっての幸せだとも限らない。

その人の幸せがなんであるのか? ということは、他者ではなく、自分で決められるようになるといい。
―最初の話に戻りますが、「子どもを生めるかもしれない身体をもっている」からこそ、自身の「生殖機能」をつかうべきか悩んでしまうことがある。それをしなかったとき、あるいはできなかったときに、「社会のなかで役割を果たしていないな、まわりの期待に答えられていないな……」というふうに、国家や社会、家制度によって、個人が責められることがないようになってほしい、って思うんです。
川上:たしかに。「仕事をしている女性はすごいかもしれないけど、子どもを生んでいるわたしのほうが偉い」みたいな風潮もまだあったりしますよね。……でもそっか。わたし、子どもを生まないかもしれないと思っている時間はあったけど、社会の役割を果たしてないと思われたらどうしよう、とかは1mmも思ったことない。1回もない。
―ほんとですか!
川上:うん。親に顔向けできないとか、親に孫の顔見せてあげたいとか、そういえば何人かの友達が「先祖代々の血をここで止めるのはしのびない」みたいなことを話してて、びっくりしたことがある。わたしの場合は、そういうのは1回も思ったことないです。でも、自分にはそういう経験はなくても、たとえば地元に帰ったときに、親戚に「孫」っていうお酒をどん! って置かれて、「孫いないからこれ飲むわ」みたいな圧を受けたって聞いたこともあるし、もっと辛い目にあった話もきくし、日常的な抑圧が強いとそういう意識にもなるんだと思う。
子どもを生む/生まないにかぎらず、その理由がどこにあるのかということや、その人の幸せがなんであるのか? ということは、他者ではなく、自分で決められるようになるといいよね。そのために、一個一個、解放されたらいい。そして、解放されて、個人で考えられるようになったときの支えとなる倫理や拠り所が、これからつくれたらいいですよね。
- 3
- 3