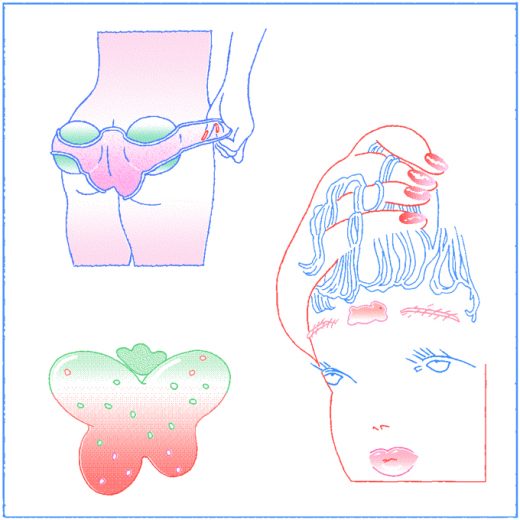小顔矯正というものに行った。新宿駅から少しの汚い雑居ビルにそのお店はあって、入り口はどう見てもふつうの家だ。かろうじて手作りの看板に店名が書いてある。インターホンを鳴らすと「どうぞー」と声がし、中に入る。ドアの向こうで、過剰に女性らしいインテリアとふわふわのスリッパ、髪をひっつめた肌の綺麗なお姉さんが迎えてくれた。
椅子にすわり問診票のようなものを渡される。出てきたお茶は甘い花の匂いがした。
・気になるところはどこですか? ◯をしてください
目 鼻 輪郭 たるみ むくみ その他……
首を傾げながら大きな丸ですべてを囲んだ。ここでは自分の不出来な造形を気にしていい。話していい。直そうとしていい。最高だ。
小学校4年生くらいの時、ピンクのフリフリのスカートを学校に履いていったことがある。服なんて当然親に買ってもらっていたし、特に何も考えていなかったのだけれど、当時の私は男子生徒に「ボス」と呼ばれる程度にはやんちゃで、木にも登るし人も蹴るし虫も食べるベリーショートのメガネ女だった。そんなボスの突然のピンクスカートに生徒一同は驚愕し、「かわいくない」「似合わない」「女装してるみたい」と批判の嵐。その突風の中で私は生まれて初めて「かわいい女の子」という価値観を知り、そしてそのカテゴリーに自分が入っていないことを知った。
それ以来ずっと「かわいい」に呪われてきた。
ピンクの服を着られない。カシスオレンジを頼めない。褒め言葉を受け取れない。すべて枕詞に「かわいくないから」がつく。呪いである。誰よりも美しいあの子も「でも鼻が高すぎるから」と言う。私たちは皆呪われている。それは自分に、完璧ばかり提示する社会に、同級生のあの子にかけられた、どうにも解けない呪い。
自分はかわいくないのだという自意識を引きずったまま中学生になり、無理なダイエットをした。高校に入ってからは美術に打ち込んだ。「ブスのチョーヒカル」より「絵が上手いチョーヒカル」になれば、ブスから逃れられるはず。今後顔で優遇されることなどないだろうから、何か特技が必要だと思った。なんとも悲しい16歳である。そんなこんなでブスから逃げ続け、果ては「かわいくなろうとしていると思われるとブスが目立つのでは?」とかわいくなることからも逃げ出した。私は絵を描き続けた。
ところがどうだ、絵がまあまあ上手くなって、仕事ができるようになってきた頃、私はすごいことに気づいてしまった。どんなに逃げても、どんなにたくさんの特技を身につけても、美しくないことは悲しい。かわいくないことは苦しい。それはもうどうしようもなかったのだ!
もう「美しい」ことだけが人生が上手くいくためのすべてではないことは知っていた。美しくないから手に入れることができた技術が、かけがえのないものなのもわかっている。だけど、逃げられないのだと。ああ、逃げられませんでした。押入れの奥にしまっていただけで、美しくなりたい気持ちはなくなってくれませんでした。
だから、再会したその気持ちに私は向き合うことにした。面倒なことは無理だけど、美しくなる努力をしてやろうじゃないか。そりゃ橋本環奈にはなれませんが、私は私のできることを。そう思ってはじめて小顔矯正の予約を入れたのだった。
「ここに仰向けで寝てくださいねー」
甘ったるい声でお姉さんが言う。
部屋に唐突に置いてある台に寝ると、顔にタオルをかけられる。
「痛かったら教えてくださいねー」
まるで歯医者みたいなことを言うんだなと思った。所詮マッサージなのに大袈裟だな、そう思った瞬間、顔に信じられないくらいの圧がかかった。
「え!? 痛! 痛いです!!!!!」
「あーそうですかー大丈夫ですよー」
「え!?!? やめないパターンのやつだ!?!?」
かわいいピンクの服を着たお姉さんは、まるで私に親でも殺されたみたいな勢いで私の顔をギュウギュウ押した。こんな物理的に顔って小さくなるの? システムとしてシンプルすぎないか? 痛みと疑問でぐるぐるして、途中自分が何をしているのかわからなくなって無性に笑えた。1時間たっぷり顔を矯正され、お姉さんはようやく私を解放した。めちゃめちゃ痛かった。
帰り道、顔全体の鈍痛を引きずりながら、わたしは清々しかった。効果のほどは正直わからない。信仰みたいなものかもしれない。それでも清々しかった。かわいくなりたい気持ちは最高にかわいいのだ。ようやく私は自分に美しくなる努力を許せた。
かわいいの呪いを解くことは、多分自分にしかできない。私たちは私たちに、かわいくなることを許してあげなければいけない。誰かに言われたから、あの人と違うから、いろんな理由をすべて無視してほしい。自分を一度許して、そこから目指す方向へむかってほしい。自分で自分の「完璧」を見定めてほしい。そうしていればきっと、呪いはもうすぐ解けてくれる。