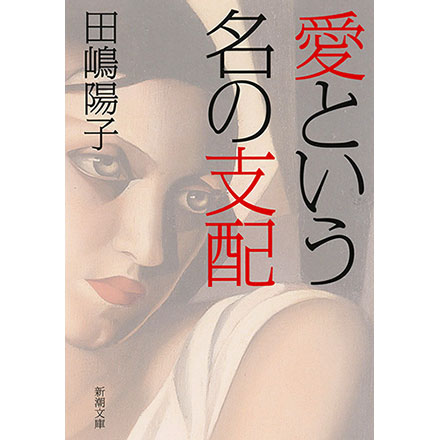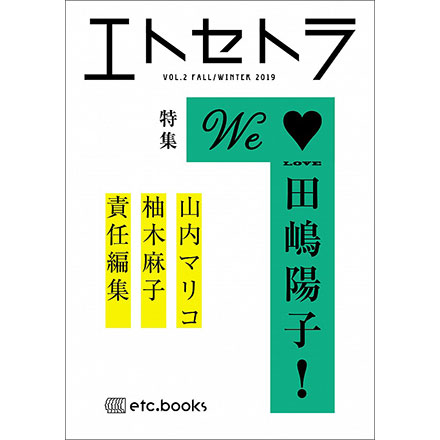田嶋陽子さんは、討論バラエティ『ビートたけしのTVタックル』への出演で高い知名度を得た、日本を代表するフェミニストだ。時は1990年代、平成がはじまったばかりのころ。フェミニストがどういう人なのか、フェミニズムがなんなのかまったく知らなかった当時のわたしも、この番組でのやりとりを面白おかしく見ているうちに、「フェミニスト=田嶋陽子」と同義語のようにすり込まれていった。そしてそのイメージは、世間一般にも深く浸透した。
なにしろキャッチーな存在だったのだ。おかっぱヘアにメガネの組み合わせ、低く落ち着いた声できっぱりと物申し、相手があのビートたけしでも一歩も引かない。議論に熱くなっているときの険しい表情と同じくらい、「ガハハ」という擬音語がしっくりくるビッグスマイルも印象的だ。誰とも似ていない強いキャラクターは、テレビが絶大な影響力を持っていた時代、圧倒的な拡散力でもって日本中に広まった。その人気は、CMやドラマ、映画にも抜擢されたほど。大学で英文学と女性学を教えるフェミニストが、テレビでタレントと互角の個性を発揮し、有名人の仲間入りをしたなんて、後にも先にも彼女のほかにいない。
そう考えると、今よりよっぽど進んだ時代だった気がしてくる。けれど、当時の田嶋陽子さんの発言をちゃんと理解し、なおかつ肯定的に受け取っていた人がどれだけいただろう。当時のわたしは、もちろん全然わかっていなかった。テレビという巨大な権威が示してくる正しさは、常にスタジオのマジョリティであるおじさんパネリストの側にあった。田嶋陽子さんはいつも、その一群と対立関係となるヒール(悪役)の役回り。女性であっても彼女を助ける人はおらず、男性と一緒になって嘲笑う。そんな、いじめにも似た構図として記憶に残っている。
愚かな大衆であるわたしはスタジオの空気に従順で、いくらでも乗せられて笑い、疑うことを知らなかった。それどころか、彼女が女性をかばったり、女性の味方をする発言をしても、その「女性」に自分もカウントされていることすら、自覚できていなかった。自分の頭で考えることを放棄し、テレビの手のひらの上でひたすら転がされ、その結果、いつも最後は「たけしがいいこと言ってたな」「さすがたけし」という後味だけが残った。そういう見せ方を、番組は一つの型のように作り上げていた。
こうして、わたしをはじめ視聴者の中に、フェミニストとイコールで結ばれた田嶋陽子さんは、どこかネガティブな存在として印象付けられることとなった。
2001年には参議院議員となり、気がつけばキー局の番組でその姿を見ることは少なくなっていたけれど、「フェミニストの名前を一人あげてください」と訊いてまわれば、きっとほとんどの人が「田嶋陽子」と即答するだろう。そう、彼女は今も、日本一有名なフェミニストなのだ。
それなのに――。わたし自身がようやくフェミニズムに目覚め、女性学の本に興味を持つようになったとき、「よし、田嶋陽子の本を読んでみよう!」とは、不思議と思わなかった。自分が目覚めたフェミニズムというものと、田嶋陽子さんとの間には、なぜか大きな溝があった。フェミニズム関連の本を買い込み、古典も新刊もチェックしていたくせに、そこに田嶋陽子さんの本は入っていなかった。もっとおかしなことに、フェミニズムにまとわりついていたネガティブなイメージが自分の中で払拭されてもなお、田嶋陽子さんのイメージは昔のまま、依然ネガティブなのだった。それほどまでに彼女に対するスティグマ(烙印)は、あまりにも深くわたしの中に刻まれてしまっていたのだ。
でもだからこそ、彼女の著作を読んだとき、長年の誤解は一気に解けた。
テレビで有名になり、嫌われ者の役割を押し付けられたことは、田嶋陽子という人の人生の中盤に、良くも悪くも突然起こったアクシデントのようなものだった。彼女は明晰な分析力を持つ研究好きの大学教授であり、恋愛経験によって生い立ちのトラウマを克服していった知性の人である。傷だらけになりながら、自分にひたすら正直に生きてきた人である。そんな嘘のない人を、嫌いになんかなれない。田嶋陽子さんをテレビで見るようになってから、実に20数年のタイムラグを経て、わたしは彼女のことが大好きになった。
- 1
- 3