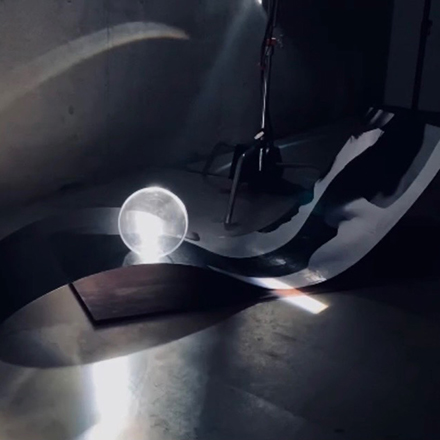美術作家で文筆家の肥髙茉実さんが、今月の特集テーマから浮かび上がった作品とともに思考のきっかけを届ける連載、「孤島にて」。境界を揺らぎながら作品をつくり言葉を綴る彼女が、いまここで生きながら個人として思うこと。第一回目はアイスランドの映画、ハーフシュテイン・グンナル・シーグルズソン監督の『隣の影』。
「まみちゃん魚座でしょ」。当時の恋人と悲惨な別れ方をして一人暮らしを始めた頃だ。占い狂の友人は、何の脈絡もなく突然私の星座を言い当てると、だってどこにも自分の居場所をつくりたがらないし、と続けた。次々と魚座の特徴を挙げる彼女を前に、私は執拗に沈黙していた。
新しい生活が始まってすぐ、私の身体は何かを思い出すように壊れた。手術は突然決まったが、いっぽう私たちの別れは突然やってきたものではなく、悲惨さも含めて、ずいぶん前から互いに十分予感してきたものだった。多くの人にとって、人間関係を築くうえで「共感」は欠かせないもののひとつだが、傷の付いた個人史や苦悩、あるいは正義を他者に向けて語るとき、その語り口には共感を求めて肥大化した被害者意識が頭角を現す。私の被害者意識は昨日より肥大化していないだろうか。無自覚にずるい語り口になることを恐れて、頼りない母を前に、頼もしい医者を前に、私はまた黙っていた。
間もなく巨大な台風が上陸し、私は家具も何も整いきらない新居でひとり、排水口の奥の水音に高潮を察したり、今にも窓が割れるかもしれない恐怖に震えた。体を壊してもなお忙しく過ごしていた私は、突如訪れた台風によって立ち止まることができ、ようやく、恋人との別れを経て自覚した被害者意識や、それが具体を持たずして暴力に転じていた可能性と向き合うことになったのだった。
「あなたを許せるか考えた アトリ、」
ふと映画『隣の影』(2017年)で描かれたアグネスの心の葛藤を思い出す。本作の舞台はアイスランド。ごく普通のマンション暮らしをするアトリとアグネスの夫婦生活は、ある日突然崩壊する。夫のアトリが元恋人とのセックスビデオを密かに鑑賞していたことが原因で、妻のアグネスに三行半を突きつけられてしまうのだ。もれなく侮蔑の眼差しを向けられたアトリは、郊外の住宅地に居を構える年老いた両親、インガとバルドウィンのもとに転がり込む。その実家にそびえ立つ大きな庭木は日差しを遮り、隣家のポーチに影を落としていた。やがてインガとバルドウィンは、その影にストレスを溜め込んだ隣人の夫婦から木の剪定を申し立てられる。この些細なクレームを皮切りに、両家は激しくいがみ合うようになり、インガたちの愛猫は突然姿を消す。1本の木を挟んで対立する2組の夫婦が越えてはいけない一線を越えてしまう戦慄の悲喜劇がアイロニカルに描かれた作品だ。
ハーフシュテイン・グンナル・シーグルズソン監督『隣の影』(YouTubeムービーで見る)
とめどない人間不信を増幅させた果てに、倫理がまったく通じなくなるインガと、その渦に呑み込まれていく両家の人々。本作は、まさしく誰かを攻撃することでしか自分を守るすべを知らない人間の弱くて愚かな本質を巧みに描写したサスペンスとなっている。インガのようにきわめて近視眼的な人間は、自分が理不尽を感じた場合に根拠もないまま対象をひどく憎み、相手をいくら傷つけても許されるという暴論に達してしまうことがある。迷うことなく常識外れの暴走へと突き進むインガは、たしかに狂気の隣人そのものだが、じつは誰しも狂気の隣人になりかねない。監督は本作について「僕なりの反戦映画」とコメントしている。
例えば19人もの障害者を殺害した相模原事件の植松聖被告は、事件当時と変わらず今も獄中から「僕の考え、どこか間違っていますか?」と私たちに問いかける(*1)。生活保護利用者や障害者に対する社会保障を充実させていき、100兆円もの借金を抱えることになった日本で、植松被告は国の未来を憂い、「意思疎通の取れない障害者は不幸しかつくらない」という身勝手な線引きによって命の選別はしかたないとする。
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」。そう明記された旧優生保護法は、恐ろしいことに1996年まで実際に存在した。命の選別をめぐっては、自民党議員・杉田水脈氏が発表した「LGBTは生産性がない」という旨の論考や(*2)、同じく自民党議員の白石正輝氏の「足立区が滅ぶ」発言が記憶に新しいところだ。少子高齢化が叫ばれるこの時代、より生産に励み、同時に生産しないものは産まれないように心がけるといった優生思想はあまりにも自然に社会に刷り込まれており、これを象徴する先述の3者は悪びれることなく、むしろ被害者意識やある種の正義を持って自身の考えを正当化しようとする。正義感と被害者意識は表裏一体であり、その意識の増幅は、いずれ被害者が加害者に転じる可能性を高めていくといえるだろう。
国家間・宗教間の紛争をはじめ、虐待やDVといった愛憎入り混じった暴力、差別偏見や貧困、検閲などの目には見えづらい構造的暴力、教育やマスコミの加担が大きい文化的暴力。誰の日常にも現実的な距離にあらゆる暴力が存在し、また映像やゲームなどにおいては過剰な爆破や戦闘、殺人の表現が多くの人に嗜好されるように、暴力のそばには快楽が横たわっていたりする。誰もがこの暴力の捻れや、(たとえ一度姿を消したとしても気を抜けばすぐにまた転がり込んでくるような)成仏しづらい性質と恐れながらも向き合い、ときにスルーしながら強く生きていかなければならない。かつてニーチェが言ったように、たしかに「怪物と戦う者は、その過程で自分自身も怪物になることのないように気をつけなくてはならない」のだ。
先日の台風は、結局列島を逸れて東京の街には薄暗い影を落としただけだった。その晩私は無防備にもスナックで酒をつくり、客と談笑しながら朝の訪れを待ち、帰りのタクシーの中では、あの巨大な台風が来たときのことを思い返していた。あれから時間が経ち、様々なかたちの優しさに出会い、ずいぶんと心の鎧は剥がれたようだった。誰かと親しくなるたびに、私は自分の言葉が彼彼女に与えるかもしれない影響を恐れつつ、それでもなおぶつかりあえば、私のためにあなたに変わってほしい、あなたの居場所は私であってほしい、という自己中心的で危険な感情がときどき顔を出す。すっかり雨が止んだことを確認し、台風には中心があり、私は人生においてたびたび台風に巻き込まれることはあっても、私自身が誰かの世界の中心になることはなく、なろうとするべきでもないことに気付き直す。一見すると幸せな日常にも、カジュアルで気付きづらい暴力が蔓延り、私たちはいつの時代もその複雑な違和感を他者に伝えることすらスムーズにいかない。「暴力」の反対を、平等のもと協力や対話の文化が活発に行われる状態だとして、私たちはいかに許し合いながら、その美しさを守り続けられるだろうか。
「あなたを許せるか考えた アトリ、
あなたを許すわ
私のことも許してほしい
私たちは間違いばかり
ここ数週間はお互いバカだった
でも まだ正しいことができる」
*1──「植松聖被告が面会室で劇高した瞬間」(『創』2018年11月号)および雨宮処凛編著『この国の不寛容の果てに 相模原事件と私たちの時代』
*2──杉田水脈「LGBT支援の度が過ぎる」(『新潮45』8月号)