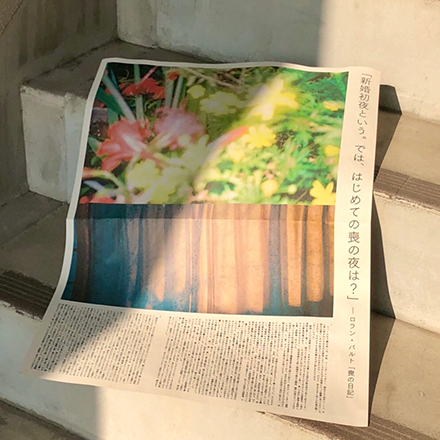「いつも一人の女の子のことを考える。
たった一人、どこで、いつ、どんなことを考えているのか。
笑っているの? 泣いているの? 怒っているの?
一人の女の子のスリルとサスペンス。
一人の女の子の自由とタフさ。
いつだって物語のようにいかないけど、
テキパキ働いて、
ウキャウキャ遊んで暮らして、
憧れは憧れのまま、でもいつか追い越すよ。
そんな彼女たちの、
別の存在でも
同じような
私たち。
こんにちは、Girlfriend。」
世界で感じる違和感をそのままにしないで、何かを表現している人や作品は私に勇気を与えてくれる。もちろん、これを読んでいる人たちにだって勇気を与えてくれるだろう。
これはライター・吉野舞が公募によってShe isの「Girlfriend」になった女性を短いテキストだけではつまめないような「存在」まで知りたいために、好奇心のまま会いに行ってみるフォト・ドキュメンタリー。
見つけたものはひとりひとりの決して逃せない輝きと同時代に生きる女の子が感じとる日常のお話。
ヴァージニア・ウルフの研究をする大学院生、楠田ひかりさんと待ち合わせ
2020年3月、第2回目のゲスト・楠田ひかりさんと待ち合わせ。「あなたのことについて聞かせてください!」と、取材のお願いをしてみると思ったよりはやく彼女と会えることなった。誰かと会うのは楽しい。でも初めての人と会うのはもっと楽しい。人を待っている時間、街は急に親しみがなくなり、よそよそしくなる。

吉野:はじめまして! 楠田ひかりさん。
楠田:はじめまして。今日はよろしくお願いします。あまり人前で話すのは得意ではないのですが……。楠田ひかりと申します。1995年生まれで、出身は兵庫県の神戸市です。今は大学院で、イギリスの作家、ヴァージニア・ウルフや、家族や生殖をテーマにした小説、フェミニズムに関心をもって研究しています。
吉野:あれっ? 楠田さん、そのトップス「mame」!?
楠田:そう! あ、吉野さんが今日着ているワンピースも「mame」だ(笑)。ちなみにこのジャケットは母が昔着ていたものです。
吉野:えー素敵! 同じブランドの服着てるね。今日は大事な取材だし、気合い入れたくてこれを着てきました。前回の麦島さんのときと同じで、楠田さんが「VOICE」で書いた記事を読んで、考えていることや存在にすぐにビビッときて「会ってみたい!」と興味をもちました。
楠田:私も前回の吉野さんの記事(Vol.1麦島汐美さんに会いに行く)を読みました。会話の流れのなかで自然に本や映画の話が出てきて、目の前の生活を日々生きることと、それよりも少し大きな範囲の出来事について考えることは地続きなのだとあらためて思えて、生きよう……となりました。公募の文章についてもそのように言っていただきありがとうございます。She isのおかげで、自分ひとりの発信力じゃ読んでもらえなかったはずの人にも届いて、こうしてお会いできることになってとても嬉しいです。
「母の立場や境遇を考え直してみると、私の母だけの個人的な問題ではないと気づいて、女性が置かれてきた状況に目を向けざるをえなくなった」
吉野:楠田さんの文章を読んで、女性のあり方を問い直すときってまずは自分の母親や身近な女性のことを考えるところから始まっていくんだな、と感じました。それに母について考えることは、自然と人間同士の関係をとらえ直すことでもあるんだなと。
楠田:そうですね。母の立場や境遇を考え直してみると、私の母だけの個人的な問題ではないと気づいて、女性が置かれてきた状況に目を向けざるをえなくなりました。
吉野:あれは楠田さんの体験談の話? それともノンフィクションなの?
楠田:書き溜めていた日記をもとに新たに構成しなおしたものです。といいつつも、とくに幼少期、いつ何が起こったかについては覚えていないことも多いから、実際の経験とは違いがあると思う。だから記憶の再構成というか、一種のフィクションというかたちで書きました。

吉野:へえ……。そういえば、公募に応募したきっかけは?
楠田:以前、ワークショップで文章を書く機会があって、そこで短いフィクションを書いたんです。それは論文や批評以外の文章を初めて人に読んでもらう経験で。すごく緊張したんだけど、読んでくれた人たちが反応をくれて嬉しかった。だから、これからも書き続けて何かかたちにしたいなとは思っていて。そんななか、2019年の春に川上未映子さんの『夏物語』を読んで、「ここには私のことが書かれている!」って衝撃を受けた。それから少しして、She isの2019年5・6月の特集のテーマ「ぞくぞく家族」の公募があって、これはぜったい今書かないといけないと思って応募しました。
吉野:「She is」にのったことで周りから反響はありましたか?
楠田:大学院の先輩が、「今まで、ジェンダー的な問いは自分に関係ないことだと思っていたけれど、記事を読んで一気にその問いが自分の問題でもあるように感じられた」って感想をくれて。私自身のすごく個人的な経験が、他の誰かにとっても自分自身のことだと思えるような経験になったことがすごく嬉しくて印象に残っています。
吉野:楠田さんは日頃から積極的に書いたものを人前で発表しているんだね。
楠田:今私がいる大学院という場所は、周りの人たちがすごく話を聞いてくれて、反応をくれるというのが自然におこなわれるところで。だから最近は、聞いてもらう環境があることで安心して文章を書かなくなってきているかも……。だけどそこで解決して終わりじゃなくて、違和感や不安をちゃんと残るかたちで言語化しないといけないなと思う。たとえそれを発信しなかったとしても、あとで見返したときに、このとき私はこういうことを考えていたんだなってわかるし。そういう意味で「She is」で書いている人のように、日頃からきちんと言葉を積み重ねていく行為は大事だなって痛感する。「She is」の公募は誰でも応募できて、私のような無名の人が自分の経験を書いた記事が載ることもある。そんな個人的なことが、遠く離れたところで似たような思いをもっている人に届くのはすごく大きなよろこびでした。実際、「母に手紙を書こうと思いました」という感想をSNSを通じて送ってくださった方もいました。
吉野:うんうん。私も周りにちゃんと話を聞いてくれる人がいてくれるからこそ、自分は考えていることや、日々感じたことを綴って、それを公にし、多くの人たちと考えを共有していきたいなと思うの。それはわたしたちができるコミュニケーション方法のひとつだから。
楠田:とっても分かる。
「『家事労働に賃金を』キャンペーンを知ってから、母親ひとりにいかに家事や仕事などのすべてを担わせていたのかに気づいた」
吉野:質問したいこともいくつかあって。どこから聞いていこう。じゃあ、楠田さんはプロフィールに、「イギリスの作家、ヴァージニア・ウルフについて研究しています。とくに、フェミニズム、後期モダニズム、家族・生殖がテーマの文学に関心があります」って書いていたのが気になって。まず研究している作家「ヴァージニア・ウルフ」に興味を持ったきっかけって?
楠田:まずウルフの説明をすると、彼女は第一次、第二次世界大戦のあいだに主に執筆していたイギリスの作家です。よく知られている作品の一つは、『自分ひとりの部屋』(1929年)。この本は、イギリスで男女平等の参政権が認められたばかりの1928年に、ケンブリッジ大学の女子学生へ向けた〈女性とフィクション〉という講演をもとに執筆されています。「女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分ひとりの部屋を持たねばならない」という有名な一節があるんだけど、それは、女性が性別によって押し付けられることなく自由に考えて意見を持つためには、誰かに経済的に頼らずに生きていけるだけのお金や環境が必要だということ。今でも女性と男性の賃金の格差は解決していないし、ウルフが当時のことを「執拗なくらい性別を意識させられる時代」と言っていることも、そのまま現在に当てはまる。今に通じている問題を提示している本です。
私が最初にウルフに興味をもったきっかけは、学部3年生の冬に、死後出版されたウルフの日記、『ある作家の日記』(1953年)を読んで、現在のなかに急に別の時間が現れるような文体に衝撃を受けて。それまでほとんど小説を読んだことはなかったし、ましてや文学研究をするつもりもなかったんだけど、一気にウルフにのめり込んでいった。

吉野:いきなり心をわしづかみにされたんだね。
楠田:最初は小説の時間描写や文体に興味があったんだけれど、大学院の授業で、ウルフの『三ギニー』(1938年)というエッセイに影響を受けた「家事労働に賃金を」キャンペーン(※1970年代にセルマ・ジェームズやマリアローザ・ダラ・コスタらがおこなった運動)を知ってから、母親ひとりにいかに家事や仕事などのすべてを担わせていたのかに気づいた。そこから、性別を理由にある役割を担わされること、不当な扱いを受けることにとても敏感になりはじめて。「今思えばあれはおかしかったよね?」という出来事もたくさん思い出してきちゃって。モダニスト作家としてのウルフだけでなく、フェミニストとしてのウルフのことを勉強しはじめました。もちろん、その二つはすごく結びついているんだけど。
「同じ世代としてひとくくりにしても、そのなかでグラデーションがあるし、語られていないこともたくさんあると思う」
吉野:現代の日本では女性に参政権はあるし、もちろんウルフがいた頃と状況は違うけど、1世紀前の作家が今も多くの人に読まれている理由は、現代でも解決できていない問いが詰まっているからっていうのもあるからだよね。私、ウルフの本を読む前に「ウルフ=フェミニスト」というイメージだけが勝手にあって。そもそも、「フェミニズム」って言葉がまるで女性が男性を批判するときに使う武器のように使われる時があると思うんだけれど、それに違和感を感じてしまうときがあるんだよね。「フェミニズム」って決して女性だけのための言葉ではなく、もっと広い意味をもった言葉じゃないかなと思っていて。
楠田:私も、女性だけのための言葉ではないと思う。もちろん、女性が性差別を受けてきたし今も受けていることはまぎれもない事実なので、フェミニズムは女性のための運動、考え方だというのが出発点だと思います。そのうえで、女性が性別を理由に不当な扱いを受けている現状では、すべての人がなんらかのかたちで、こう振る舞うべきという性規範を押し付けられたり、性別を理由に差別されたりする可能性があるということだよね。だから、女性差別をなくすことは、ひいては性別を理由にした差別をなくすことにつながっている。
それに、フェミニズムが解決しようとしている問題は他の問題とも複雑に関わり合っていて。性差別のように、誰かをより弱い立場に置いて支配しようという考え方は、特定の民族に対する差別や、環境問題、労働者の搾取にもつながっているよね。フェミニズムの目的は、女性が、今この社会で不当に力を得ている一部の男性と同じように、支配する力を得ることじゃない。差別が起こる構造自体を変えていくことが目的です。だから、そういった構造を支えているものは何なのか、領域を越えて考えていくことが必要だと思っています。
吉野:なるほど。最近、#MeToo運動があったり、フェミニズムに関連した多くの本が出版されているけど、活動や本が注目される前からそのことについて発言する人はいたでしょう。現代のフェミニズムの活動は第四波と言われていて、今に至るまで色んな活動が行われてきた。例えば、祖母と私とで「女性の平等」をテーマに話すと、世代によって主題の違いがあるんだなって思うんだけど、昔と今で性差別からの解放などについての考え方に違いが生まれることについてはどう思いますか?

楠田:ある世代を「犠牲者」として語るのは違うというのは、ほんとにそう思う。たとえば、今は「女性は家事労働をして、男性は賃労働をする」ということをすべての人の前提として考えるべきではないと思うけど、だからといって、祖母や母の世代の人たちが専業主婦として生きてきたことを否定するのは違う。いうまでもなく、今その生き方をしている人を否定するのもぜったいに違う。同じ世代としてひとくくりにしても、そのなかでグラデーションがあるし、語られていないこともたくさんあると思う。もちろん、どんな状況においても他人の人生をジャッジすることはぜったいにすべきではなくて。
だけど、自分の生き方について話すとき、どうしても、単に「私はこう思う」という考え方の違いとして結論づけられないこともあって、すごく難しく感じる。以前祖母に、私は自分自身が結婚して子供を産むことに迷いがあるということを話したとき、「それでも子どもを産むことはすばらしいこと」というようなことを言われたんだよね。それはすぐにはうなずけることではないけれど、だからといって、それを否定することはもしかしたら祖母自身を否定することになってしまうのではないかと思って。もちろん私が自分の思うように生きることが祖母の生き方を否定することにはつながらないとはわかっているんだけれど。
たしかに、祖母は子供を産んだし、私は子どもを産むかもしれない身体を持っているという点では共通しているんだけど、別の選択をしたとしてももちろん互いの選択は尊重されるべきで。でもそこで、「女性」としての選択というふうに主語が大きくなりすぎると、色んな差異が見えづらくなってしまう。だから、「女性」と言われるとき、そこで想定されているのはどんな人なんだろう? ということを慎重に考えるようにしています。もちろん、「女性」と掲げることによってつながれるということはあるよね。
吉野:このメディア「She is」も、「女性」と掲げてつながれるそのひとつで。
楠田:そうだね。以前、「She is」という名前について、「どうしてTheyじゃないんですか?」って聞かれたことがあったんだって。そこで、編集部の人が「あきらかに日本でまだ女性差別がある中、まず自分自身が当事者として語り始められるSheのことから考えていって、その先にTheyの話ができるようになっていけばいい。最初はそこから考え始めていかないと」って言っていてすごくうなずいた。
- 1
- 2