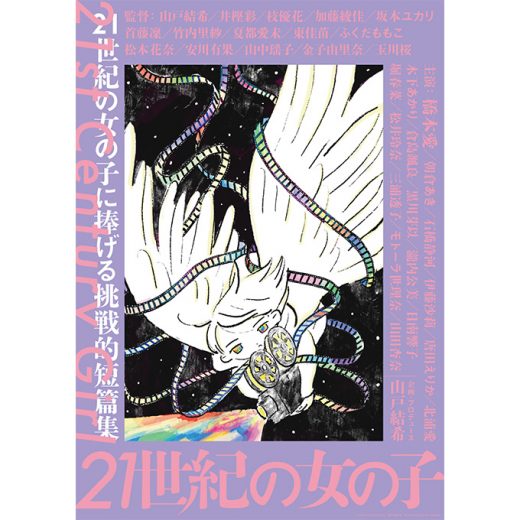「女の子」「少女」「女性らしさ」「女性の生き方」……。言葉というのは、ときに意味が独り歩きし、本来それが指し示していた対象から遠く離れてしまうことがあります。そんな上辺の言葉によって語られたとき、言葉は「こうあるべき」という呪いに変わり、語られたものたちの行動や心を縛ってしまうことがある。この社会には、そういう呪縛のような共通認識や価値観というのが、まだまだ存在しているのだと思います。
そのような状況において、今年2月に公開される映画『21世紀の女の子』は、ひとりひとりの個人を主語に新しい物語を語ろうとしている挑戦的な短編集。本映画の企画・プロデュースを務めた映画監督の山戸結希監督が、15人の監督を集め、1本のオムニバス作品を生みました。そのなかで、松本花奈監督作『愛はどこにも消えない』で主演したのが俳優・橋本愛さんです。
『東京国際映画祭』の舞台挨拶で「言葉にならない涙が出た」と話した橋本さん。まなざす監督/まなざされる俳優という立場が時に逆転し、時にその視線が交差し、『21世紀の女の子』という作品でどんな景色を二人は共に発見したのでしょうか。いつだって理想の生き方を思い描こうともがく永遠の女の子である私たちと、そしてその理想が形になった世界に生きる未来の女の子たちへ向けて。二人が言葉を紡いだ数十分をお届けします。
「女の子」という存在を、取り戻さなければいけない。(山戸)
ー『21世紀の女の子』というプロジェクトでは、いままで主な語り手ではなかった「女の子」たちについての映画を集め、新しい話法によって、理想の世界を描き直そうとする気配を感じました。
山戸:世の中に存在するたくさんの言葉において──女性を指して使われるたくさんの単語が、もはや女性のための言葉ではない事態が生じえます。まなざす側がつくりあげた象徴に過ぎず、その言葉が本来的に名指すべきだった存在さえも、決して望まれない文脈に乗って語られてしまうことがあります。一人の女性が生まれたとき、自我が芽生えて、最初に巡り合うそんな言葉の一つが、「女の子」であると言えるかもしれません。だからこそ、「女の子」という言葉が内包する存在を、あるいはその言葉が超えた存在を、取り戻さなければいけない、と考えました。
この世界における主語を、自分自身の身体に設定したとき、「どんな物語を生きたいのか」ということを、自ら考えるきっかけになるものをつくりたい。どんなに同じモチーフを取り扱っても、どこまでも独立した、ひとりひとりの存在を取り戻したいというのが『21世紀の女の子』の大きなテーマとしてありました。
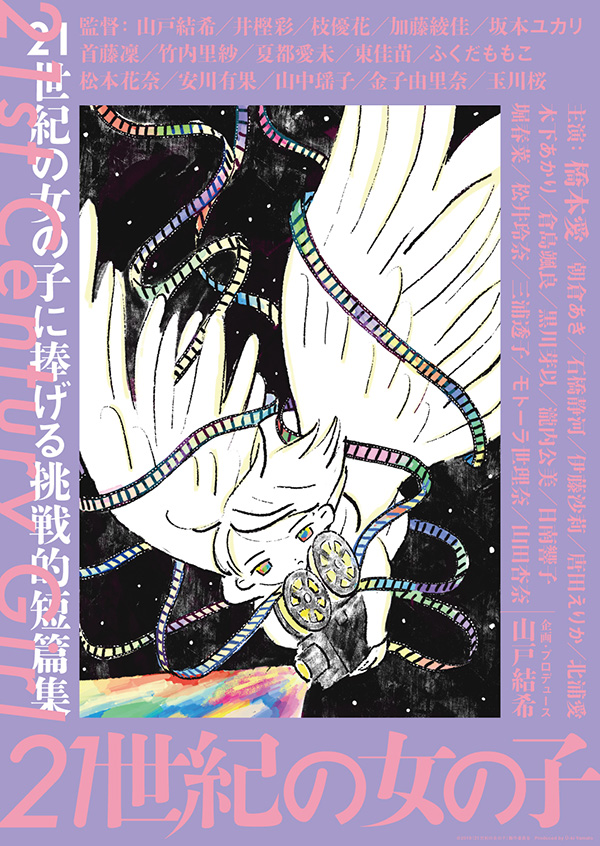
『21世紀の女の子』メインビジュアル(オフィシャルサイトを見る)
ー山戸さんと橋本さんは、職業的な役割で言うと「まなざす側」の監督と、「まなざされる側」の俳優です。それぞれこの映画を通して、なにを見て、なにを見せようとしたのか、お話しいただけますか?
山戸:どのようにまなざし、まなざされるかということを含め、これまでのやり方ではない「語り方」が必要だと考えています。作品をどう撮るか以前に、俳優さんのキャスティングの時点から、明瞭に新しく物語ろうとする監督の皆さんの意志を感じました。

『21世紀の女の子』チラシビジュアル
山戸:橋本さんが出演された『愛はどこにも消えない』における、松本花奈監督にとって橋本さんの存在はずっと撮りたいと願った方で、橋本さんを映し出すそのまなざしに、大きな愛情を感じました。ですが、メイキングを拝見したところ、愛情的なまなざしだけではなく、橋本さんが松本監督のまなざしを受け止める愛情も同時に感じたんです。おふたりがそうした双方向の関係性にあることこそが素晴らしいことだと感じました。そこにはおそらく「ただ見られるだけでは終わらせない」という、橋本さんの強い意志もあったのではないでしょうか。
「見られる」は、「見る」ことの楽しさにかなわない。その豊かさが勝っているから、この仕事をずっと続けられる。(橋本)
ー「見られる」というのは、見るほうの見方によっては、ともすれば「奪われる」ことにもなってしまう行為ですよね。また、『21世紀の女の子』は詩的な作品も多く、俳優がまず言葉を本気で受け止め、そのうえでスクリーンの向こう側にいる人々から見られることに対して強い覚悟を持っていないと、本質的なところが伝わらない可能性もあったと感じます。俳優という生き方において、「見られる」ことを引き受けていらっしゃる橋本さんは、どのような感情で映画に向き合われているのでしょう。
橋本:役者という世界に入ったのが12、3歳だったので、もうすぐ人生の半分をこの仕事に費やしたことになります。見られることに対する恐怖やトラウマもかつてありましたが、まなざされることはいつの間にか日常化していて。でも、私は「見られている」と同時に、役を演じることを通して「見る」こともおこなっているんです。そして私にとって、「見られる」ことそのものや、それによって起こり得る恐怖というのは、「見る」ことの楽しさにかなわない。その豊かさが勝っているから、この仕事をずっと続けられるのだと思います。

橋本愛さん
ー見られていると同時に、役を演じることを通して、なにを見ているのですか?
橋本:自分自身の心理や思想を知りたいと思うこともあります。でも私のいちばん強い欲望は、役の女の子が見る景色を自分も見てみたいということ。『愛はどこにも消えない』で演じた女の子は、私が知らない種類の「好き」という感情を持った女の子でした。深く突き詰めず、表層的な部分だけで捉えていたら、彼女の持っている感情を自分にひきつけて理解することはできなかったと思います。でも、演じながら考え続けているうちにハッと腑に落ちる瞬間があるんです。「彼女はここにいるんだ!」という境地にたどり着き、私と役と監督が同じ景色を見たと信じられる瞬間がいちばん快感です。

『愛はどこにも消えない』劇中写真
橋本:取材をお受けすると必ず監督と同年代であることに関して質問を受けますが、松本監督の年齢を何度聞いても覚えられなくて(笑)。それくらい私にとって同年代という共通項が意味するものは重要ではないし、ひとりの監督としてしか松本監督を見ていないのだと思います。それこそ男性だろうと、女性だろうと関係ありません。
山戸監督がおっしゃってくださった親密な関係性を築けているのだとしたら、それは私が松本監督のことを好きだからだと思います。いいなと思ったのは、モノローグの収録時に、当日までずっと原稿を書き直されていて。鮮度の高さや生々しさ、松本監督の「今」の連続を私が引き受けるような心地がして、そこに惚れました。
山戸:監督がまなざす側で俳優さんがまなざされる側というフレーミングが採用されますが、橋本さんのお話をうかがって、まさに俳優さんもまなざす主体であるのだと、電撃が走りますね。たしかに、撮っている俳優さんから、カメラを通して逆流的に、「あなたの内側に、演じさせる力が、演じるべき物語が、どれだけありますか?」と、ずっと問いかけられている心地になるんです。監督としての姿勢ではなくて、もっと個人的な内なるものを見つめられている。映画を撮ることにおいて、見る/見られるというのは、カメラという可逆装置の存在によって、顛倒的な状態にあると言えるかもしれませんね。
- 1
- 3