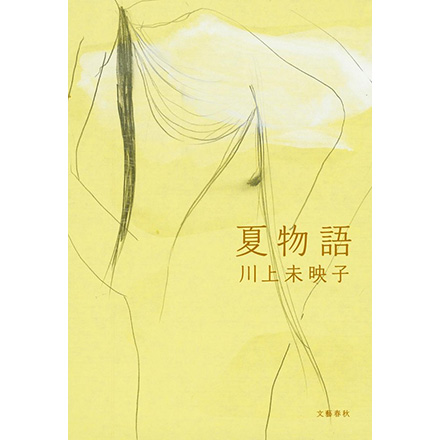「フィクションをつくることが、どんどん祈りの形態に近づいてきた」。これは以前、小説家の川上未映子さんが語った言葉。人は自分が選んだ人生以外を生きることはできず、そして選んだことを、選ばなかったことにすることはできません。
川上未映子さんの新作小説『夏物語』の後編のインタビューでは、前編にひき続き、これまでになかった家族のかたちから、いまだに可視化されていない差別が横行するいびつな世界で生きてしまっているわたしたちのよりよい生き延び方、そして小説にたくした祈りについて、お話をうかがいました。
さまざまなシステムや社会のしがらみがひとつひとつ解きほぐされて、個人の選択が尊重され、自由な世の中になりますように。そして同時に、わたしたちが個人になったときに、孤独になってしまう人が増えることのないように。『夏物語』に答えはないけれど、そもそも正解なんてない人生の、あなたに響きあう拠り所なら、きっとあると思うのです。
【前編】川上未映子が話す。わたしたちはなぜ子どもを生むのか、生まないのか
『夏物語』では、現時点でいちばん困難な家族の編成をつくりたいなと思いました。
―『夏物語』には、家族のありかたというものも色濃く描かれていますよね。主要な登場人物が、『乳と卵』にも登場する夏子、夏子の姉・巻子、その娘の緑子という家族だということもありますし、夏子が「自分の子どもに会ってみたい」と思ったときに、おのずと自身の「家族像」とも向き合わざるをえなくなっていって。
川上:そうですね。家庭環境っていうのは、代々再生産されていく部分も大きいから、そういうところもこの物語にしっかり書けたらいいなと思って。貧乏ってこうやって連鎖していくんだよな、とか、そういう部分も。
主人公の夏子はセックスがほとんどできないし、パートナーもいない38歳の女性で。だけど自分の子どもには会ってみたい。そういう自分が、どうしたら子どもを生めるのだろう? そもそも、まるで茄子の煮浸しのように疲れはてている自分から、新しい生命なんて生みだせるのだろうか……? なんて不安もいだきながら、精子バンクについて調べ始めるんですよね。

川上未映子さん
―夏子の友人である小説家でシングルマザーの遊佐は、「女が女だけで生んで育てることもできるんだ」ということを言っていて。最終的にセックスが好きではなかった夏子は、卵子と精子が結合しないと子どもがつくれない仕組みのなかで、自分の気持ちを尊重するぎりぎりの方法で子どもを生みました。
それは「どうして人はひとりでは、子どもに会えないのか?」という、男女がつがいにならないと成立しない出産や家族という概念への切実な抵抗になっていましたよね。
川上:そうですね。育てるという意味では、シングルマザーやシングルファザーとして多くの人がひとりで子育てをしているわけで。出産という場面においても、1回しか会ったことがない人の子どもを生んでいる人がたくさんいるなかで、精子提供を受けての妊娠は、それとはどう違うのか? 自分のやろうとしてることって本当のところはどうなのか? 夏子は逡巡し倒しますが、その行ったり来たりをぜひ読者にも一緒に辿ってほしいと思いました。
精子提供にも、いくつかの方法があります。海外から輸送されてくる提供主のデータがしっかり管理された冷凍精子を使うのか、インターネットで知りあった人の精子を喫茶店で受け取って注入するようなDIY的な方法を選ぶのか……など、いろいろな方法が存在するのだけれど、『夏物語』では夏子の最終的な家族像を描くときに、現時点でいちばん困難な家族の編成をつくりたいなと思いました。
―いちばん困難な家族の編成。
川上:うん。どんな家族もそれぞれの困難はあるけれど、たとえばいまは、女性同士のコミュニティをつくって、血が繋がっている人も繋がっていない人も同じ場所を借りて生きていくような、そんなかたちも小説では多く描かれていると思うのですが、夏子と彼女の人生観を大きく変える逢沢潤の関係というのは、いままでなかった組み合わせなのではないかな。
―たしかに夏子の性的な特徴や、逢沢のバックボーンは、これまでになかった男女の繋がりですよね。
川上:生物的な父親であっても、たとえば逢沢のように離れて暮らしている場合、なにをどれぐらいすればほんとうに父親になれるのかについては、まだ明確な答えがありません。そして夏子はセックスが好きではないわけだから、いわゆる「夫婦」の間柄であっても、子どもをつくる以外のセックスはおこなわない。そういう関係において、はたして彼ら/彼女らはどんな「家族」になりえるんだろう? っていう問いが物語の先にも続いているような気がします。
家族に安定したかたちなどなくて、常にメンテナンスが必要。
―夏子は、これまで「あたりまえ」とされてきたこととは、ことごとくちがった方法をとりながら、家族をつくろうとしていますよね。
川上:「家族」はそこまで丁々発止で常に問い詰めあったりしないでいられる、ゆるい共同体としての最終的なシェルターのようなものだから大事にしなければ! っていう考え方が世の中にはありますよね。でもその心地よさって、これまで誰かが犠牲になって、まわってきたものなんじゃないかなって。
―犠牲。
川上:もちろんさまざまなケースがあるとは思いますが、でもはっきり言って、多くの場合、犠牲になってきたのは「母親」でしょう? 女性でもない、人間でもない、家事も育児もパートも介護も、なんでもやらせてよい「母親」とか「嫁」として、みんなが使い倒してきたわけです。たとえば新築を建てたとして、他の家族には部屋があるのに、お母さんだけ居間や台所が居場所みたいになっていたりね。そういうことが、これまで可視化されてこなかったわけです。
だから、ゆるっと、その使い倒してきた側が「家族はいいよ~」とか言って、そのままで家族という自治が守られると思っている人がいるとしたら、それはほんとうに勘弁してほしい、って思います。

―『夏物語』にでてきた、ある種の家庭環境においては女性が「まんこつき労働力」になっているという言葉のインパクトが強烈でした。
川上:いま「家族」に関して、さまざまな角度から考えるタイミングがきているように感じますが、家族に安定したかたちなどなくて、常にメンテナンスが必要なものなんです。
―ああ、メンテナンス……。家族というのは、変化する人と人が一緒に生きることだとしたら、関係を維持したりよくするために、メンテナンスはすごく重要ですね。
川上:「血が繋がってない家族もいいよね」といった提案も、もちろんいいと思います。でもそういう形を語る前に、血が繋がっていようが、いなかろうが、目の前にいる人を、「家具扱い」するのをやめることからはじめようよ、って。
―家具?
川上:家具って、ずっとあるし、意見を言わないじゃないですか。人を家具扱いするような態度は、なにも昔の話ではなくって、いまでも存在するんです。ママ友の話を聞いていても、Twitterを見ていても、小説が裸足で逃げ出すぐらいのモラハラが家族間であたりまえに起きているから。
家族というものの、多様で複雑な形態を考えると同時に、目の前の人の「しんどさ」とかを想像できるかが、ほんとうに大切。いわゆるジェンダーロールに飲み込まれて、可視化されてこなかった個人の感情に気づけていないことが圧倒的に多いと思います。まずはそういう一対一のコミュニケーションに真摯に取り組むべきで、「家族の理想形」を言葉で語るのは、その次じゃないかな。
- 1
- 3