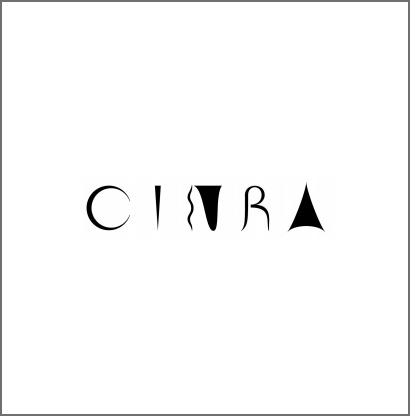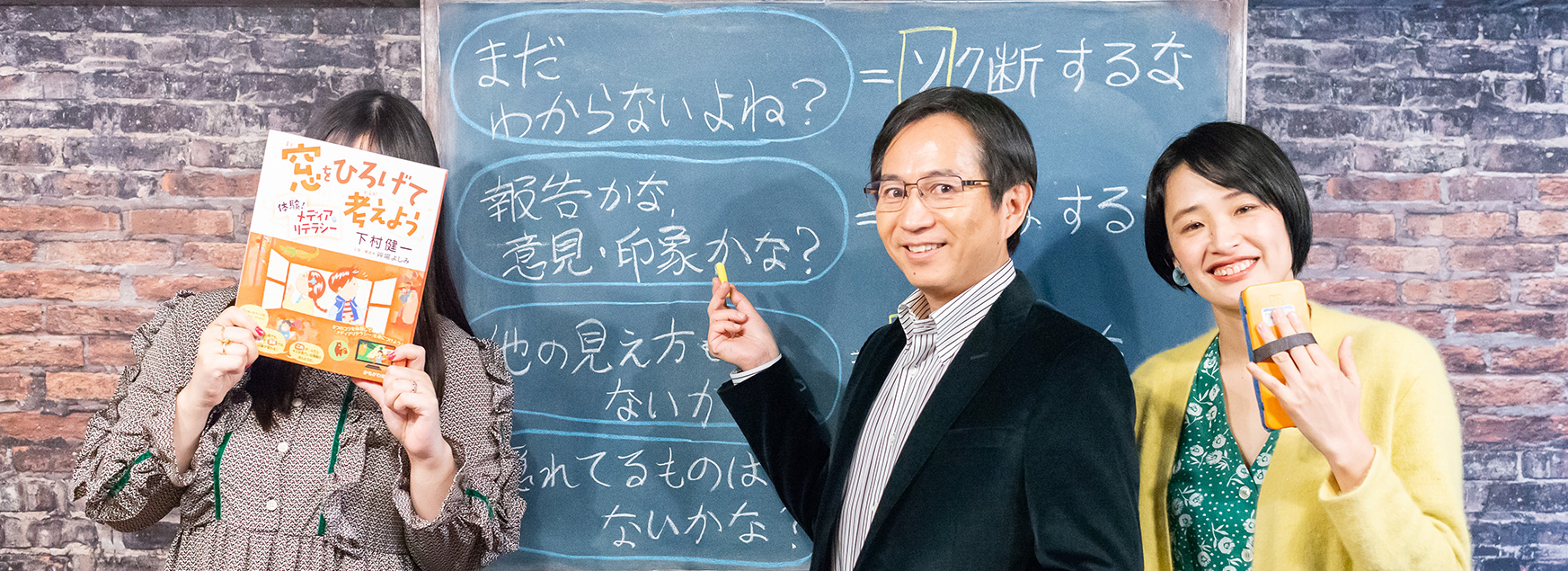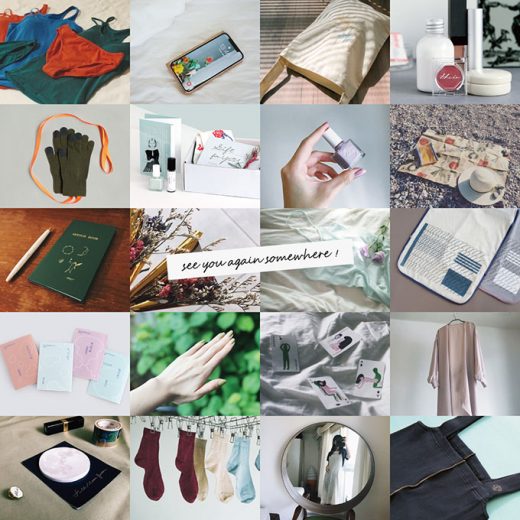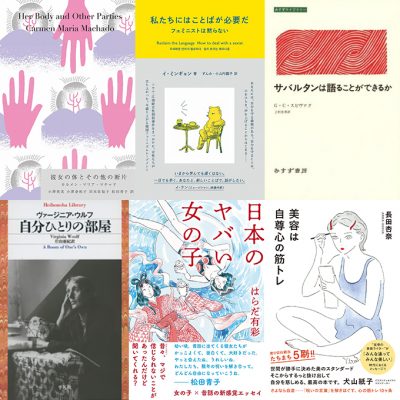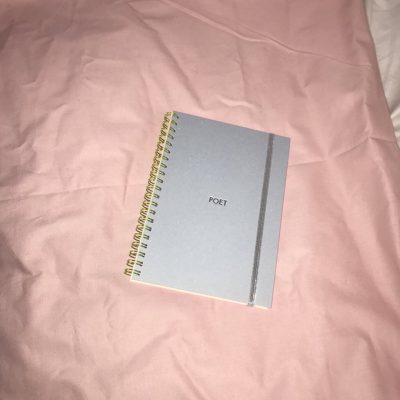何を信じていいかわからない!情報が溢れる時代の、メディアとの付き合い方
無いとは言えない偏向報道や情報操作、不安や対立を煽るデマにフェイクニュース……。本当かどうかいちいち調べる余裕はないけれど、せめてざっくり見極めて振り回されずに暮らしたい。政治1年生としてニュースを追うようになった長田&かんが、情報のエキスパートに取材。「新聞を読みなさい」では済まないネット時代に改めて身に付けたい、「使える」メディアリテラシーについて教えてもらいました。
※この鼎談は2019年12月に収録し、記事化にあたり、コロナ対応等について加筆修正を行いました。
<前回までのおさらいはこちら>
政治音痴のための7.21参院選 長田杏奈&かん(劇団雌猫)が緊急取材
政治1年生のための消費税。長田杏奈&かん(劇団雌猫)が経済学者に取材
政治1年生のための社会運動。長田杏奈&かん(劇団雌猫)が社会学者に取材
教えてくれるのは
「小学生にも経営者にも、ほとんど同じ授業をします」
下村健一(しもむら けんいち)
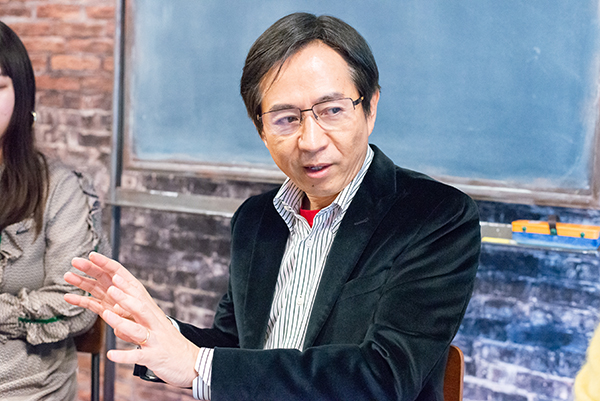
下村健一
1960年、東京都生まれ。令和メディア研究所主宰。東京大学法学部卒業後、TBS入社。報道アナウンサー、現場リポーター、企画ディレクターとして活躍。2000年以降、フリーとして取材キャスターを続ける一方、市民グループや学生、子どもたちのメディア制作を支援する「市民メディア・アドバイザー」として活動。2010年秋から約2年半、内閣広報室の中枢で首相官邸(民主党政権も自民党政権も)の情報発信を担当。東京大学客員助教授、慶應義塾大学特別招聘教授などを経て、現在は白鴎大学特任教授。小学教科書(国語5年/光村図書)の執筆から経営者研修まで、幅広い年代のメディア・情報教育に携わる。ネットメディアの創造性&信頼確立を目指して40団体以上が加盟する「インターネットメディア協会」(JIMA)に、設立理事として参画し、メディアリテラシー部門を担う。著書に『窓をひろげて考えよう』(かもがわ出版)、『10代からの情報キャッチボール入門――使えるメディア・リテラシー』(岩波書店)、『マスコミは何を伝えないか』(岩波書店)ほか。
教わったのは
「JCメディアリテラシー確立委員会公式Twitterが肝心な時に沈黙してて困惑」
かん
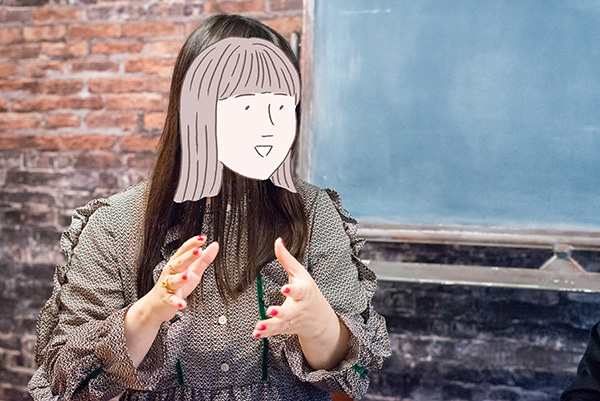
かん
1989年、兵庫県生まれ。書籍『浪費図鑑』等を制作するオタク女子4人組「劇団雌猫」メンバー。何が正しい情報か分からないときは、一回スマホを閉じて、みんなの議論が活性化するのを待つ。新刊はコミック『だから私はメイクする』(祥伝社)、イガリシノブと共同監修の『化粧劇場』(池田書店)。K-POPアイドルSEVENTEENのジョシュアと宝塚歌劇団の芹香斗亜を応援中。
「好きなラジオ番組は、荻上チキ・Session-22」
長田杏奈(おさだ あんな)

長田杏奈
1977年、神奈川県生まれ。ライター。テロップや口調で煽るテレビが苦手で、ニュースはネットやラジオでチェック。新聞は電子版派。センセーショナルな見出しやコメント欄、ニュースの並び順がワイドショーっぽいサイトは避けて通る派。著書に『美容は自尊心の筋トレ』(Pヴァイン)、『あなたは美しい。その証拠を今からぼくたちが見せよう。』(大和書房/6月発売)。『エトセトラ VOL.3 特集: 私の 私による 私のための身体』(エトセトラブックス/5月18日発売)責任編集。
<もくじ>
p1. フェイクニュースってどう見分けるの?
P2. 最低限必要なメディアリテラシーを教えて
P3. 情報をバランスよく取り入れる方法は?
P4. どこで情報収集すればいい?
P5. 政治について発信すると攻撃されそうで怖い
P6. ファイナルアンサーが決められない!
P7. みんながメディアリテラシーを身に付けるとどんな世界になる?
P8. 【おまけ】楽しくメディアリテラシーを学ぶエンタメ作品
フェイクニュースってどう見分けるの?
かん:「政治1年生」としてこれまで選挙、消費税、社会運動と学んできました。
あんな:いままでスルーしていたニュースが、一気に「知ってる話題の続報」になって面白いよね。
かん:でも、少し学んだからこそ壁にぶち当たっていて……。それが、「同じ情報について全く真逆の見方をしている人たちがいて、何を信じたらいいのかわからない」ということ。
あんな:ニュース媒体によって意見が真逆だったり、ピックアップの角度によって全然ちがう話に見えたりするもんね。「提灯記事」も紛れ混んでいるから気が抜けないし。最近だとどんなニュースを見たときに迷った?
かん:うーん、大きなことだと原発賛成/反対かな~。原発事故なんかを見て、危ないし絶対反対! って思っていたけど、一方で脱原発をすると火力発電の比重が大きくなってグレタ(・トゥーンベリ)さんなんかが訴えている温暖化を加速させかねないって聞いて。
あんな:せっかくニュースへの興味が深まっても、情報が多すぎて迷子になっちゃう。何を羅針盤に情報を見極めればいいのか、メディアリテラシーの専門家、下村健一先生にたっぷり教えてもらうとしよう。そもそも、メディアリテラシーってどうして必要なんでしょう?
しもむら:デタラメや勘違いの情報は大昔からあったけど、今はそれがケタ違いに出回りやすくなってしまいました。こうなると、フェイクニュースなどに感染しないための、ワクチンのようなものが必要ですよね。フェイクニュースって、一見すごくリアルなものもあるから、いつ騙されてもおかしくない。

あんな:最近だと、新型コロナウィルス(COVID-19)関連のデマがSNSで拡散してるよね。「東京は◯月◯日からロックダウンする」という特定系から、「新型肺炎は生物兵器」とか「ビル・ゲイツの陰謀説」みたいなトンデモまで。不安な時を狙って、デマを流すのはやめてほしい。私たちみたいな素人でもできるファクトチェックの方法はありますか?
しもむら:ある程度までは見極められます。ただ「減災」はできても、100%の「防災」は困難です。あるニュースがフェイクかどうかを突き止めるのって、実は専門性と労力の必要なことで、個人が独力で確定的に見極めるのは大変なんです。
だからこそ、日本でも2017年6月に「FIJ(ファクトチェック・イニシアティブ・ジャパン)」という団体が設立されました。新型コロナウィルスに関するファクトチェックの結果を一覧できる特設サイトもこの団体が作っていて、BuzzFeed Japanや毎日新聞、中京テレビ、琉球新報などの「メディアパートナー」が実際に記事のチェックをおこなって、検証結果を報告しています。
あんな:そのサイト見ました! 世界的にも「国際ファクトチェックネットワーク」という組織があって、同じような活動をしているみたいです。ハッシュタグは、#CoronaVirusFactsとか#DatosCoronaVirus。
かん:そういえば、Twitterのフェイク動画や嘘の情報を流す投稿に「操作されたメディア」とラベルをつける取り組みがニュースになってましたが、そういう工夫は助けにはならないんですか?
しもむら:それなりの目安にはなるでしょう。ただ今後は、どういう基準で「フェイク」と判断するか、また誰がそれを行うか、といった審査基準の問題をちゃんと考えないと危うさもありますよね。
あんな:それを聞いて思い出したのが、Twitter Japanと日本青年会議所(*1)が組んでメディアリテラシーを高める取り組みをすると発表して、即炎上した事件。私もウォッチしてたんだけど、暴言をリツイートしていたりしていて、「メディアリテラシーとは?」って頭を抱えたし、Twitter使うのが怖くなっちゃった。
*1=日本全国700弱の青年会議所を束ねる調整機関として、1951年に設立した。青年会議所では、原則20歳から40歳までの入会制限のもと、会員たちによるボランティアや地域振興など多岐にわたる活動を行う。国会議員をはじめ、知事、市長、地方議員などを多く輩出している。

かん:あれ本当になんだったんだ!?
しもむら:実は僕は、その日本青年会議所とは、2年ぐらい前から相談に乗ってる関係なんです。だけど、本当に真剣に取り組もうとしてる一群と、意味を勘違いして暴走する一群とがずっと並存してて、なかなか治りません。見放したら後者が勢いづいちゃうから、僕はガックリしつつ前者を励まし続けてるけど……。
かん:いろんな内部事情があるんですね。でも受け手側にはそんなのわからないし関係ないから、正直、責任感持ってコントロールして欲しい!
しもむら:まさにその通りの言葉を、僕も彼らに直言してます。で、話を元に戻すと、ファクトチェックの体制を担うのは、ジャーナリズムの使命です。ただ、正確なファクトチェックをするためにはマンパワーも手間もコストもかかります。その一方で、デタラメな情報はなんの苦労もなく作れてしまうから、果てしないもぐら叩きになってしまうし、デマの根絶は難しいんです。
かん:えー、じゃあどうすればいいんでしょう。
しもむら:そこで身につけてほしいのが、メディアリテラシーなんです。フェイクニュースが拡散してしまった後の、治療をするのがファクトチェックの役割だとしたら、拡散を予防するのがメディアリテラシーの役割。予備知識のない情報が目の前に現れ、見極める知識も時間もないときにどう扱うべきか。リテラシーを高めて、フェイクニュースに対する免疫をつける必要があります。
スマホが普及した現代は、SNSを通して誰でも発信ができる「国民総発信者時代」。なのに、メディアリテラシーについてきちんと教えられていないんですよね。
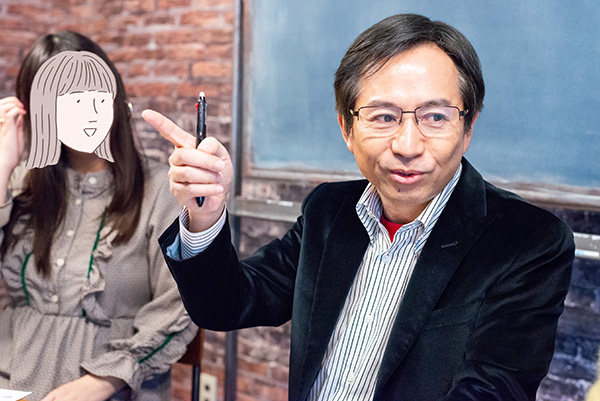
かん:確かに、きちんと授業とかで教えられた記憶ない。
しもむら:でしょ? それが問題なんですよ。デマやフェイクニュースのパンデミックを防ぐには、ジャーナリズムのファクトチェックという解熱剤治療と、個人のメディアリテラシーというワクチンが必要。日本中の人にメディアリテラシーというワクチンを打って回るのが、僕のライフワークです。
かん:自分で真偽を突き止めるのは難しいって言ってもらえて、ちょっと気楽になった!
あんな:メディアリテラシーワクチン、打ってくぞ~。まずは、最低限必要な基本のキを教えてください。
<ポイント>
Q.「フェイクニュースってどう見分けるの?」(あんな)
A.「素人がフェイクニュースを見分けるのは難しいけど、減災はできる! ジャーナリズムのファクトチェック体制と、個々人のメディアリテラシーの両輪が必要」(しもむら)
- NEXT PAGE最低限必要なメディアリテラシーを教えて
- 1
- 8