人と比べるんじゃなくて、「私は昔の自分より20%よくなれた!」と思えたら、自分にとっても他人とコミュニケーションするうえでも、ハッピーになれると思う。
─詩は遠くの作品ではなくて、もっと人間の営みに近い、身近なもの。
永原:そうですね。それと、“あそんでいきよう”という曲には、<What is The MUSIC?>という歌詞があります。谷川さんの詩に「自分は詩人なのか?」という問いかけがあるとしたら、これは「食べて働いて寝て、それで、音楽って何?」という音楽に対する問いを含んだ曲で。

─さきほど引用したTwitterでも、「戦う生活労働者たちに捧げるべく、寄り添うべく、最高にノリノリなブルースをつくりました」と書かれていましたけど、永原さんにとって音楽というのは、食べることや眠ることといった生活と地続きにある、ひとりひとりに寄り添うものであって、特別なものじゃないんだ、という想いを感じます。
生活のなかで思わず歌いたくなるような、詩的な言葉をひとつでも吐き出したくなるような、そういう人間の心を包み込む応援歌。けして「特別になれ」とは言わない優しい歌というか。
永原:前に、インタビューで「何者かになろうとしなくてもいい」って言ったことがあるんですけど、それは、そんなことよりも大事なことがいっぱいあるじゃん、って思ったからなんです。みんな、食べて寝て働いて、それだけですごく大変なんだから、さらにそんなに重荷を背負わなくてよくない? って。
でも最近は、実は何者かになる・ならないというのは二択じゃなくて、自分が変化したときの幅を、自分でちゃんと認めてあげられることが大事なんじゃないかな、と思うようになりました。大事なのは、「私はあのときより20%変わった」とか、そういうささやかな変化に自分で気づくこと。俯瞰した統計学的な視点で見ると「私はあの子に比べてダメだ」と悲観してしまうけど、自分のバロメーターで「私は昔の自分より20%よくなれた!」と思えたら、自分にとっても、他人とコミュニケーションするうえでも、ハッピーになれると思う。そう思えるようになってきました。
─「何者かにならなくていい」と決めつけるのではなくて、きっとみんなゆるやかなペースで変化しているし、それに自分で気づくことが大事なんじゃないかということですね。いつ頃から考えが変わってきたのですか?
永原:ここ1、2年ですかね。特に自分がバンド(SEBASTIAN X)を休止してから(現在は活動を再開)、今回のソロのフルアルバムをつくれるようになるまで、気持ちが追いつくことも考えたら2年半くらいかかっていて。20代から30代になったという年齢の変化もあって、圧倒的に体も変わったんですよね。それもあって心身ともに、自分の音楽をまた楽しめるようになるにも時間がかかりました。
変化って時間がかかるけど、それこそ一度にくっきりと変わるんじゃなくて、グラデーションみたいにゆるりゆるりと変わっていくんだなって実感していて。だから今回のタイミングでのソロアルバムでは、ひとりひとりの個人のグラデーションに寄り添える音楽をつくることを目指しました。
<「ぼく」のように「わたし」のように 歌ってみなよ すきな声で>("HAPPY GO LUCKY"より)
永原:同時に、自分の内なるものに初めて向き合ったのが、多分このアルバムだと思います。SEBASTIAN Xではバンドという形態上、4人の集合体を代弁したいという気持ちでずっと書いていて。だから個人というより、「この4人の価値観はどんなふうだろう?」「この4人とお客さんとでつくってきた空間や雰囲気ってどういうものかな?」ってことからインスピレーションを受けて、ずっと詩を書いてきました。なので、私だけが見たもの、体感したもの、匂ったもの、触ったものと、自分の内なる感覚を響き合わせてつくったアルバムは初めてです。
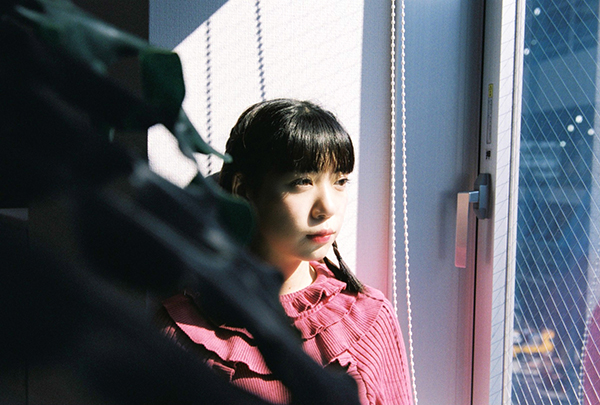
─つくってみて、どんな変化がありましたか? これから、いろいろな人に聴いてもらってから感じることもたくさんあるとは思いつつ。
永原:このアルバムは、大切な友達に聴かせて、褒められたら、もしかしたら今までよりも、一番嬉しいかもしれない。それは、怒りや不満と同時に、私がつくりたい全力の理想郷を込めているから、それを「素敵ね」って言われたらすごく嬉しいな。私は私に興味があるんじゃなくて、自分を介して世界を見て、聴いて、そうやってつくられたものに興味があるのかもしれない。
というより、自分を介してしか作品はつくれないから、作家としては、むしろ「自分」という存在は足かせですよね。もっといろいろな人間に憑依できたら、いろいろな詩が書けたり、いろいろな声で歌えたりするのに。だから「自分」なんて言うのはある種、制限だと思っている。だから、曲を聴いてもらったときに、私が何を考えているのか汲み取ってもらうことより、そこからそれぞれイメージを膨らませてもらったり、「夜帰るときに聴いてみたいな」と感じてもらったり、そういうひとりひとりの感受性を信じているし、感じてもらえたら嬉しいです。
音楽が鳴っているときぐらいは、もっと心に嘘をつかない場所がそこにあってもいい。
─自分と向き合ったアルバムだからといって、「私を見て」ということではなくて、永原さんが五感でとりこんできたイメージや理想を、純度高く形にできたということですね。
永原:そうですね。今回は頭で考える思想よりも、時には怒りだとか呑気さだとか、自分の感情のボルテージに素直になって、音楽をつくることができました。もちろん感情を説明するときには言葉が必要だし、それもすごく大切なのですが、究極的には私が伝えたいのは言葉の先にある、あるいは言葉の前にある感覚なので。
曲を聴いてもらって、私が到達したい地点というのは常に、「すごくいい曲」って思ってもらうこと。それが到達点だから、この曲も言葉も、その感情に届くまでの経由地点でしかない。本当に理想的なのは、外国にも飛べて、小さい家にも行けるような、そういう作品をつくること。感情の回路図みたいなものがあるとしたら、そこを音楽で移動したい。音楽や詩は、それでしかないと思います、いつも。

─永原さんはよく「光」という言葉を歌詞に使っていますよね。それは、表面的な言語や、理性的な思考を飛び越えて人に届くものとして、象徴的だと思うんです。音楽も光のように届いて、心を灯したり照らしたりしたいと願って、祈っているというか。
永原:だって、理性的だと葉っぱは集められないですから(笑)。理性があると、どの葉っぱを拾っていいかわからなくなってしまう。意味を求めていたら、気持ちが隠れてしまう。理性的に思考する場面ももちろん大切だと思いますけど、今、社会は十分そういう理屈で成り立っているじゃないですか。だったら、音楽が鳴っているときぐらいは、もっと心に嘘をつかない場所がそこにあってもいい。
私の音楽は、一生懸命働いて、食べて、寝るーーそういう人に、捧げたいと思いました。ちゃんと生活しないと、体を壊しちゃうし、よく寝ないと翌日動けないから、たっぷり寝なくちゃいけない。そうやって毎日生きている人の人生のBGMになる瞬間があったら、このアルバムはすごく幸せなんです。それが私の、祈りですね。
- 3
- 3


















