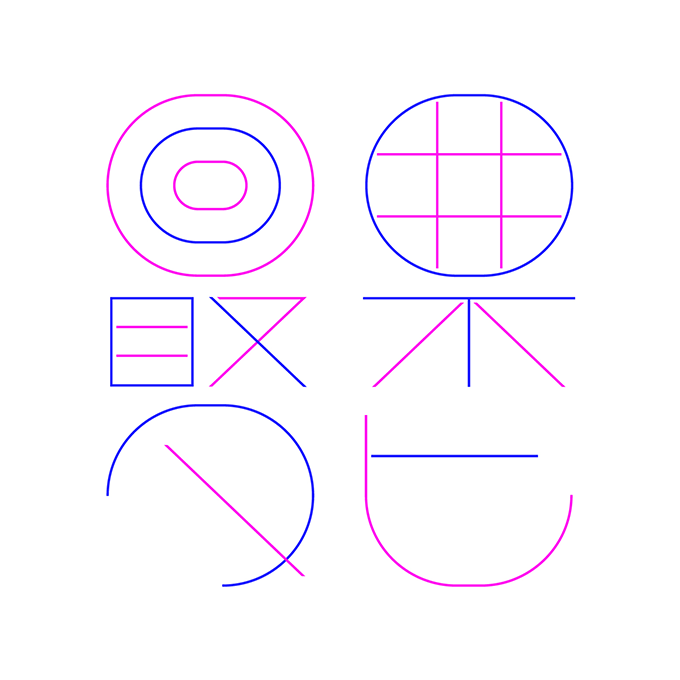「みんな」そう思っているからやめましょうと、「みんな」のせいにするのはよくない。(最果)
─今回、詩の水筒にどんな詩をのせるかというところで、「死」という言葉について議論したんですよね。この詩には、多くの「死」という言葉が使われていて。Membersの登録している方々すべてに届くという前提にたったときに、その言葉を重ねて使っている詩をどう扱うかについて。詩の冒頭から「死なない湖、死なない丘の」とはじまるので、もちろん「死ね」と言っている詩ではまったくないのですが……。
最果:そうですね、「死ね」とは言ってないです。
佐々木:「死」という漢字が多く使われているということですよね。

最果:もともと提出した詩にたいして、She isさんから「死は一般的にネガティブな言葉とされているのでできれば避けてもらえたら……」といった連絡があったんです。NGが出たことより、その言葉がだいぶ衝撃でした。
─それは編集部として、本意ではないお伝えの仕方でした。私と担当者の間で「死という言葉にたいして、その人が置かれている状況によって、もしかしたらのっぴきならなさというか、取り返しのつかないほどの反応をしめす個人がいるかもしれない」という考えがあってのギフト担当者からのご連絡だったのですが、伝え方の共有ができていなかったこともあり、改めて申し訳ありませんでした……。
最果:いえ、怒ってはないんです、「一般的にネガティブって……な、なんだ?」ってなって。「これからのルール」ってテーマなのに、めっちゃ「これまでのルール」の話だな、というのがすごく気になって、特にShe isさんのような場所だからこそ、ちゃんと話を聞きたいと思いました。
─そう感じると思います。「一般的って誰を指しているの?」となると思います。
最果:日本は、死を穢れとする風潮がまだ強く残っていますよね。それってどうしてだろう? という気持ちがすごくあるんです。結局誰しもが死ぬのに、死のことを語ってはならないとするならば、本当に死のことに直面している人だけが、死について考えなくてはならなくなって、とても孤立してしまうという感覚をずっと持っています。
もちろん、人によって極度に死を恐れる人もいるはずですし、それはその人の人生によって培われた感覚だから、むしろ絶対に尊重されるべきと思います。ただ、発信する側としては、発信する/発信しない、のどちらを選ぶにしても、「みんな」そう思っているからやめましょうと、「みんな」のせいにするのはよくないんじゃないかと思ったんです。
─おっしゃるとおりだと思います。
最果:さっきのルールの話と一緒で、誰かが定義づけた言葉をそのまま使ってしまうことって、ルールによって苦しめられる構造につながるように思います。「一般的に死がネガティブ」っていう定義も、社会が与えたものです。それでいうと、すべての死が不幸であるということになってしまって、それはすごく悲しいことです。絶対にみんな死ぬのに、死は不幸中のことだと決定づけてしまったら……。死との不幸な出会いはどうしてもあると思います。ただ、生きて生きて、その末に、その集大成としてその時間があるということを忘れたくないと思います。
たとえば死が排除された世界で、それでも死のことを考えてしまう人がいたとして、でもあなたには死という言葉を与えません、なぜなら「みんな」が死を避けることを望んでいるから、というのはある種の暴力じゃないかと思います。かといって、そういう人がいるから、「みんな」絶対に死ということを考えましょう、話し合いましょう、というのも違う。だから、発信者が言葉を使うとき、そこには、言葉を「与える」か「奪う」のどちらかしかないんです。誰かのせいには絶対にできない。「私がこう思うからこう伝えます」という態度がとても大切だと思うんです。
She isが、She isとして「発信しない」というのを選ぶのなら、それは尊重したいと思いました。「みんな」を理由にしないのならば、それはShe isの考え方であるし、She isがShe isであるために必要なことだと思うから。だから、She isとしての考えを聞きたくて、メールでたくさん話し合いをしました。
今回は、「これからのルール」というテーマを踏まえて「社会をリセットするんだったら森だな」って思ったときに、森は死骸と共に生存している動物たちがいて、死を書かないことの方が不自然だと私は思っていました。またなによりも、「生きること」を描くとき、そのなかに死はどうしてもあって、それを書かないというのは、生すらも不自然にするとも考えていたので、だから「死」がこの詩には登場しています。

─今回は発信者として、「最果さん」と「She is」の両方がいると考えたときに、She isとして、さまざまな背景をもったひとりひとりが「死」という言葉とともに詩を受けとるときの「補助線」をひかせてくださいという相談をしたんですよね。それは、最果さんからコメントをいただくということでした。
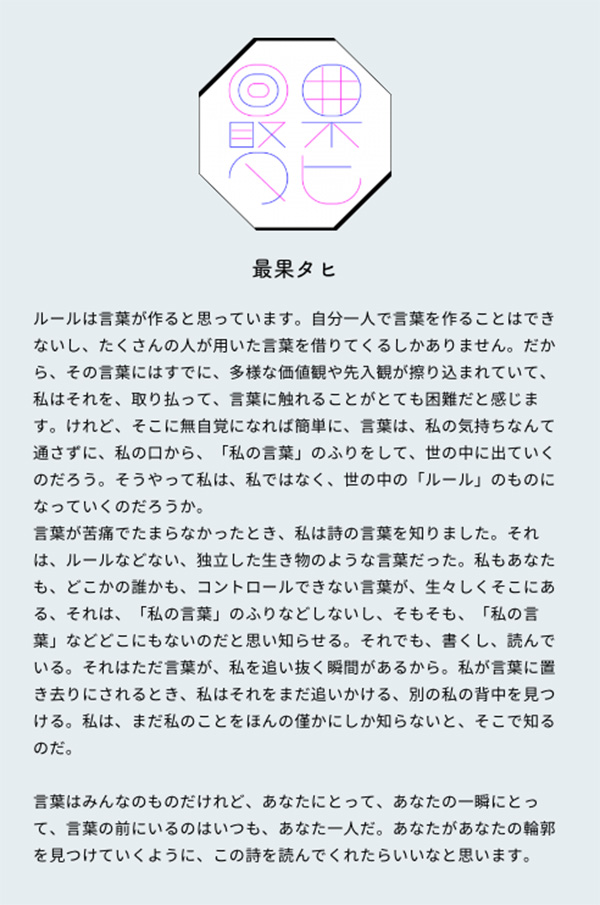
最果:一連のやりとりを経て、She isは改めて、読んでいる人に「考える」ことをそっと促すメディアだと感じましたし、詩からさまざまなことを思う人はいるだろうけど、それを否定することもなく、それでいて、別の視点をこちらからも伝えられることができたらいいなと思いました。